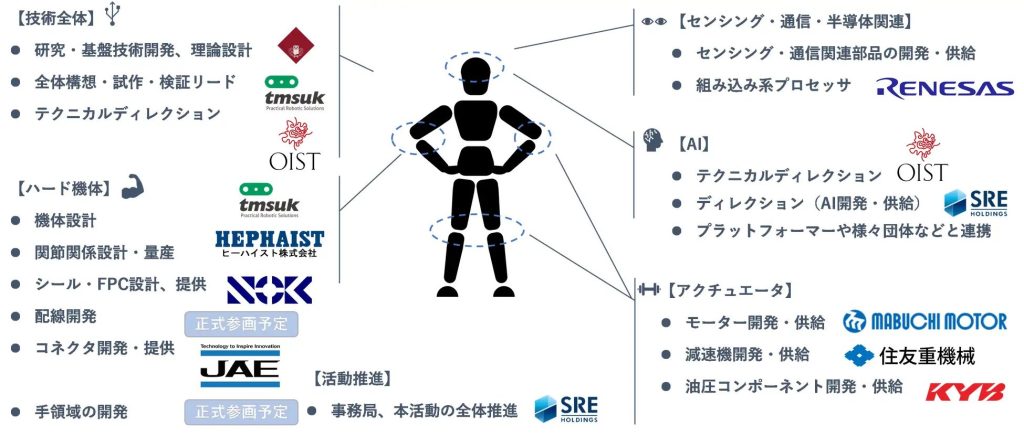東海国立大学機構と富士通、生成AIで治験選定を高速化 日本のドラッグ・ロス解消に道筋

2025年5月23日、東海国立大学機構と富士通は、生成AIを活用して治験候補患者を選定する実証実験の成果を発表した。医療データの解析を通じ、日本国内で深刻化するドラッグ・ロスの解消を目指す先進的な取り組みである。
生成AIが非構造化医療データを90%の精度で解析
富士通と東海国立大学機構は、生成AI技術を用いた治験候補患者選定の実証実験を行い、その有用性を明らかにした。今回の実験は、名古屋大学医学部附属病院および岐阜大学医学部附属病院に蓄積された約1800名分の乳腺外科診療データを対象としたものである。
これまで治験に必要な患者の抽出は、医師の所見や診療記録といった非構造化データの扱いが障壁となり、時間と労力を要していた。だが、生成AIを活用することで、こうした非構造化データの約90%を精度高く構造化することに成功した。
さらに、過去に実施された3件の乳がん治験をモデルケースに、AIが候補患者をスクリーニングした結果、42名が抽出され、そのうち7名が実際に治験に適合する患者であると判明した。
従来と比較して、選定作業にかかる時間が約3分の1に短縮される可能性が示された点にも注目できる。
この取り組みは、承認されていない医薬品の使用機会を逃す「ドラッグ・ロス(※)」の解消に寄与することを目的としている。
※ドラッグ・ロス:海外では承認・使用されている医薬品が、日本国内では制度や薬価の制約により使用できない状況を指す。適切な治療機会を逃す要因とされ、医療格差の一因とされている。
治験の効率化が医療と産業に波及 今後の課題は制度と連携体制
今後、富士通はこの成果をもとに、生成AIによる医療データの解析機能を拡張していく方針だ。実証実験で用いられたのは、同社のクラウド型プラットフォーム「Healthy Living Platform」であり、ここに生成AIサービス「Fujitsu Kozuchi Generative AI」が組み込まれる形となる。
サービス提供は2025年5月30日に開始予定で、他疾患や医療機関にも応用を広げる計画が進められている。
また、治験支援を行うParadigm Healthのプラットフォームとの連携により、今後は製薬企業や医療機関を横断するエコシステムの構築も視野に入れている。将来的には、富士通が開発する大規模言語モデル「Takane」との連携を通じて、さらに高度な患者選定や臨床データ解析が可能になる見込みだ。
一方で、AIが解析したデータを実臨床へ円滑に統合するには、薬事制度や倫理面の整備も不可欠である。生成AIの活用は治験の効率化に大きな期待が寄せられるが、データの正確性や偏りのリスクは留意すべきだろう。
技術と制度の橋渡しが、今後の成否を左右する鍵になると思われる。