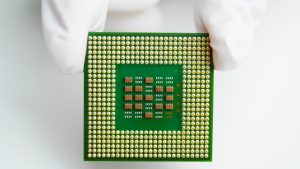米NVIDIAのNVLink Fusionで進化するAIインフラ 富士通MONAKAが対応へ
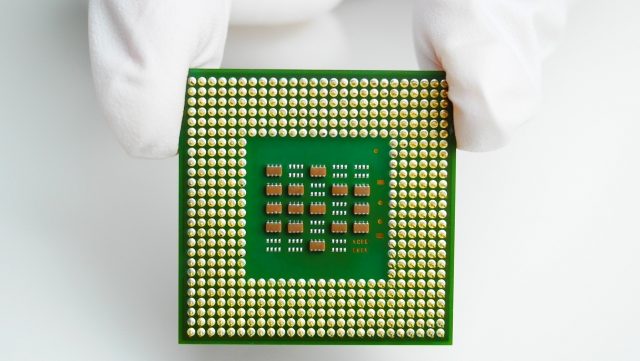
2025年5月19日、米NVIDIAは新インターコネクト技術「NVLink Fusion」を発表した。富士通が2027年に投入を予定している次世代CPU「FUJITSU-MONAKA」は、このNVLink Fusionとの接続に対応する見通しであり、AIインフラ構築における柔軟性と性能向上への期待が高まっている。
異種CPUとの接続を可能にするNVLink Fusion
NVIDIAが発表した「NVLink Fusion」は、自社製GPUと他社製CPUやASIC(特定用途向け集積回路)との直接接続を可能にする新しいインターコネクト技術(※1)である。これまで同社のNVLinkは、自社製CPU「Grace」との組み合わせを前提としていたが、新技術により接続対象の幅が広がった。
初期の対応パートナーとして名を連ねたのは、富士通および米Qualcomm Technologiesである。
富士通が2027年に投入を計画している次世代CPU「FUJITSU-MONAKA」は、2ナノメートル技術を採用したArmベース(※2)の省電力CPUであり、同社のクラウドインフラやAI用途において中核を担う製品とされている。
富士通CTOのヴィヴェック・マハジャン氏は、「MONAKAがNVIDIAのAIプラットフォームと連携することで、従来にないレベルのパフォーマンスと省電力性の両立が可能になる」との見解を述べ、技術的な相乗効果を強調した。
富士通とAMDの協業も進行中 今後の展望
富士通はNVIDIAに加え、24年11月に米AMDとの協業も発表している。同社はAMDのAI向けGPU「Instinct アクセラレータ」と組み合わせを視野に入れており、自社のAIサーバーにおいて複数のGPUベンダーと連携する方針とみられる。
これにより、同社はGPU依存度を分散しつつ、技術的な選択肢を広げる構えだろう。
こうした戦略は、AI分野における需要の急拡大とともに、パートナーエコシステムの構築が企業競争力に直結する時代背景を反映していると見られる。特に、NVIDIA製GPUの供給に制約が生じるリスクや、米中摩擦の影響を考慮すると、複数ベンダーとの協力体制は重要なリスクヘッジにもなり得る。
NVLink Fusionの登場は、NVIDIA自身がオープンなAIインフラ市場での競争に本格的に関与する姿勢を示すものとも捉えられる。他社製CPUとの親和性を高めることは、自社GPUの採用拡大にも直結するため、NVIDIAにとっても中長期的な戦略の一環といえるだろう。
MONAKAの正式投入は2027年を予定しており、今後の仕様確定や他社GPUとの実装事例の登場が注目される。
AIインフラを取り巻くハードウェアの選択肢が拡大する中で、MONAKAのような柔軟なプラットフォームの価値はさらに高まる可能性があるだろう。
※1 インターコネクト技術:CPUやGPUなど異なるプロセッサ間で高速なデータ転送を実現する通信方式のこと。システム全体の性能やスケーラビリティに大きく影響を与える技術領域である。
※2 Armベース:英Arm社が設計するCPUアーキテクチャで、低消費電力・高効率を特徴とする。近年はサーバー用途やAI処理にも活用が進んでいる。