フジ清水社長と堀江貴文氏、大学で特別講義 AI活用でメディア改革を提言
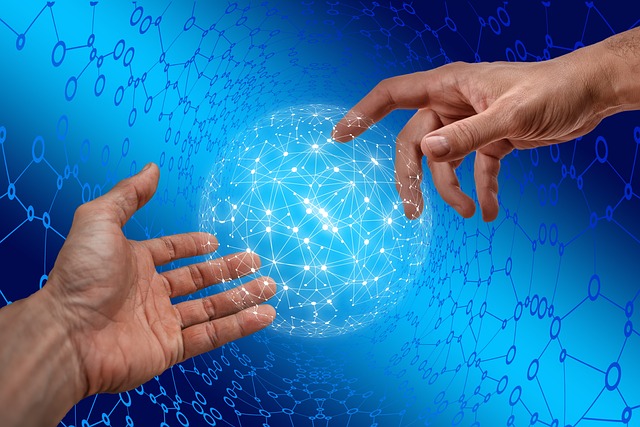
2025年7月22日、フジテレビの清水賢治社長と実業家の堀江貴文氏が、東京都内のiU情報経営イノベーション専門職大学で開催された特別授業にゲスト登壇した。
生成AIの活用やメディアの変化について議論し、次世代のコンテンツ創出に向けた展望を語った。
生成AIでメディアの限界を突破 両氏が授業で示した未来像
フジテレビ・清水賢治社長と堀江貴文氏は、iU情報経営イノベーション専門職大学の江端浩人教授が担当する「クロステックビジネスデザイン」の特別授業に招かれ、「メディア」「コンテンツ」「サブスクリプションビジネス」「生成AIの活用」をテーマに講義を行った。
両氏はAI技術の進展がメディア産業にもたらす可能性について語り合い、清水社長は「メディアの上に乗っかるコンテンツは無限大になっている」とした上で、「作れる物もたくさん作れる。作るのにすごくお金のかかる物もあるけど、AIを使えば、画像処理も簡単にできる」と述べた。
堀江氏はAI事業について「早くやった方がいいですよ」と強調し、AIを用いた新規事業の推進を呼びかけた。
清水社長は「絶対そこに勝機がありますよね。これはいくらでも試せるのが良いですよね。
テレビは不自由で準備するのに何カ月もかかってしまう」とし、既存の放送形態からの脱却に意欲を見せた。
また 堀江氏は、テレビ業界が変革に踏み出せない要因として「イノベーションのジレンマ(※)」を挙げ、現場の社員は変化を起こしづらいのではないかと問いかけた。
これに清水社長は同調し、「過去の成功モデルが本当に邪魔をしている。別にiPhone一つでできるなら、試してみればいいと思う」と現状打破の必要性を強調した。
※イノベーションのジレンマ:企業が既存の成功モデルや収益構造に固執することで、新たな技術やビジネスモデルへの対応が遅れ、変化に取り残されてしまう現象。クレイトン・クリステンセンによる提唱。
生成AIは“補助”から“共創”へ メディア制作の構造変革
今回の特別授業で語られた生成AIとメディアの融合は、今後のコンテンツ産業において転換点となる可能性がある。
生成AIの導入によって、制作コストの削減やスピード感ある実験的コンテンツの創出が実現しやすくなると考えられる。
特にテレビ業界のように制作準備に多大な時間と人手を要する現場では、生成AIが“制約からの解放”として機能する場面も出てくるかもしれない。
一方で、AI生成コンテンツには著作権や倫理、品質保証といった面で未整備な点が多く、乱用や信頼性の低下といったリスクが懸念される。
制作の自由度が高まる反面、視聴者や社会が求める「公共性」や「編集責任」をどこまで担保できるかは、引き続き議論が必要とされるだろう。
今後、生成AIはテレビをはじめとするマスメディア全体において、「補助技術」から「主体的な制作パートナー」へと役割を広げていく可能性がある。
例えば、ニュース制作やバラエティ番組の編集、スポーツ中継の補足映像などの領域で段階的に活用され、効率化と多様化が同時に進んでいく展開も予想される。
関連記事:https://plus-web3.com/media/horietakahumiaigoukakugimon20250408/












