気象分科会、AI気象予測の技術開発を提言 気象庁の中長期戦略に反映へ
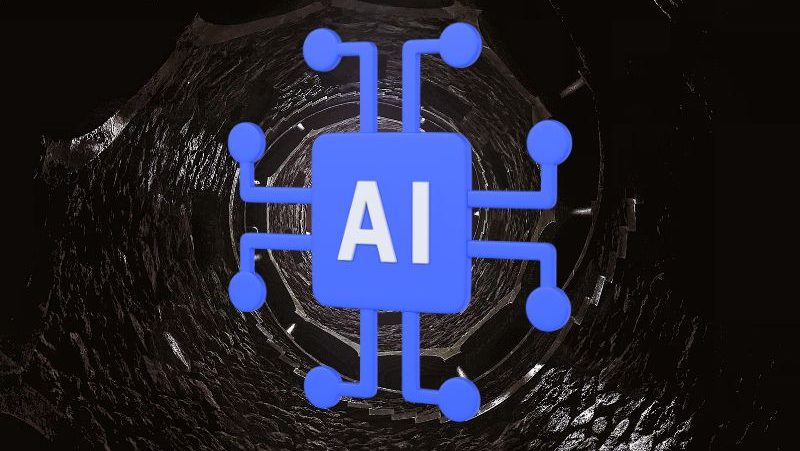
2025年6月27日、国土交通省の交通政策審議会気象分科会は、気象庁が今後講じるべき中長期施策として、AIを気象予測に活用するための技術開発や気候変動情報の高度化を提言した。
気象庁はこれを踏まえて施策を進める方針である。
AIによる気象予測実現へ体制強化進む
交通政策審議会気象分科会がまとめた提言では、AI活用のための技術開発を次世代の気象業務の柱と位置づけている。
特に、ディープラーニング(※)を用いて気象庁が保有する膨大なデータから気象変化の兆候を自動抽出し、精度の高い予測を行うシステムの実装が想定されている。
これに先立ち、気象庁は2025年4月にAI活用の専門チームを設置し、研究体制の強化に着手していた。
現在の数値予報モデルとAIのハイブリッド運用も視野に入れ、予測の信頼性と即応性の向上を目指しているという。
また、2029年度に運用を開始する予定の気象衛星「ひまわり10号」の観測データ処理においても、AIによるリアルタイム解析の導入が検討されている。
極端気象の兆候をいち早く捉え、災害対応を迅速化する効果が期待されている。
※ディープラーニング:人間の脳の神経構造を模した「人工ニューラルネットワーク」を多層に重ねた機械学習手法。大量のデータから特徴を自動抽出し、予測や分類を行う。
精度向上と自動化に期待 導入には課題も
AIの導入により、予測精度の向上と業務の自動化が進む可能性がある。
とりわけ短時間豪雨や突風などの局地的な現象については、従来モデルよりもAIの方が変化の兆候を早期に捉える力があるとされている。
これは、災害リスクの低減や住民避難の判断材料として極めて重要だ。
一方で、AIによる予測結果の信頼性をどのように検証するかという課題も残る。気象は非線形で不確実性の高い分野であり、AIが誤学習するリスクも考えられる。
また、既存の業務プロセスとの整合性や職員の運用スキル向上も導入の成否を左右する要素となるだろう。
これから、多様なアプローチを交えながら、気象庁はAIによる次世代予測体制の構築を段階的に進めていくとみられる。技術開発が進めば、より高精度で迅速な気象予測が実現し、防災・減災への貢献が一層期待される。












