JR東日本、信号トラブル復旧に生成AI導入へ 復旧時間を最大50%短縮
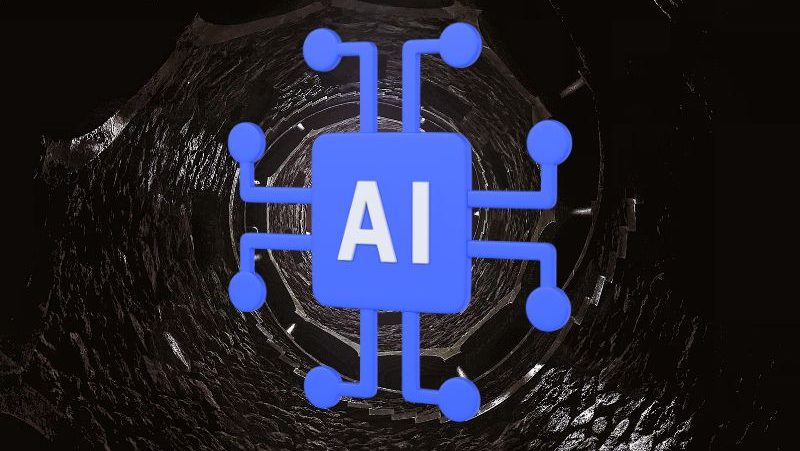
2025年6月10日、JR東日本は信号通信設備にトラブルが発生した際の復旧作業支援に生成AIを導入すると発表した。復旧までの時間を、従来の最大半分に短縮できる見込みだ。
AIが無線通話を解析し、現場対応の効率化へ
JR東日本はDXを推進しており、将来的には2027年度末までに「鉄道版生成AI」の完成を目指している。今回の導入はその一環として、生成AIを復旧支援に活用するものである。
同社は2023年3月から、首都圏の在来線信号設備の一部において、故障発生時に指令員の判断を支援する「AI解析システム」を導入している。
指令所の社員は、無線で現場の状況を聞き取り、原因の分析や対応策を検討しているが、復旧までの時間や作業の属人性が課題とされてきた。
そこで今回、社員同士の無線通話の音声を自動的にテキスト化する生成AIシステムを取り入れる。
生成AIが情報を解析し、トラブルの原因特定や対応方針の提示までを即座に復旧支援システムに反映することで、人的作業を大幅に削減できる見込みだ。
具体的には、復旧までの平均所要時間を最大約50%短縮できる見込みだという。
また、JR東日本は、生成AIの導入と並行して、さらなる活用の可能性を探る実証実験にも着手する。
日立製作所と連携し、首都圏の鉄道運行管理システムに生成AIを導入する実験を2025年9月から開始する計画である。鉄道運行管理という大規模インフラでの生成AI活用は国内初となる。
AI活用の拡大へ 鉄道業界で進む実証実験と課題
今回のシステムは、音声認識と自然言語処理を組み合わせたリアルタイム情報解析が強みであり、特にトラブル発生時の初動対応力を高めることが期待できる。
一方で、誤認識や過剰な自動化による判断ミスへの懸念も残るだろう。
AIによる分析結果が現場判断と乖離するリスクや、AI依存によるスキル低下なども今後の検討課題となる可能性が高い。
とはいえ、人口減少と人材確保が難しくなる中で、AIによる効率化と運行安定化は避けて通れないテーマだろう。
鉄道という社会インフラにおける生成AIの本格運用が進めば、他業種への波及も期待できる。
今後の実装状況や成果は、国内外の交通インフラ関係者にとっても重要な試金石となるだろう。












