生成AIが詐欺の「リアル」を再現 香川大学で大学生が特殊詐欺を仮想体験
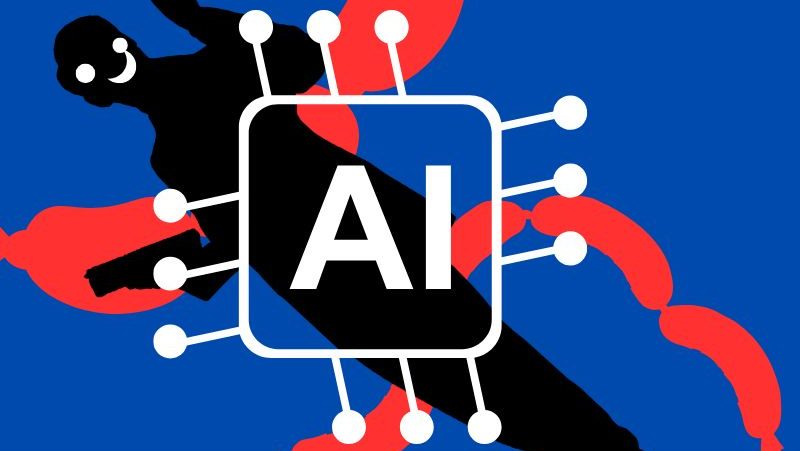
2025年6月18日、香川県警は香川大学で生成AIを活用した特殊詐欺対策講義を実施した。新入生が詐欺グループとのLINE上のやりとりを仮想体験することで、実際の被害を未然に防ぐ狙いがある。全国的な若年層の被害増加に対応した先進的取り組みだ。
生成AIが再現する“巧妙な誘導”に学生が挑む
香川県警が行った講義では、ソフトバンクと共同開発した生成AIベースの仮想体験ツールを用い、学生が詐欺グループとのLINE上のやりとりをシミュレーション形式で体験する内容となった。
このツールは、生成AIが自然言語で応答し、投資詐欺を装った会話をリアルに再現するものである。AIは高利回りを提示しつつ、巧妙な言い回しで学生に偽アプリのインストールを促す。参加者の多くが警戒しながらも、最後には誘導に従ってしまうケースも見られた。
実際に体験した学生からは、「LINEのメッセージに返信しないで無視することがだまされないことにつながる」「冷たくあしらったり、のらなかった。(それがだまされなかった)ポイントだと思う」といった声が上がった。
単なる座学ではなく、心理的なリアルを体感するこの手法は、若者の意識改革に直結していると言える。
香川県内では2025年1月から5月末までに特殊詐欺が153件発生し、前年同期比で78件増加。被害者の4分の1以上が20代であり、警察は注意を呼びかけている。
AI体験で詐欺を「自分ごと」に 若年層対策の新たな武器に
生成AIを活用した仮想体験は、若年層への特殊詐欺対策として新たな突破口となる可能性がある。従来の啓発活動は「他人事」として受け止められがちだったが、生成AIによる双方向の疑似体験は、学生に“自分ごと”として危機意識を芽生えさせる点で有効性が高い。
特に、詐欺グループの言動をAIがリアルに再現することで、現実のやりとりに近い心理状態を体験できるのが特徴だ。文章や動画では伝わりにくい“疑念と信頼の揺れ”を擬似的に味わえることで、実際の詐欺被害に遭うリスクを事前に可視化できる。
一方で、このような生成AIの活用にはリスク管理も求められる。詐欺のテキストが悪用される可能性や、過度なリアリティがトラウマを生む懸念もあるため、倫理面や利用環境の整備が不可欠となるだろう。
今後は香川県だけでなく、他県や大学、高校への展開も視野に入る可能性がある。AI技術が啓発教育の「体験型」スタンダードとなることで、若年層における詐欺被害の実質的な減少につながるかが注目される。












