親子の会話、スマホで短縮傾向に 子どもはAIに疑問を解決依頼
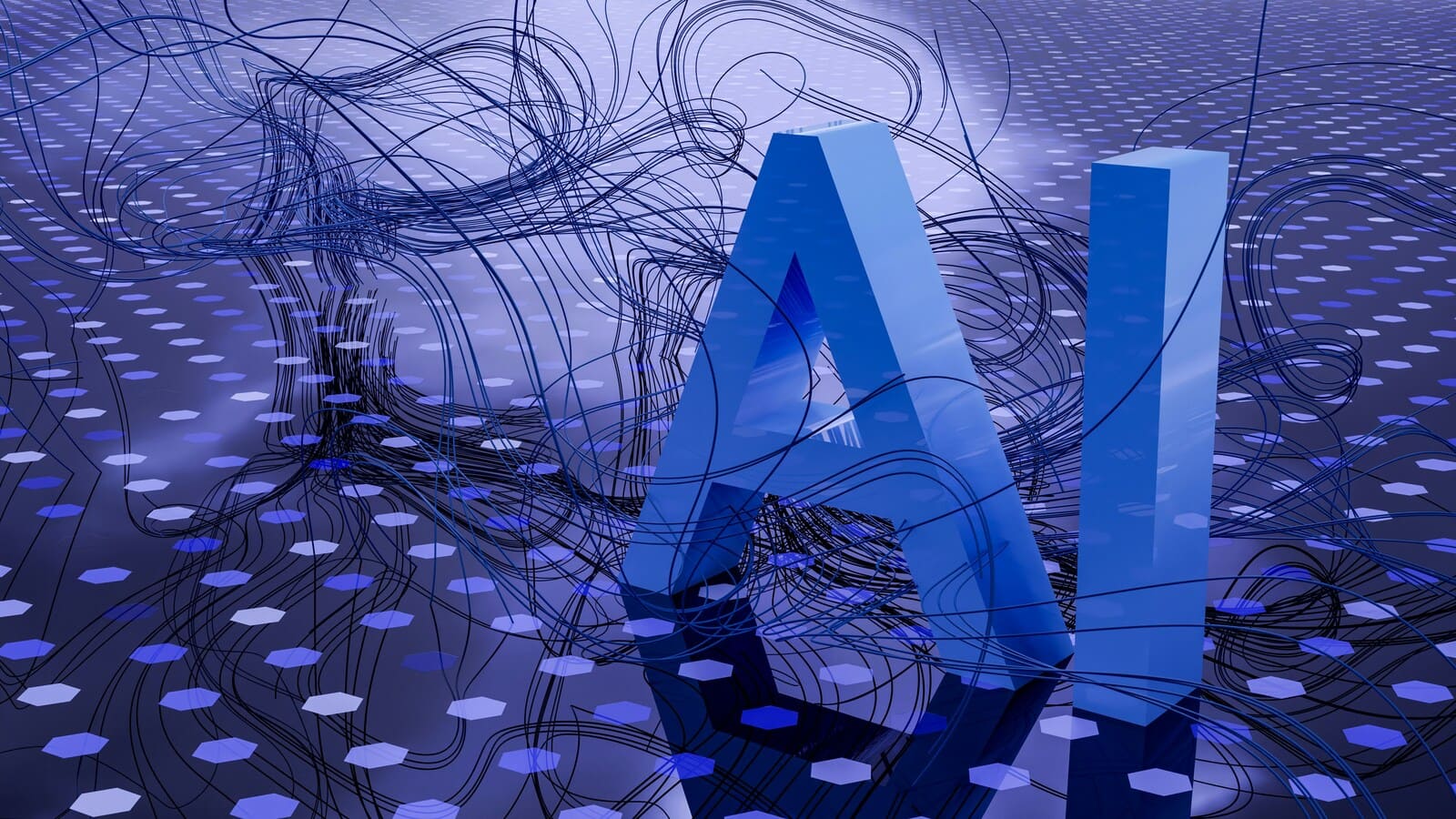
2025年6月9日、シチズン時計が実施した調査により、共働き家庭における親子の会話時間が13年前と比べて減少していることが明らかになった。
背景にはスマートフォンの普及と、人工知能(AI)の活用が進んでいる現状がある。
親子の会話、13年前より休日は20分以上減少
シチズン時計は6月10日の「時の記念日」を前に、小学生の子どもがいる共働き世帯の親子400組を対象に、家庭内での時間の使い方に関する調査を行った。
その結果、休日の会話時間は父親が1時間40分、母親は2時間3分であったが、2012年の調査結果と比較すると、父母ともに20分以上短縮していた。
平日の会話時間は、父親が平均52分、母親が1時間34分とされ、これもまた過去に比べて減少傾向にある。背景にはスマートフォンやタブレットの普及があると見られ、家庭内での過ごし方が変化していることが影響している。
同調査では、子どもたちが平日にスマートデバイスを使用する平均時間が、低学年で1時間46分、高学年で2時間12分に及ぶことも判明した。使用用途としては動画視聴が最も多く、ゲームや連絡手段が続いた。
特に注目すべきは、子どもが分からないことに直面した際の対応として、「親に聞く」よりも「AIに質問する」と答えるケースが増えている点だ。
家庭内のコミュニケーションの変化を象徴しているといえる。
AIによる家庭内の会話時間減少がもたらす長期的な影響
親子の会話時間の減少は、単なる生活スタイルの変化にとどまらず、子どもの情緒的発達や家庭内の信頼関係に影響を与える可能性がある。特に初等教育期における言語能力や対話スキルの形成は、日常の親子コミュニケーションに大きく依存しているとされる。
AIに質問するという行為自体は、即時性や正確性という面で利点があるが、それが常態化すれば、人と人との対話を通じた学びや思考の深化が損なわれるリスクがある。
また、保護者が子どもの興味や悩みに気づきにくくなることで、育児や教育への関与が希薄化する懸念も生じる。
一方で、家庭内でのAI活用を前提にした新たな教育モデルが構築される可能性もある。
親子でAIを共同活用し、知的探求を共有する体験を創出することができれば、対話を補完するためのツールとして、AIはより有用なものとなるだろう。
今後は、スマートデバイスとの関わり方を見直す取り組みが、学校や自治体レベルで進むと思われる。
時間管理や家庭内ルールの策定を通じて、親子の会話時間を意識的に確保する動きが広がれば、「AIと人間関係の健全な共存」が実現できるのではないだろうか。












