AI社会の分断に警鐘 全国最大級の学会で見えた「教育と共生」への道筋
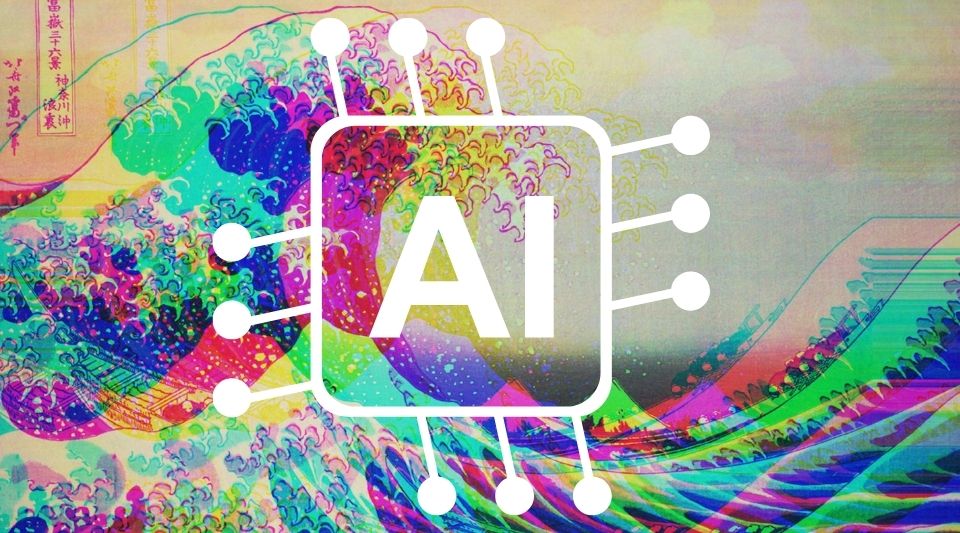
2025年5月27日、人工知能学会は大阪市内で第39回全国大会を開幕した。
研究者や企業関係者が集まる国内最大規模のAI学術イベントであり、技術成果や社会的課題について発表・議論が行われている。
AI活用の格差に懸念、教育と共生の視点強調
大会初日、学会の栗原聡会長は講演で「AIを使える層とそうでない人たちで格差が進む」との懸念を述べ、AIリテラシー教育の強化が不可欠だと訴えた。
特に子どもたちへの早期教育が重要であるとし、「自分のことを思って行動してくれる“バディAI”が必要となる」との見解も示した。
バディAIとは、日常生活や業務を支援する「伴走型人工知能」を示していると思われる。
会場では、日本製鉄が製造工程におけるAI活用の事例を発表した。
膨大な工程データをもとにした生産性向上への取り組みが紹介され、企業関係者の間で活発な意見交換が行われた。
今回の大会は39回目で、対面とオンラインを併用したハイブリッド形式。
最終日となる5月30日までの期間中、延べ4,000人以上の参加が見込まれている。
AIを「使える人」と「使えない人」の分断拡大への危機感
AI技術の進展が進む中、社会全体がその恩恵を享受するには、技術そのものの進化と同時に、人材側の受け皿を整える必要がある。
そのため、栗原聡会長が示した教育現場での取り組みに加え、企業や行政による実務的なリスキリングの支援も重要だろう。
AIの利便性が高まるほど、活用スキルを持たない人々が取り残される懸念も現実味を帯びてきた。
AIによる自動化や省力化が進むなかでは、雇用の質や働き方にも再設計が求められる可能性がある。
本大会で提示された「バディAI」のように、人とAIが協調して動くモデルが実現すれば、単なる技術競争にとどまらず、社会課題の解決や包括的な共生に向けた一歩になり得る。
政策の対応や各社の技術開発に、今後も注目したい。












