三重県、生成AI「ディープシーク」の利用を制限 情報漏えい防止へ向けた対策
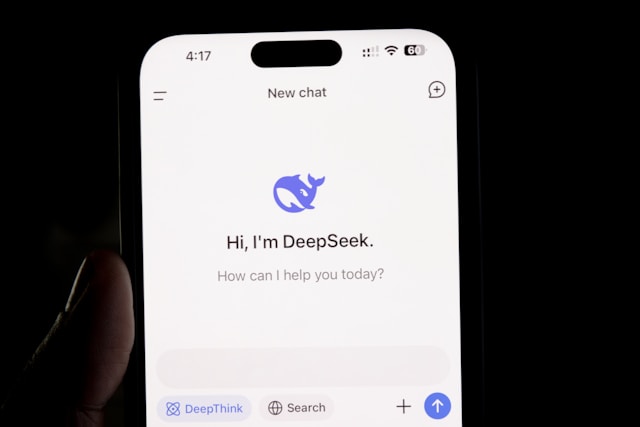
三重県は2025年2月7日、中国のスタートアップ企業「ディープシーク」が開発した生成AIの業務利用を制限すると発表した。
この措置は、情報漏えいリスクの防止を目的とし、県内約5500台のパソコンに対して同AIへのアクセス遮断が実施されている。
情報セキュリティ対策を強化するこの取り組みは、他自治体や企業にも影響を与える可能性がある。
情報漏えい防止を目的とした生成AI利用制限の背景
三重県がディープシークによる生成AIの利用を制限するに至った背景には、情報漏えいリスクへの懸念がある。一見勝之知事は2025年2月7日の定例記者会見で、同社に関する情報漏えいが指摘されていることを明らかにした。県内の重要な情報が外部に流出する事態を未然に防ぐため、この措置が講じられたと説明している。
具体的な対策として、2025年2月6日から県内約5500台のパソコンに対して、ディープシークAIへのアクセスを遮断するフィルタリングが開始された。これにより、同AIの業務使用は事実上不可能となった。また、三重県のデジタル推進局が調達した生成AIのみを業務に使用する方針が示されており、現在は「ChatGPT」が採用されている。
一見知事は記者会見で、ディープシークの利用制限によって県庁内の情報管理に関する問題は解消されたと述べた。この発言は、情報セキュリティを最優先に据える姿勢を示すものだ。生成AIによる情報漏えいリスクへの懸念は広がりを見せており、他の自治体や企業でも同様の対策が検討される可能性がある。
三重県の情報セキュリティ対策と今後の展望
今回の措置は、生成AIの急速な普及によって新たに生じた情報漏えいリスクを抑制する一環として位置付けられている。三重県はこの決定を通じて、外部技術への依存を適切に管理する姿勢を明確にしたといえる。特に、外部企業による生成AIが一部で問題視される中、県内情報の保護を重視した自主的な取り組みとして注目されている。
また、県が採用している「ChatGPT」は、デジタル推進局による審査を通過しており、セキュリティ上の懸念がないと判断されている。今後も県は、技術環境やリスク評価の変化に応じて生成AIの利用基準や運用方針を見直す予定だ。
他の自治体や企業においても、情報漏えいを防ぐために生成AIの導入基準や運用管理体制を強化する動きが進む可能性がある。政府主導によるガイドラインや規制が整備されれば、さらなる対策が広がることが予測される。三重県は今後も情報セキュリティ分野でリーダーシップを発揮し、他機関にとってのモデルケースとなることを目指している。
Plus Web3は「Web3領域に特化したキャリア支援サービス」

Plus Web3では、Web3で働きたい人材と、個人に合わせた優良企業をマッチングする求人サービスを行っています。
- Web3で働くことも考えている…
- Web3のインターン先はどこがいいか分からない…
- どんな知識やスキルがあれば良いのか分からない…
このような悩みを抱える人は、一度「無料キャリア相談」にお越しください。あなたにマッチした優良企業をご紹介いたします。









