ガートナー発表 生成AIを提供するベンダーのリスク管理策とは
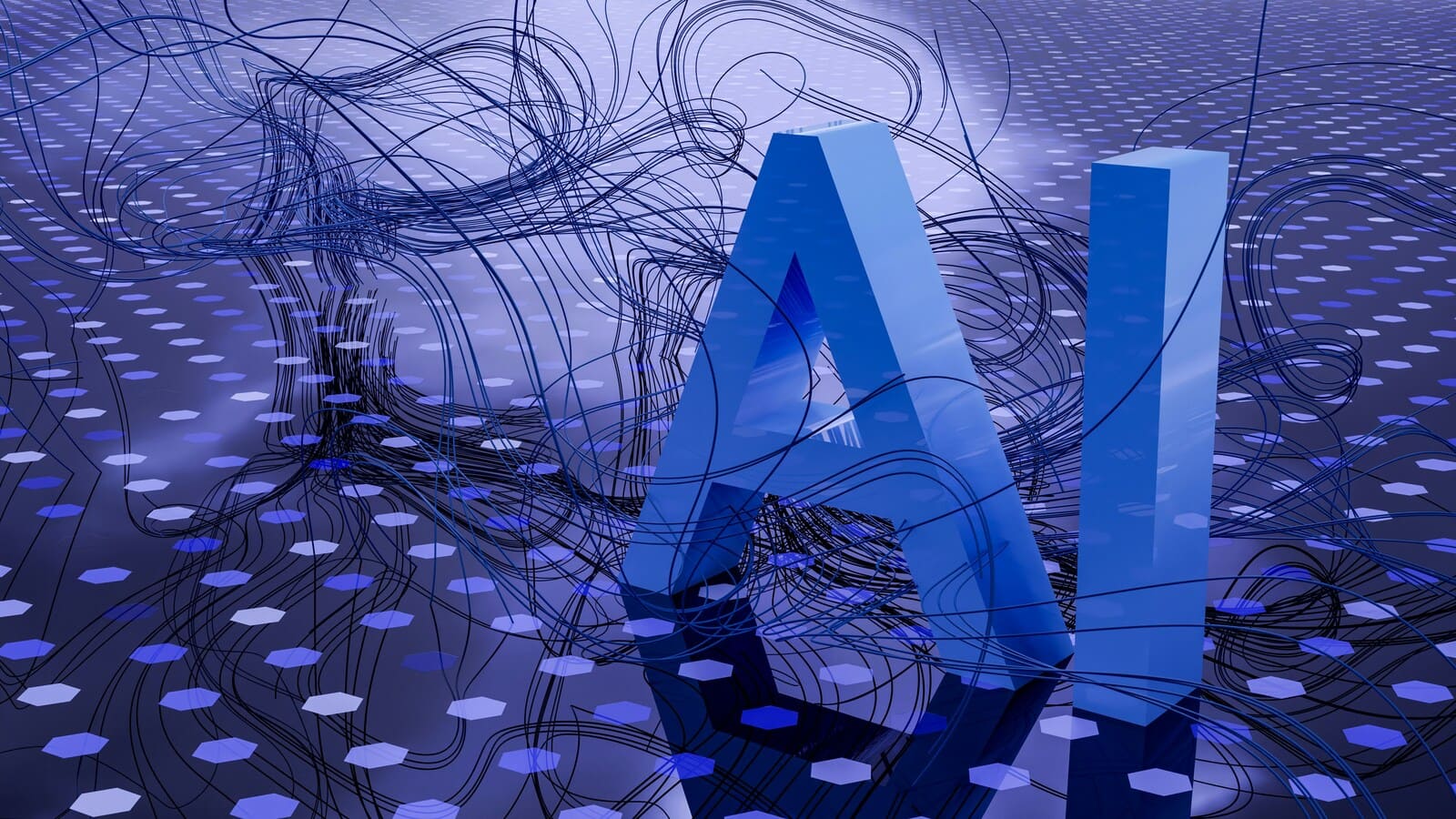
ガートナージャパンは2025年6月2日、「生成AIサービスを提供するベンダーへのリスク対策を進めるために取り組むべきアプローチ」を発表した。
生成AIは、国内では導入が進む一方でリスク管理が追いつかず、対応に大きなばらつきが生じているという。
生成AI導入が進む一方で、ベンダーリスク管理は整備遅れ
ガートナーが発表した調査によると、国内企業の63%がすでに何らかの生成AIサービスを利用しており、46%は複数のサービスを併用している実態が明らかになった。
一方、生成AIに特化したベンダー向けの管理ルールや基準を策定している企業は全体の約20%にとどまり、リスク対策の遅れが浮き彫りとなった。
この調査は、2024年3月にIT調達に関わる国内企業の担当者を対象に実施されたもので、生成AIサービスのベンダーに内在するセキュリティ、信頼性、契約リスクなどへの対応が十分に進んでいない実情が明らかとなった。
ガートナーのシニア ディレクター アナリストである土屋隆一氏は、「既に海外を中心に生成AIのリスクがビジネスに影響する形で顕在化した例も見られるが、生成AIのリスクは今後さらに多様化していく可能性がある」と指摘。選定から契約、運用、廃棄に至るベンダー管理の各段階で、リスクに応じた具体的な対応策が求められると警鐘を鳴らした。
ガートナーは今回、企業が限られたリソースの中でも現実的に取り組める施策として、①ユースケースのリスク評価とベンダーの成熟度の見極め、②生成AI利用環境に応じたルール・基準の適宜改定を提案した。
特にリスクの高いユースケースや、信頼性が不十分なベンダーに対して集中的に対策を講じる「メリハリある管理」が推奨されている。
また、リーダー層が関係部門と連携して柔軟に対応できる体制整備を呼びかけている。具体的には、①部門間のホットライン構築、②トリガーイベント(※)に応じたルール再評価の仕組み、③社内のAIオーナー部門の棚卸しと再教育の実施が挙げられる。
今後の展望 生成AI活用の明暗は「付き合い方」で決まる
生成AIはもはや試験的に導入する技術ではなく、意思決定支援や創造業務の中核を担いつつある。一方で、導入に伴うリスク管理や責任体制の整備が後手に回る企業も多い。
現場主導のPoC(概念実証)を繰り返すだけでは、企業全体の“生成AIリテラシー”は育たない。運用体制が不十分なまま普及すれば、情報漏洩や誤判断の温床にもなり得ると考えられる。
また、生成AI関連ではベンダーやスタートアップと連携するケースが多く、知財や責任の所在が曖昧になるリスクもあるだろう。問われるのは「すべてのリスクを排除する」姿勢ではなく、「リスクを前提に活用する」という視点だと言える。
どの企業も無限のリソースは持たない。だからこそ、限られた人員と時間で重点領域を見極める力が経営の分岐点になるのではないだろうか。生成AIを使いこなすには、技術理解に加え、“技術を組織でどう扱うか”という視座の転換が不可欠だろう。
※トリガーイベント:ベンダーのサービス仕様変更、セキュリティ事故、法規制の改定など、ルールや基準の見直しを必要とする契機となる出来事。












