住友商事と東北大学、産廃活用で半導体材料「SiC」を合成する技術開発へ
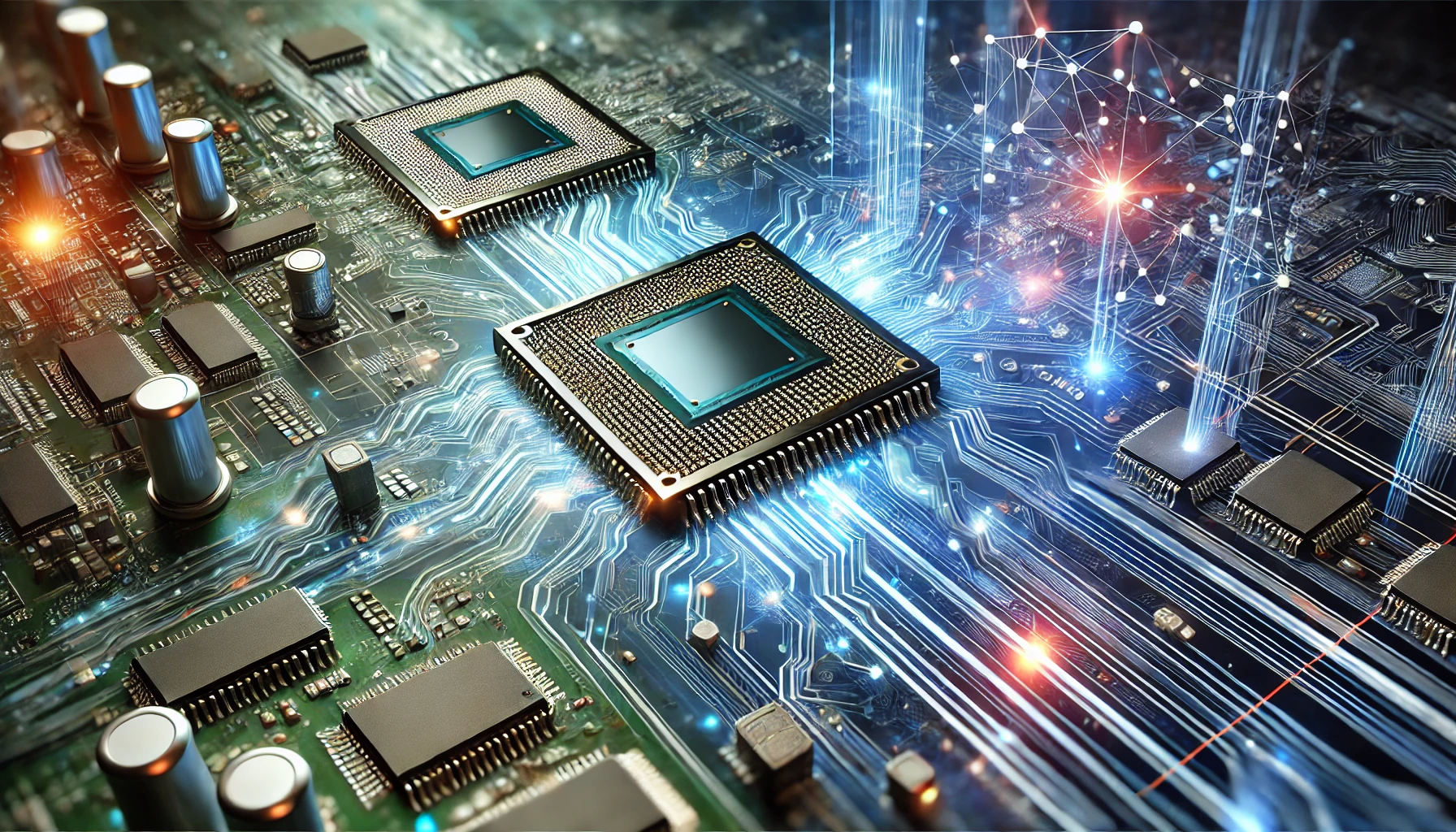
2025年5月14日、住友商事は東北大学と共同で、二酸化炭素(CO2)やシリコン系産業廃棄物を活用した炭化ケイ素(SiC ※)の合成技術開発の実証事業を開始すると発表した。半導体などの材料に使われるSiCの一部国産化に寄与するとみられ、2028年度からの実用化を目指す。
EV時代を見据えたSiC国産化、環境負荷低減と資源循環を両立
住友商事と東北大学は、2028年3月までの約3年間にわたり、SiCの新たな製造技術の実証事業に着手する。
この取り組みは、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の委託事業として進められ、2030年以降の半導体供給基盤強化に向けた重要な一手となる見通しだ。
開発の核となるのは、二酸化炭素と太陽光パネルや半導体製造で排出されるシリコン系廃棄物の再資源化である。
住友商事は、これらの廃棄物とCO2の安定調達に加え、市場性やサプライチェーンの構築を担う。
一方、東北大学は、SiCの合成反応における条件最適化と高純度化技術の確立を目指し、学術的な知見を活かした基盤整備を進める。
SiCは従来、輸入依存度が高く、その製造にも多くの電力を要することから、環境面でも課題を抱えていた。
本プロジェクトは、脱炭素時代に即した低環境負荷型の国産SiC製造の実現を試みるものであり、電気自動車(EV)などに不可欠な次世代パワー半導体の安定供給体制を築く上で大きな意味を持つ。
※SiC(炭化ケイ素):シリコン(Si)と炭素(C)の化合物で、耐熱性・高電圧特性・低損失性能に優れ、次世代パワー半導体の材料として注目されている。
競争激化するSiC市場、資源循環型技術で日本の優位性確保なるか
世界的にSiCの需要は急増しており、とりわけEVや再生可能エネルギー分野において高効率化が求められる中、SiCの採用は加速している。
米国や中国の企業も次々と大規模な生産計画を発表しており、日本国内においても対応が急務となっていた。
そうした背景の中、本プロジェクトは単なる技術開発にとどまらず、国内における資源循環型産業モデルの確立という側面も持つ。CO2や産業廃棄物を有効活用することで、環境への配慮と経済合理性を両立できる可能性がある。
仮にこのプロセスが実用化されれば、日本発の低炭素型SiC製造技術として、国際市場での差別化要因ともなり得る。
2028年度の実用化を目指す本事業は、最終的に国内での安定的な供給体制の構築を視野に入れている。
SiCの国産化が進めば、価格競争力だけでなく、地政学的リスクに対する耐性も高まり、半導体・EV関連産業にとって大きな支えとなるはずだ。
日本が持つ技術力と産業インフラを組み合わせた「循環型半導体材料戦略」が実を結ぶか、今後の進捗に注目が集まる。












