AI生成楽曲を見破る「Spotifake」登場 音楽業界の倫理と透明性を問う新ツール
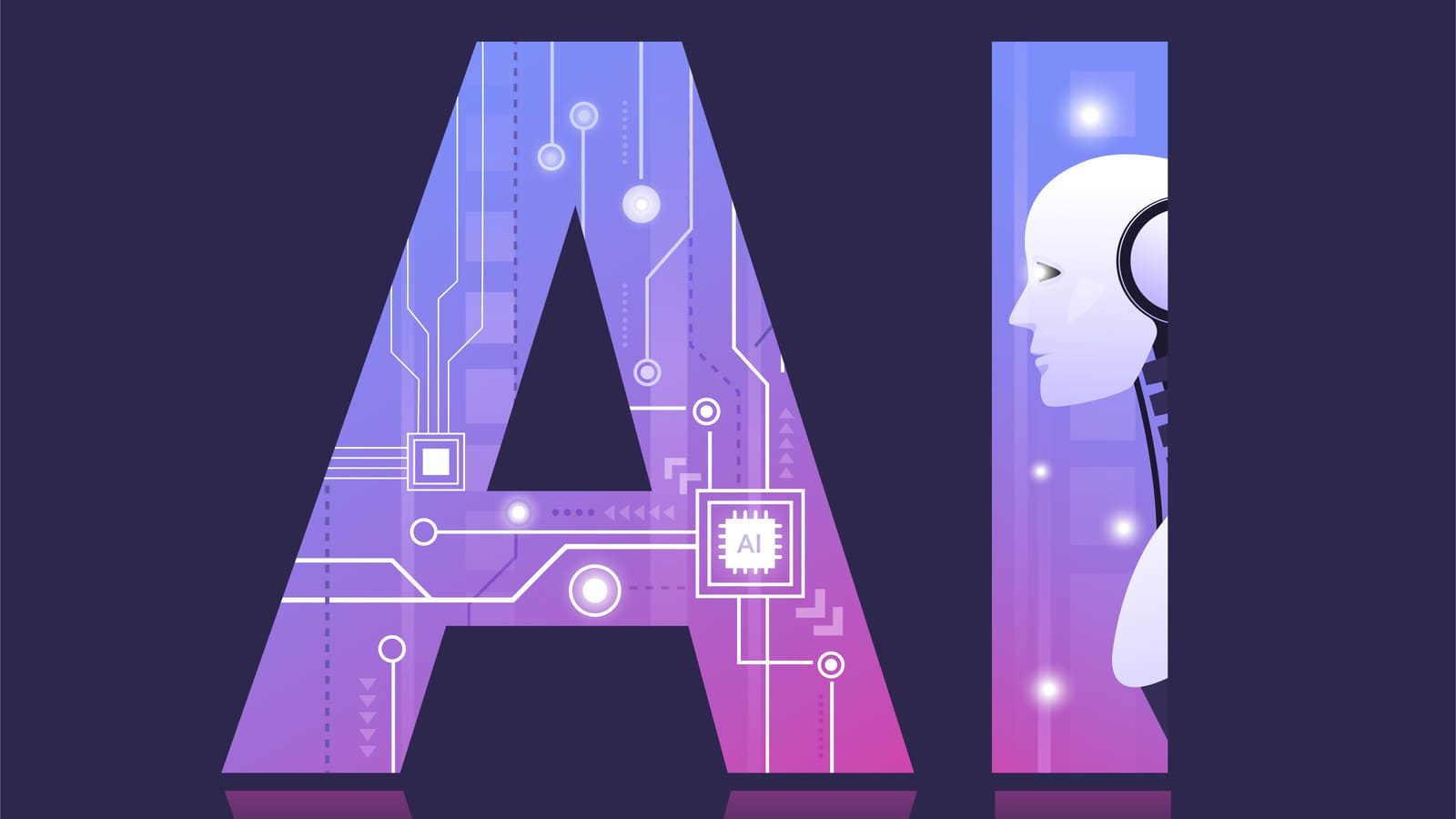
2025年4月23日、東京のAIクリエイティブラボQosmoが、音楽ストリーミングサービス「Spotify」上でAI生成楽曲を判定するツール「Spotifake」のβ版を公開した。
このツールは、AIによる大量の音楽生成がアーティストの収益や創作活動に与える影響への懸念から開発されたものである。
AI生成楽曲の氾濫と「Spotifake」の登場、アーティストの権利保護に向けた一歩
近年、音楽生成AIの進化により、AIが作成した楽曲の流通が急増している。
特にSpotifyでは、AI生成楽曲が既存アーティストの作品としてアップロードされ、収益を不正に得る手段として利用されるケースが報告されている。このような状況に対抗するため、Qosmoは「Spotifake」を開発した。
Spotifakeは、Spotify上の楽曲URLを入力することで、その楽曲がAI生成である可能性を数値で表示するツールである。
この判定には、カリフォルニア大学サンタバーバラ校の研究者が開発した「SONICS」というデータセットが活用されている。
SONICSは約9万7000曲を収録し、その半数以上がAIによって生成されたもので、AI楽曲の検出に特化した構成となっている。
Qosmoは、AIを用いた音楽生成には有意義な使い道があると認識しつつも、アーティストにとって不公平な形でのAIの利用には反対している。
特に、AIによって大量生産された音楽が出所を明らかにせずに流通することは、真摯に音楽と向き合うアーティストにとって不公平であると指摘している。
AI音楽の未来と今後の展望
AI生成楽曲の増加に伴い、音楽業界ではその検出と管理が急務となっている。
今後、SpotifakeのようなAI検出ツールは、他のストリーミングプラットフォームや音楽配信サービスにも広がる可能性がある。
たとえば、DeezerはAI生成楽曲の検出ツールを導入し、AI生成コンテンツの透明性を高める取り組みを進めている。
また、AI生成楽曲の検出精度向上には、より多様なデータセットの活用や、機械学習アルゴリズムの進化が求められる。
さらに、多くのストリーミング配信プラットフォームでは、AI生成楽曲の明確な表示や、適切な収益分配の仕組みの導入が検討されている。これにより、アーティストとAIの共存が可能となり、音楽業界全体の健全な発展が期待される。
総じて、AI生成楽曲の検出と管理は、音楽業界における重要な課題であり、Spotifakeのようなツールの進化と普及が、その解決に向けた鍵となるだろう。












