ソフトバンクG、カーネギーメロン大に22億円超を寄付 日米AI研究の国際連携を支援
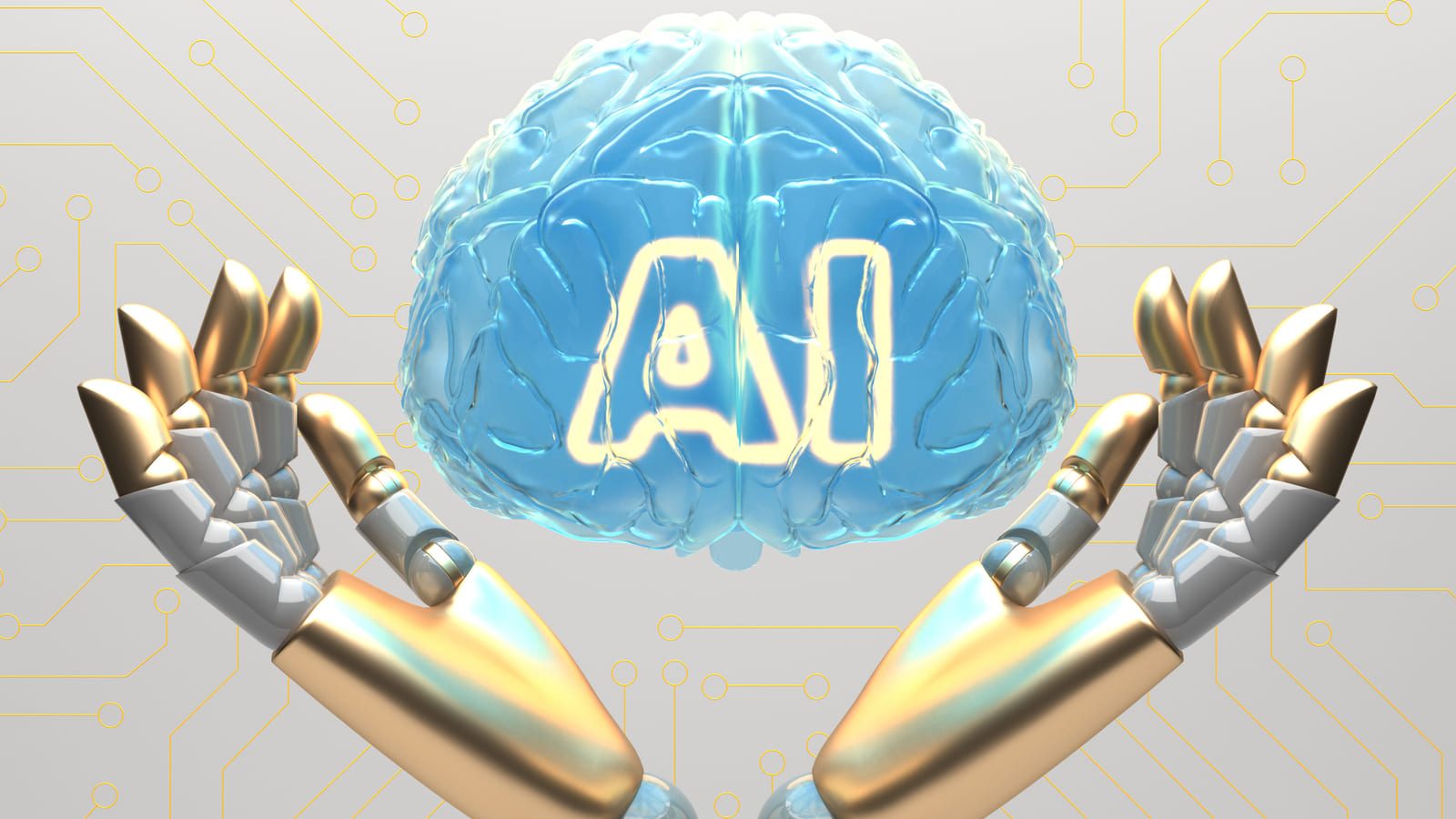
2025年5月15日、ソフトバンクグループおよびその傘下である英Armは、米カーネギーメロン大学に対して1550万ドル(約22億4750万円)を寄付すると発表した。日本と米国が連携するAI研究体制の強化を目的とした動きである。
日米連携によるAI研究強化へ、ソフトバンクの戦略的投資がもたらす波及効果
対象となるのは、カーネギーメロン大学と慶應義塾大学による共同研究プロジェクトであり、両大学間での学術的連携を後押しする。寄付金は、研究インフラの強化や人材育成にも活用される見通しだ。
この背景には、2024年4月に立ち上がった日米間のAI研究パートナーシップがある。
カーネギーメロン大学と慶應義塾大学に加え、筑波大学と米ワシントン大学もこの枠組みに参加しており、グローバルな知の協働が始まっている。産官学の協力による研究加速が期待される。
ソフトバンクの支援内容には、Armの「Academic Accessモデル」も含まれる。このプログラムを通じて、研究者たちは先端的なハードウェアやソフトウェア環境に自由にアクセスできるようになる。また、「ソフトバンクグループ–Armフェローシップ」として、博士課程学生向けの奨学金制度も創設される予定だ。
支援対象となる研究は、マルチモーダル・多言語学習やロボティクス、自律型AI、ライフサイエンス領域のAI活用など多岐にわたる。中でも家庭内タスクをこなすロボットの開発など、実用化を見据えた研究が着実に進められている。
ソフトバンクのグローバルAI戦略と、研究者・市場への影響
この寄付は単なる学術支援にとどまらず、ソフトバンクのAI領域における戦略的布石とも読み取れる。AI技術をめぐる国際競争が激化する中、世界屈指の研究機関との関係強化は、長期的な技術獲得と人材リクルートの優位性につながる可能性が高い。
研究対象の一つであるエンボディードAI(※1)は、ロボットが人間の生活空間に自然に溶け込むために欠かせない技術だ。また、マルチモーダルAIは画像・音声・テキストなど異なる情報を統合して理解するため、次世代の生成AIや翻訳技術などへの応用も視野に入る。
日米の大学連携は、AIの基礎研究だけでなく、ライフサイエンスや医療、都市インフラ分野に至るまで、幅広い社会課題の解決につながると考えられる。これらの技術が社会実装されれば、新たな産業の創出にも寄与するはずだ。
他の企業も大学との連携を強める動きを見せており、今後さらに研究開発競争が加速するだろう。
※エンボディードAI:身体性(embodiment)を備えた人工知能のこと。センサーやアクチュエーターを通じて物理環境と相互作用し、環境に適応して学習・行動する技術を指す。












