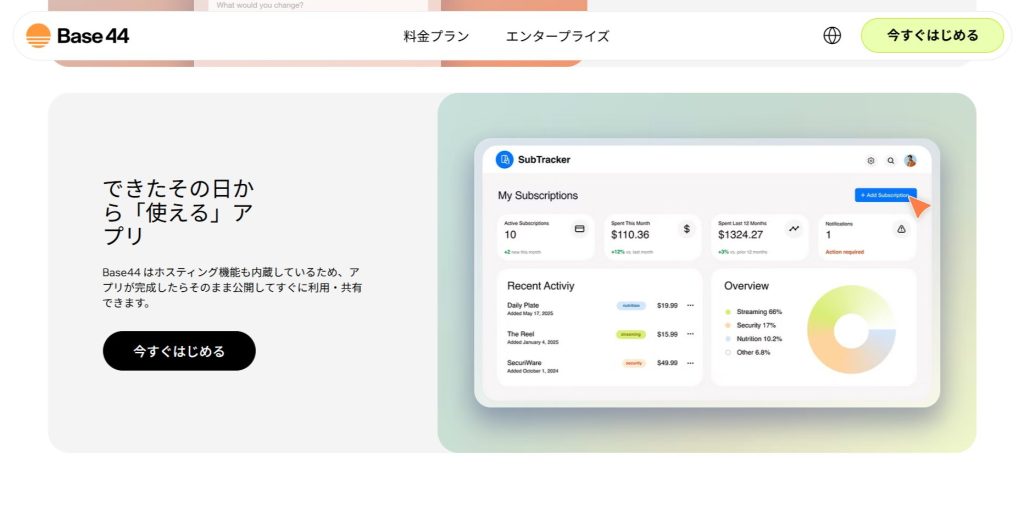“味覚”を数値化する時代へ 新潟市がAI活用で食品開発に挑む産学官プロジェクト始動

2025年5月29日、新潟市中央区で「にいがた2kmおいしさDX産学官共創プロジェクト」の説明会が開催された。
味や香りといった“おいしさ”をデジタルで表現し、AI活用による新商品やレシピの開発につなげる新たな取り組みが本格的に動き出した。
味や香りの“見える化”により、商品開発を加速
本プロジェクトには新潟市、新潟大学、地元IT企業が連携。従来は職人の経験や勘に依存していた「おいしさ」の要素を科学的に分析・記録する仕組みを構築している。
具体的には、香り成分や味覚の強度、食感などをセンシング機器で定量化し、統計的に解析することで、消費者に支持される食品の特徴を明らかにすることを目指す。
説明会では、データの蓄積によりAIが「売れるレシピ」を自動生成する未来像も提示された。
新潟市都市政策部の宮崎博人政策監は、「新潟の方々は新潟の食を、自信を持って自慢してはいるが、なかなか何がおいしいかというのを口でしゃべるというのが苦手。そこを我々の取り組みでは、デジタルで表現するというのが一つの特徴」と語った。
食品業者からも「大学と一緒にデータをデジタル化して、もっと色んなところで新潟の農産物を使ってもらいたい」との期待が寄せられている。
多数の事業者が参画することで地域全体でのデータ収集が進み、商品開発の可能性が広がると見られている。
AIが導く“おいしさ革命” 食品業界に新たな競争軸
この取り組みが軌道に乗れば、新潟発の“おいしさの標準化”が食品業界に新たな競争軸をもたらす可能性がある。
AIによるレシピ開発や味覚予測は、短期間でヒット商品を生み出す手段になり得るため、開発リードタイムの短縮や試作コストの削減といったメリットが期待できる。
また、データに基づいた味の設計は、ターゲット消費者の嗜好に合わせた製品企画を可能にすると考えられるため、地域外市場への展開も視野に入るだろう。
一方で、課題も存在する。
味覚や香りの評価には依然として個人差が大きく、どのデータを“おいしさ”と定義するかの基準設定には慎重さが求められると思われる。また、AIが提案するレシピが、実際の製造工程やコストに適合するかといった実務上の調整も不可欠であろう。
それでも、「感覚」に頼ってきた業界にとって、デジタル化による客観的な判断軸の導入は革新的な変化といえる。プロジェクトの成果次第では、新潟発の技術が他業種への展開へと波及する可能性も考えられるため、今後の動向にも引き続き注目したい。