AIが雇用を奪うとの主張に懐疑 米ミネアポリス連銀総裁が見解示す
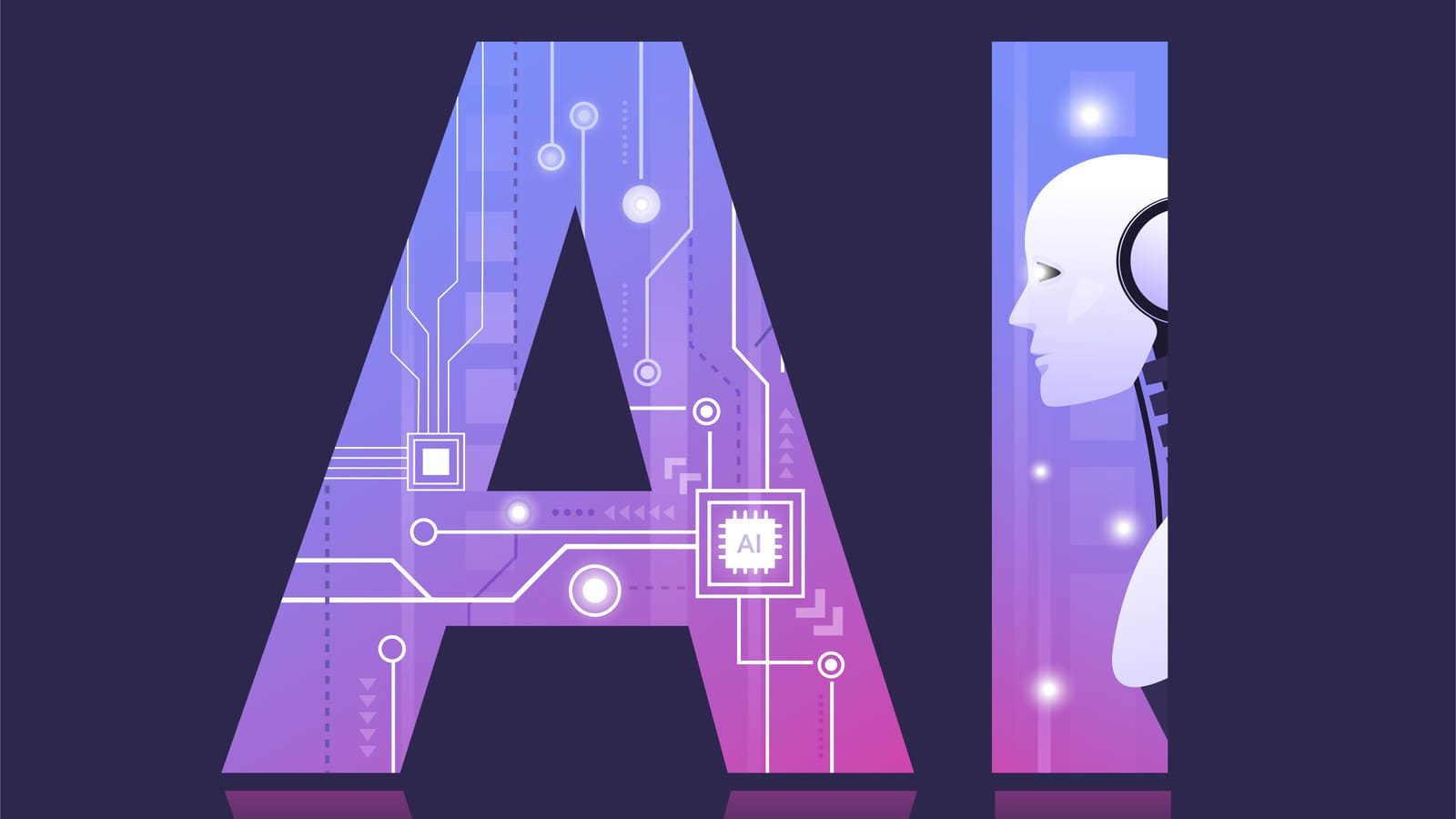
2025年10月7日、米ミネアポリス地区連邦準備銀行のニール・カシュカリ総裁は、AI(人工知能)が労働者を急速に置き換えるとの主張に懐疑的な見方を示した。経済への影響を判断するのは時期尚早だとし、AI導入を過度に恐れる風潮に警鐘を鳴らした。
「AIによる雇用崩壊は誇張」 過去の技術革新と同様に浸透は緩やか
カシュカリ総裁は、ミネアポリス・スター・トリビューン紙主催のノース・スター・サミット2025で、「多くの労働者がAIに置き換えられるという状況には懐疑的だ。そうした証拠もまだ見つかっていない」と述べた。過去の技術革新を例に挙げ、AIが経済や社会に根付くまでには相応の時間を要するとの見方を示した。
同氏は、AIツールが仕事の性質を変える可能性を認めつつも、労働者は経済において重要な役割を果たしていると強調。
同イベントには米オープンAIのチーフエコノミスト、ロニー・チャタジー氏も参加した。
同氏はまた、たとえFRBが政策金利を引き下げても、AIデータセンターへの巨額投資が金利を押し上げる傾向があると指摘。「住宅やアパートの建設に充てられるはずだった資金が、より高い投資収益を生み出すデータセンターの建設に転用されているため、住宅ローン金利の低下にはつながらない可能性がある」と述べた。
さらに、「もしFRBが経済的に正当化される範囲を超えて金利を大幅に引き下げれば、経済は事実上過熱しているため、おそらく失業率は非常に低くなりインフレ率は非常に高くなるだろう」と語った。
その上で、9月のFOMC(米連邦公開市場委員会)で0.25%の利下げを支持し、今後も同規模の利下げを通じて雇用市場の軟化を防ぐべきだとの立場を示した。
AI経済がもたらす構造転換 生産性向上と格差拡大の岐路に
カシュカリ総裁の発言は、AIが短期的に雇用を奪うという「技術失業」論への慎重な姿勢を示したものだ。一方で、AI導入が進むことで職務内容の再定義や再教育が急務となる点も否めない。企業が効率を優先して人員を削減する動きが広がれば、一定の雇用不安は避けられないとみられる。
しかし、AIがもたらす最大のメリットは、生産性と付加価値の向上にある。ルーチン業務をAIが担うことで、労働者はより高度な判断や創造的業務に集中できる。特に、サービス産業やホワイトカラー職では、AIを補助的に活用する「共存型モデル」が主流になると予測される。
一方で、AI関連投資の偏在が格差拡大を助長する懸念もある。
大規模なデータセンターやAI基盤を整備できるのは一部の資本力を持つ企業に限られるため、資本集約型経済へのシフトが進む可能性がある。
こうした構造変化の中で、政府や中央銀行は「AI時代の労働再分配」という新たな政策課題に直面していると考えられる。
今後、AIが経済の成長エンジンとして定着するか、それとも社会的分断を深める要因となるかは、教育・金融・雇用政策の舵取りにかかっているといえる。












