NASAとIBM、太陽AI「スーリヤ」発表 2時間前のフレア予測を実現
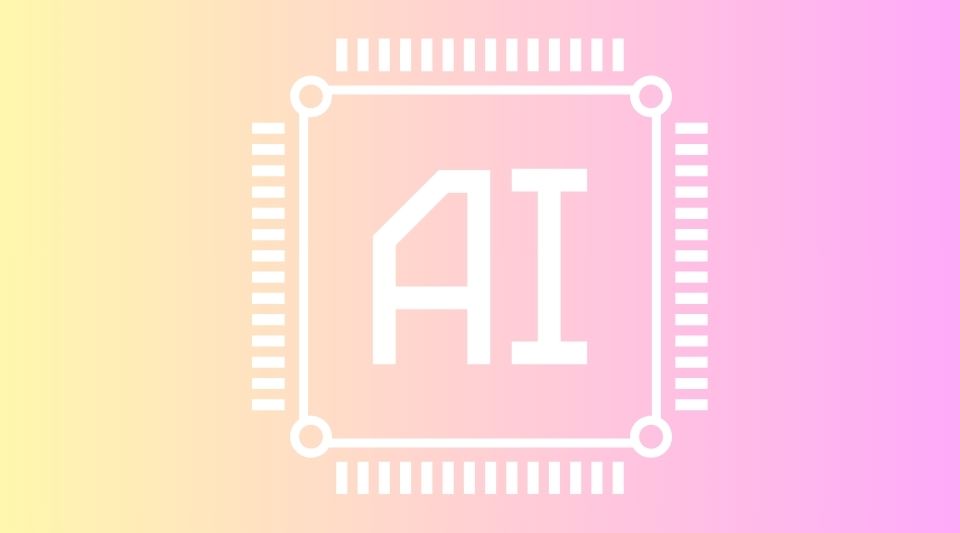
2025年8月20日、米IBMと米航空宇宙局(NASA)は、太陽フレア発生地点を最大2時間前に予測可能な人工知能(AI)モデル「Surya(スーリヤ)」を発表した。宇宙天気の予報精度向上により、衛星・電力・通信インフラへの影響対策が一歩進む見通しだ。
IBMとNASA、太陽フレア予測精度を大幅改善
スーリヤは、NASAの太陽観測衛星「Solar Dynamics Observatory(SDO)」が9年間にわたり取得した高解像度画像を学習したAIモデルで、サンスクリット語で「太陽」を意味する名称が付けられている。
このモデルでは、太陽フレアや太陽風(※)の速度、爆発を引き起こす活動領域を精密に分析し、発生を従来よりも高い確度で予測することが可能となった。
初期試験では、太陽フレアの強度予測において従来手法を最大16%上回る精度を示したほか、フレア発生の場所を史上初めて2時間前に特定できた。
これにより、衛星軌道調整や送電網保護など、実運用レベルでの事前対応が現実味を帯びてきた。
スーリヤは標準AIの10倍規模の画像を処理可能な設計で、世界最大級のAIモデル共有プラットフォーム「Hugging Face」上で公開されている。
背景として、2024年5月に発生した大規模な太陽フレアに伴う「コロナ質量放出(CME)」では、北緯40度付近までオーロラが観測され、G4~G5級の激しい磁気嵐を引き起こした。
この経験が、各国で宇宙天気予測精度の向上を求める声を高めたと言える。
※太陽風:太陽から放出される荷電粒子の流れで、地球の磁気圏や電離層に影響を及ぼす現象。
宇宙天気予測の商用化進む 経済効果と過剰対応リスクも
スーリヤの活用により、太陽活動による影響を受けやすい航空機運航、GPS、海底ケーブルなどのインフラ事業者は、従来よりも長い猶予時間を確保できるようになるだろう。
これにより、衛星の姿勢制御や電力供給計画の最適化など、経済的損失の抑制が期待される。
一方で、過剰な予測対応によるコスト増や誤検知リスクも無視できない。誤報に基づいた運用停止は、航空便の欠航や物流遅延といった二次的損害を生む可能性がある。
このようなデメリットはありつつも、安全が第一に優先される現代においては、リスクマネージメントが容易になるという点でメリットと言えるかもしれない。
また、富士通やGoogleなど、他社による宇宙天気予報の高精度化も進行中であり、予測精度とコスト効率をめぐる競争は今後一層激化すると見られる。
将来的には、宇宙天気予報が地震や台風と同等の社会インフラとして扱われる可能性もあるが、その信頼性確保が課題となるだろう。












