宇宙最大級のクエーサー密集領域を発見 偶然生じる確率は“1不可思議(10の64乗)分の1”未満
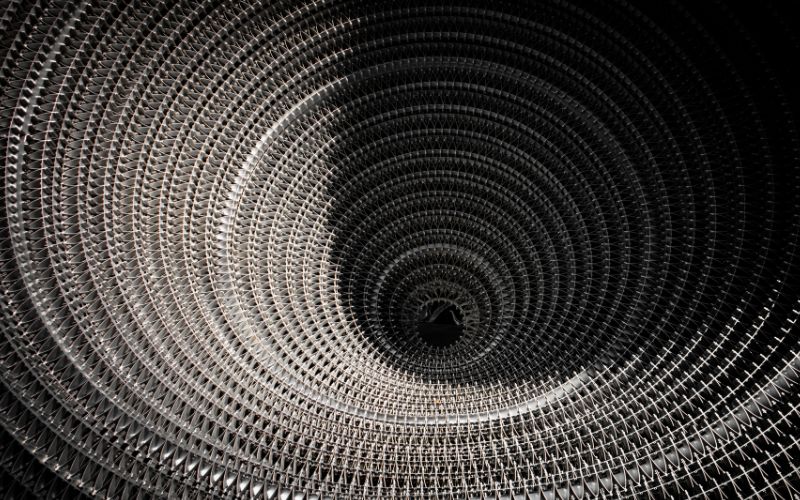
2025年6月3日、国立天文台と東京大学などの国際研究チームが、超巨大ブラックホールの密集領域を発見したと発表した。11個のクエーサーが集まったこの構造は、偶然ではほぼ起こり得ない天文学的な配置である。
超巨大ブラックホール11個が直径4000万光年内に集中
国立天文台と東京大学を中心とする国際共同研究チームは、スローン・デジタル・スカイ・サーベイ(SDSS)の観測データを解析し、すばる望遠鏡による追観測を行った結果、くじら座の方向にある約108億年前の宇宙空間に、11個のクエーサーが密集する領域を発見した。
発見された領域の直径は約4000万光年。
このスケールにおいて、11個もの超巨大ブラックホールが互いに近接して存在するのは極めて異例である。これらのブラックホールはいずれも活発に周囲の物質を取り込み、強い光を放つ「クエーサー(※)」として観測されている。
国立天文台ハワイ観測所のリャン・ヨンミン博士は「もし偶然であるとすれば、その確率は10の64乗分の1未満という驚異的な数字」と話し、この発見の特異性を強調している。
研究チームの解析によれば、これは天文学においてもほとんど起こり得ないレベルの確率であり、「1不可思議分の1(※)」という極端な例えで語られるほどである。
※クエーサー:超巨大ブラックホールが活発に物質を吸収し、強いエネルギーを放射している状態。非常に明るく遠方でも観測可能。
※1不可思議(10の64乗((10^64)):(10^8)=1億。(10^8)^8=10^64なので、1億を8回かけた数字。比較対象として、宝くじ(ロト6)の1等の当選確率は、約1/(6×10^6)=1/600万と言われている。
「宇宙のヒマラヤ」が示すブラックホール進化の新たな鍵
通常、クエーサーは銀河が密集する領域で活発化するとされている。
銀河同士が引き合い、衝突や合体を繰り返すことで中心にガスが集中し、ブラックホールの成長が促進されるからである。
しかし、今回の密集領域はこの通説を覆す可能性をはらんでいる。
観測によると、11個のクエーサーが位置していたのは、2つの銀河集団の“中間”にあたる空間だった。これは、クエーサーの成長環境が「単純な銀河の密度」だけでは説明できないことを示唆している。
研究チームはさらに、銀河間に広がるガスの三次元分布を解析。
その結果、クエーサーは中性ガスと電離ガスの境界、いわば「宇宙の遷移帯」に分布していることが判明した。
これは、クエーサーの強い放射が周囲のガス環境に影響を与えている可能性と、将来的に形成される巨大銀河団の“種”を示している可能性を同時に示すものといえる。
リャン博士は「これは、クエーサーが放つ強い光が周囲のガスの状態を変えていると同時に、作られつつある巨大構造、例えば銀河団の種をトレースしている可能性を示している」と述べており、研究チームは今回の構造を「宇宙のヒマラヤ」と名付けた。
今後、すばる望遠鏡の新たな装置である超広視野多天体分光器(PFS)を用いた観測により、この構造の成因やブラックホールの成長史がさらに明らかになる可能性もあるだろう。
ブラックホール研究の次なる突破口となるか、続報に注目したい。












