日本電子計算、AIエージェント基盤「つなぎAI」を拡張 業務自動化を加速
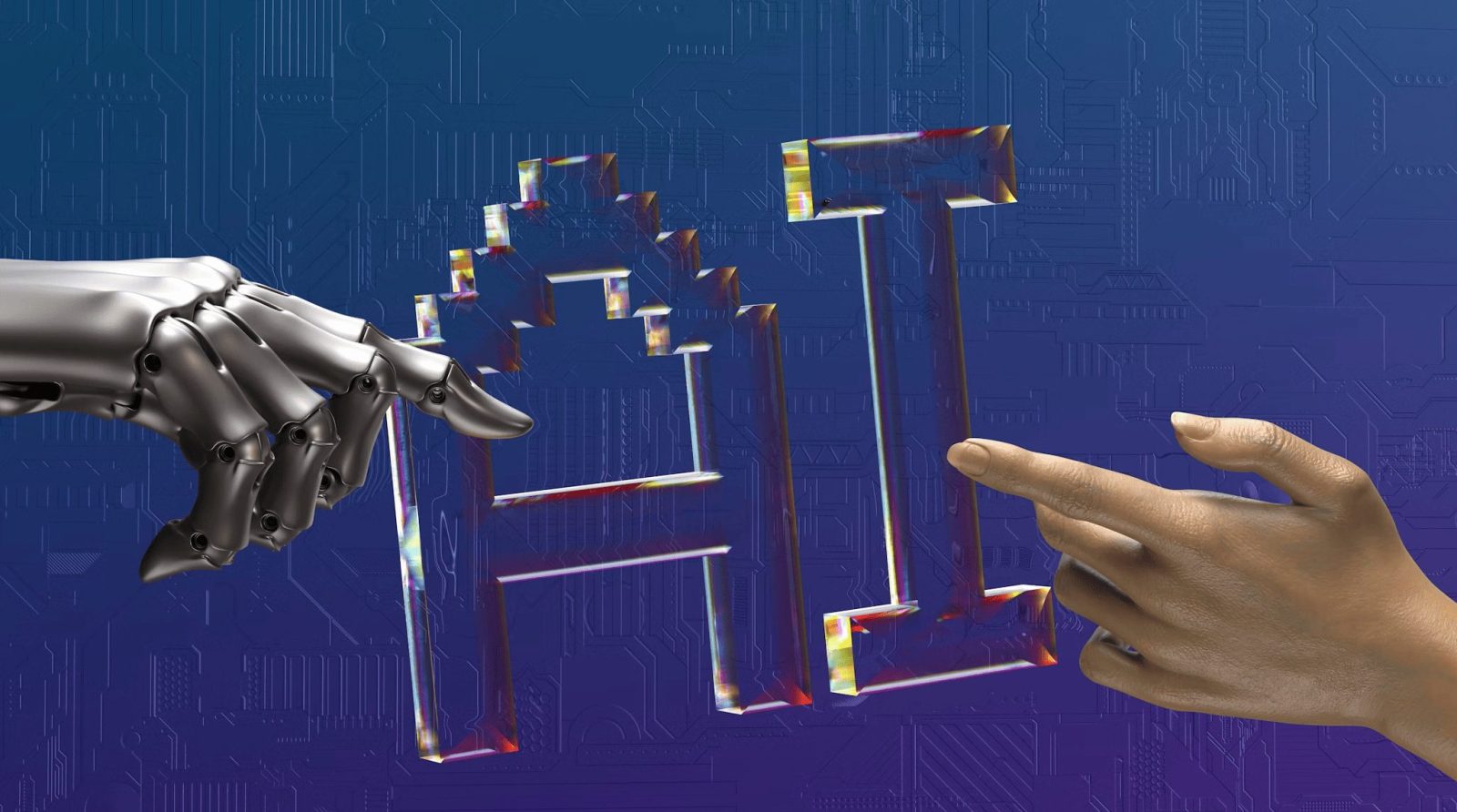
2025年10月14日、NTTデータグループの日本電子計算株式会社は、株式会社NTTデータと共同で提供するAIエージェント基盤サービス「つなぎAI(つなぎあい)」の機能強化を発表した。
プラグイン機能や外部システムとの連携を新たに可能にし、10月末から順次提供を開始する。
「つなぎAI」がVer1系対応 プラグイン・MCP連携で拡張性強化
「つなぎAI」は、LangGeniusが開発したLLM(※1)アプリ開発基盤「Dify(ディフィ)」をベースに、日本電子計算とNTTデータが日本企業向けに独自機能を追加したSaaS型AIエージェント基盤である。
ユーザーが自ら業務フローを設計でき、各プロセスの根拠や実行内容を確認できる「プロセスエージェント」として、透明性と業務効率化を両立する構成を採用している。
新たな機能拡張によって、「Dify」のVer1系への対応が可能となった。
これを通じて、プラグイン導入やMCP(※2)クライアント機能を利用した外部システムとの連携が実現する。
この対応により、従来は困難だった複雑な業務プロセスの自動化や、複数のAIエージェント間での連携が容易になるとしている。
さらに、小規模導入を検討する企業向けに、10ユーザー・年間96万円から利用できる「ベーシックプラン」を新設。
セキュリティ機能を維持しながら構成を簡素化し、10月末にβ版を、12月に正式版を提供する予定だ。
あわせて、12月までの契約企業を対象に、3カ月24万円から試用できる「ベーシック有料PoC」キャンペーンを実施する。11月末までの申し込みで初月無料となる特典も用意された。
日本電子計算は今後、「つなぎAI」とRPAツール「WinActor(ウィンアクター)」との連携を予定している。
これにより、RPAシナリオの自動生成やエラー対応をAIが支援できる体制が整う見込みだ。
※1 LLM(大規模言語モデル):膨大なテキストデータを学習し、人間の言語を理解・生成するAIモデル。ChatGPTなどが代表例。
※2 MCP(Model Context Protocol):異なるAIモデルやアプリを連携させ、統一的に動作させるための通信規格。
業務自動化の深化とガバナンス強化が次の焦点に
「つなぎAI」の拡張は、AIエージェントによる業務自動化の幅を大きく広げる契機となるだろう。
プラグインやMCP連携により、複数システムを横断して情報を統合できるようになった点は、企業の生産性と柔軟性を高めるうえで大きなメリットといえる。
一方で、外部システムとの連携範囲が広がるにつれ、セキュリティ対策やガバナンス設計の難易度は一層高まるとみられる。
AIが意思決定に関与する領域では、誤作動や責任の所在を明確にしなければならないだろう。
また、現場担当者のスキル差がAI運用の品質に影響を及ぼす懸念も残る。
今後は、AIを業務の中核に組み込む「エージェント統合時代」への移行が進むと予想できる。
その際、企業が重視すべきは、精度だけでなく“説明できるAI”への転換だと考えられる。
つなぎAIが透明性と信頼性を兼ね備えた基盤として確立できるかが、市場での真価を決める鍵となりそうだ。
関連記事:
AWS、エージェント型AI搭載ワークスペース「Amazon Quick Suite」を一般提供開始 ビジネスデータ活用を自動化へ













