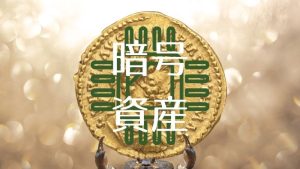暗号資産のインサイダー取引規制、金融庁が方針固める 2026年に金商法改正案提出へ
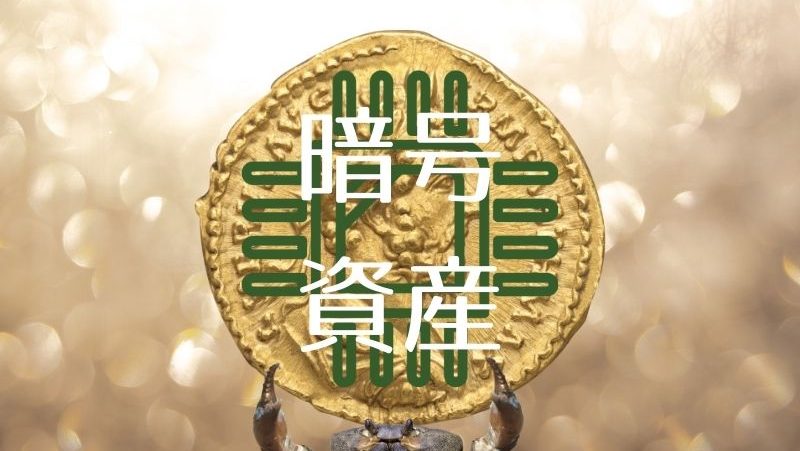
2025年10月15日、日経新聞は、金融庁が暗号資産(仮想通貨)をインサイダー取引の規制対象とする方針を固め、2026年の金融商品取引法(略称:金商法)改正案提出を目指すと報じた。
暗号資産を「内部情報禁止」対象にする方針
金融庁は、暗号資産を金商法の適用対象に移行させる方針を明確にしたと報じられている。
これまで暗号資産は資金決済法上で「決済手段」と位置づけられており、金商法に基づくインサイダー取引(※)規制の対象には含まれていなかった。
日経新聞報道によれば、金融庁は年末までに作業部会で詳細を詰め、2026年の通常国会で金商法改正案を提出する計画だという。
この改正案には、未公表の重要情報に基づく暗号資産の売買禁止が明記される見込みである。
背景には、暗号資産市場の拡大や投資資産としての取引増加があるとみられる。
国内の暗号資産稼働口座数は近年増加傾向にあり、交換業者や日本暗号資産等取引業協会(JVCEA)に関する情報管理の重要性が指摘されている。
また、金融庁は今年7月に、暗号資産に関連する制度のあり方等に関するディスカッション・ペーパーを公表しており、その中で情報開示強化やインサイダー取引への対応なども含まれていた。
※インサイダー取引:企業などの内部関係者が、公表前の重要事実を用いて株式などを売買し不正利益を得る行為。
制度化で問われる「保護」と「革新」の両立
今回の動きは、暗号資産に対する規制を投資市場の枠組みにも取り込む試みと位置づけられる。
暗号資産を金商法の枠内に取り込めば、インサイダー取引の抑止や市場の信頼回復につながると予想できる。特に、価格形成の透明性が高まり、国内外の機関投資家が参入しやすくなることはメリットだろう。
日本市場が国際的な基準に近づくことで、取引の健全化と資本流入の促進が進む可能性が高い。
一方で、暗号資産特有の非中央集権構造は規制設計を複雑化させるかもしれない。
発行主体が曖昧なトークンでは、どの情報を「未公表」とみなすかの判断が難しく、過剰な規制が技術革新を阻害するおそれもある。
特に中小プロジェクトやスタートアップにとっては、監督体制の整備や法的手続きに伴うコストが負担となりうる。
今後は、投資家保護と市場の活力をいかに調和させるかが重要なテーマとなりそうだ。
金融庁が民間団体やブロックチェーン事業者との連携を深め、実効性と柔軟性を兼ね備えた制度設計をどこまで進められるかが試される局面に入るとみられる。
こうした取り組みが着実に進展すれば、暗号資産はこれまでの「制度の外」にとどまらず、「金融の中枢」に位置づけられる存在へと変化していく可能性もあるだろう。
関連記事:
金融庁、暗号資産規制を「金商法」へ一本化提案 重複回避で制度明確化狙う