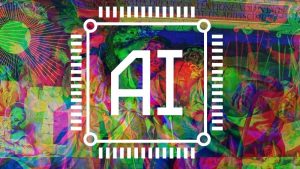コロプラ式「AI活用の社内浸透モデル」公開 社員9割超が利用、業務量半減も
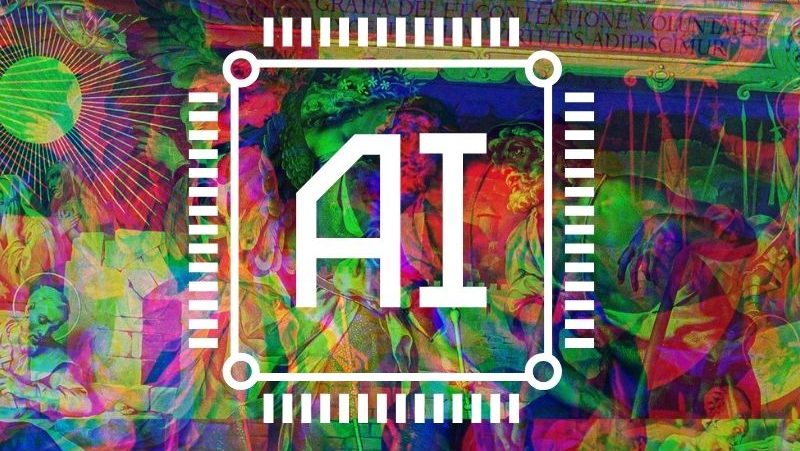
2025年10月6日、ゲーム開発大手のコロプラが、自社のAI活用に関する社内浸透モデルを公開した。
社員の9割以上がAIを業務に活用し、3人に1人が業務量50%以上の削減を実感しているという。
導入だけで終わらせない AI浸透の5段階モデルと心理支援策
コロプラは「AI導入で止まらない」組織づくりを目指し、段階的な社内AI浸透策を展開している。
2022年から本格導入を進め、現在では社員の92%が何らかの形でAIを利用。
そのうち半数以上が「ほぼ毎日」使用している。
特に注目されるのが、AI活用を可視化した「5段階の成熟度モデル」と、社員の心理的反応を整理した「心理的浸透度モデル」だ。
前者では、AI活用を「認識」「探索」「運用」「体系化」「変革」の5段階で定義。
企業がどの段階にあるかを把握し、戦略的に次のフェーズへ進む指針を示す。
一方、心理的モデルでは、社員がAIに対してどの段階の受容・抵抗を示しているかを評価し、自然な浸透を促した。
また、役職者による率先利用が浸透の起点となった点も特徴的である。
コロプラでは、マネージャー層の活用率はほぼ100%に達している。
Slackでの事例共有やAI勉強会、経営層のメッセージ発信などを通じて「トップダウン」「ボトムアップ」「ミドルアップダウン」といった多方向からのアプローチ戦略を採用した結果、心理的な抵抗感を和らげ、誰もが安心してAIを使える環境を醸成したという。
その結果、社員の約4分の1が「革新期(※)」に達し、AIを積極的に業務に組み込む段階に移行している。
※革新期:心理的浸透度モデルの最終段階。社員がAIを自発的に活用し、既存の業務改善にとどまらず、新たな仕組みや価値を創出する段階を指す。
AIが生み出す業務効率と創造性の両立 今後の展望は
今後、コロプラのAI活用は「共創の深化」へと発展していくとみられる。
これまで業務支援やコンテンツ生成にとどまっていたAIの役割が、社員と共に新たな発想を生み出す“共創パートナー”として定着していく段階に入るだろう。
各プロジェクトで培われた知見が社内全体に還元されることで、AIと人の発想が有機的に結びつく「創造の循環」が形成される可能性が高い。
また、AIが生み出すデータやアイデアを人間が再編集する仕組みが整えば、ゲーム制作における世界観設計や物語構築のプロセスそのものが変化する可能性もある。
AIが“ひらめきの起点”となり、開発者がそれを拡張・再構築する流れが一般化すれば、創作のスピードと質の両立が期待できる。
一方で、AIリテラシーや情報セキュリティの格差をどう埋めるかは、今後も重要なテーマとなりそうだ。
AIの判断過程を人が理解し、共に成長していく「透明性のあるAI文化」が形成されるかどうかが、次の焦点になるだろう。
コロプラの事例は、AIを“使う”段階から“共に学ぶ”段階へと進化する企業像を示唆しており、今後の国内企業におけるAI導入モデルの方向性を占う試金石となる可能性がある。
コロプラ お知らせ:https://colopl.co.jp/news/info/2025100601.php
関連記事:
【MITレポート】95%のAIプロジェクトが失敗?成功するポイントとは