GMO・NTT東西など、IOWN APN活用で分散型AI基盤を実証 福岡-東京間でGPU遠隔接続
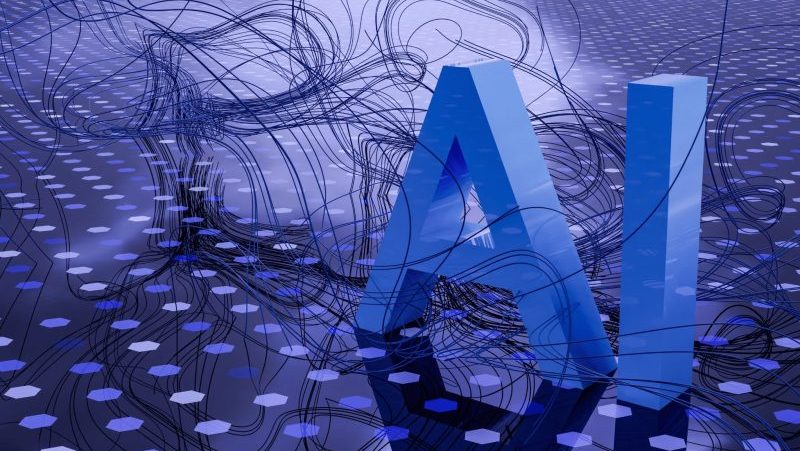
2025年10月2日、GMOインターネットとNTT東日本、NTT西日本、QTnetの4社は、次世代通信技術「IOWN APN(All-Photonics Network)」を活用した分散型AIインフラの技術実証を開始した。
福岡と東京間でGPUとストレージを遠隔接続し、低遅延環境下でのAI処理性能を検証する。
GMO GPUクラウドとIOWN APNを組み合わせた県間接続を実現
GMOインターネット、NTT東日本・西日本、QTnetの4社は、IOWN APNの超低遅延通信技術を活用し、遠隔地間でAI演算基盤を接続する技術実証を共同で進めている。
GMOの「GMO GPUクラウド」を用い、福岡のGPUと東京の大容量ストレージをIOWN APNで県間接続をするのは初めての試みだ。
背景には、大規模言語モデル(LLM)など生成AIの普及に伴う計算需要の急増がある。
GPUとストレージを物理的に隣接させる従来構成では、設備拡張や地理的制約が課題だった。
IOWN APNを導入することで、これらを分散配置したまま、高速大容量かつ低遅延を実現し、柔軟なAI基盤構築が可能になる。
2025年7月には、約1,000km離れた福岡と東京を想定した疑似環境で事前検証を実施。
画像認識と言語学習の2つのタスクで、遅延15ミリ秒条件下でも性能低下は12%程度にとどまった。
これにより、社会実装の可能性を高める結果となった。
今後11月から12月にかけて、IOWN APNの実回線を用いた本格的な検証を行い、商用利用への実現性を確認する予定だ。
NTT東西は通信環境を、GMOはAI処理基盤を、QTnetは福岡側の実証環境をそれぞれ提供する。
分散型AI基盤が切り拓くIOWN時代の可能性
GMOインターネットとNTT東西、QTnetの実証は、生成AI時代の新たなインフラ像を示したと言える。
大規模言語モデルの普及に伴い、AI演算を支えるGPUとストレージの需要は急増していると考えられる。
IOWN APNの超低遅延通信を用いることで、従来の物理的な制約を取り払い、遠隔地間でも高速・安定な分散処理を実現できる点は大きな利点だろう。
事前実証での良好な結果は、地理的分散型データセンターの現実的な選択肢を提示したと言える。
一方で、実環境での通信品質やコスト面の課題も残されており、今後の本格検証での成果が注目できる。
AI基盤の分散最適化は、災害に強い社会構造やリソースの効率利用にもつながると考えられ、日本のデジタルインフラ戦略に新たな方向性をもたらすだろう。
GMOインターネット ニュース:https://internet.gmo/news/article/88/?utm_source=chatgpt.com
関連記事:NTT Com、IOWN APNによる3拠点分散DCでの生成AI学習に世界初成功













