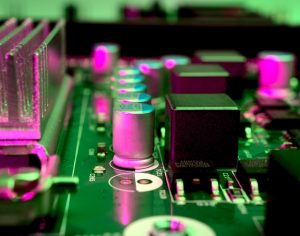ソフトバンク、AI計算基盤と理研の量子コンピュータを接続開始 ハイブリッド計算で事業化へ前進

2025年9月29日、ソフトバンク株式会社と理化学研究所は、学術情報ネットワーク「SINET」を介して両者の計算基盤を相互接続し、10月から運用を開始すると発表した。
量子コンピュータとスーパーコンピュータを融合させたハイブリッド環境の構築と事業化を目指す。
量子とAI基盤を結合 産学連携で研究開発加速
今回発表された取り組みは、経済産業省の「ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業」の一環である。
NEDO(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)が公募した「計算可能領域の開拓のための量子・スパコン連携プラットフォームの研究開発」に、ソフトバンクと理研が提案し・採択された「JHPC-quantum」プロジェクトに基づくものだ。
これまで理研の量子コンピュータは、東京大学や大阪大学が運用するスーパーコンピュータと連携してきたが、今回新たにソフトバンクのAIデータセンターに構築された計算基盤が接続される。
この接続には、国内の大学や研究機関を支える学術情報ネットワーク「SINET(※)」の接続サービスが活用される。
低遅延の高速通信によって量子とスーパーコンピュータの密な連携が可能となり、応用研究や事業化に向けた検証が加速する見通しだ。
プロジェクトでは、量子・HPC連携アプリケーションの開発と有効性の検証も進められる。
ソフトバンクは、量子コンピュータ応用の社会実装を視野に入れ、次世代社会インフラ構築に資する研究成果を事業化へと結びつけたい考えである。
同社は今後、テストユーザーの要望に応えるため、SLA(サービス品質保証)やセキュリティ基準、運用ルールの整備を進める。
同時に、事業化を見据えた実証検証にも取り組む方針だ。
※SINET(サイネット):国立情報学研究所が運用する学術情報ネットワーク。
国内の大学や研究機関を結び、高速・大容量の通信基盤を提供している。
量子とAI基盤接続が示す意義と今後の焦点
ソフトバンクと理研が進める今回のプロジェクトは、産学連携による先端技術開発の象徴と言える。
量子コンピュータとスーパーコンピュータを結び付け、AI基盤を活用することで、これまで難しかった計算領域の拡張が期待できる。
SINETによる低遅延の通信環境は、両者の協調動作を支え、応用研究や事業化に向けた検証を加速させるだろう。
また、製薬や新素材開発、金融シミュレーションなど社会的インパクトの大きい分野で新たな計算手法を提供できる可能性がある。
ソフトバンクがSLAやセキュリティ基準を整備し、運用標準を固めていく姿勢も、産業利用に向けた信頼性を高める要素となるだろう。
一方で、量子技術は依然として安定稼働や、コスト面で課題を抱えていると考えられる。
制度設計や市場ニーズへの適応が不十分であれば、事業化は停滞しかねない。
今後は、技術開発の進展に加え、利用者に応じたサービス水準やセキュリティ強化をどこまで実現できるかが鍵となるだろう。
産業応用の広がりは、この基盤がどれほど実用的な成果を示せるかに左右されるとみられる。
ソフトバンク プレスリリース:

関連記事:理研とIBM、量子とスパコンの連携を開始 神戸で国内初の運用体制整備
https://plus-web3.com/media/latestnews_1000_3880/