内閣府、医療データ利活用を加速へ 治療法や新薬開発の推進を視野に検討会設置
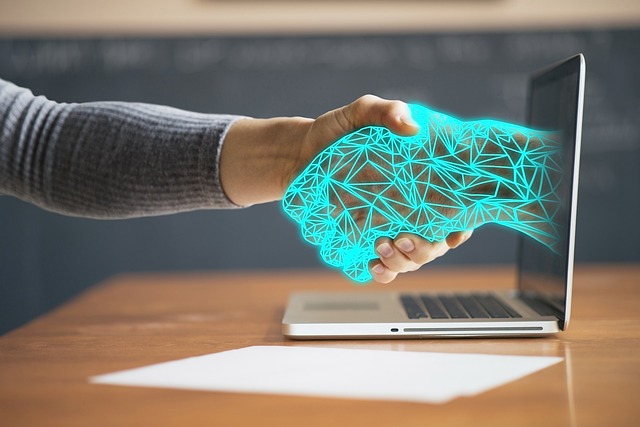
2025年9月3日、内閣府は医療データの活用促進を目的とした検討会を立ち上げた。
電子カルテやPHR(パーソナル・ヘルス・レコード)の二次利用を進め、治療法や医薬品開発への応用を目指す。
年内に中間報告をまとめ、27年通常国会への法案提出も視野に入れている。
内閣府、医療データ活用へ検討会を設置
内閣府は3日、医療データを活用した治療法や新薬の開発を推進するため、「医療等情報の利活用の推進に関する検討会」を発足させた。
座長には東京大学名誉教授の森田朗氏が就任し、日本製薬工業協会や経団連、日本医師会、国立情報学研究所、国立がん研究センターなどの関係者が参加した。
検討会では、電子カルテや個人の健康情報を蓄積するPHR(※)を対象に、連携基盤の整備などについて議論し、治療法などの開発に役立てる方針だ。
12月に中間報告をまとめ、最終的には2026年夏までに議論を整理。必要に応じて法改正を行い、2027年通常国会に法案提出を目指す。
収集方法については、医療機関や学界から一定の強制力やインセンティブを用いて集める案が検討されている。
また、集めた文書や画像をAIで構造化し、研究開発で活用しやすくする仕組みも焦点となる。
一方で、セキュリティ強化や匿名化処理の徹底は不可欠とされ、データ提供の義務化や費用負担の在り方も慎重に探る。
政府は6月に「デジタル社会の実現に向けた重点計画」を閣議決定しており、医療データの二次利用を円滑化する方針を示していた。
今回の検討会は、その具体化に向けた第一歩と位置付けられる。
城内実科学技術担当相は「有効な治療法や医薬品、医療機器などを開発し、医療の質向上を図っていくためには、医療データの利活用を一層促進することが大事だ」と強調した。
※PHR(パーソナル・ヘルス・レコード):個人が自身の健康・医療情報を収集・管理し、必要に応じて医療機関や研究機関と共有する仕組み。
研究促進と制度信頼、医療データ活用の行方
医療データの利活用は、医療研究や産業競争力を変える可能性がある。
電子カルテやPHRを統合すれば希少疾患や個別化医療の研究が進み、製薬企業や研究機関はより短期間で成果を得られるとみられる。
AIによるデータ構造化が進めば臨床試験や医療機器開発にも応用でき、国際競争力の向上にもつながるだろう。
短期的には、データ連携基盤や匿名化技術の導入が優先課題となるだろう。
医療機関や患者が安心できる仕組みを早期に整えれば、制度への信頼が高まるとみられる。
中期的には、研究成果の蓄積により精密医療や新薬開発が加速する可能性がある。
データアクセスの拡大は産業界の競争力を高め、海外との共同研究も進むと予想できる。
ただし透明性が欠ければ社会的反発を招きかねない。
長期的には、医療制度全体を再編する契機となり得る。
高齢化社会を背景に予防医療や地域医療への応用が広がるだろう。
一方で「患者中心」か「産業優先」かで評価は分かれ、政策設計のバランスが成否を左右すると考えられる。
関連記事:内閣府がAI政策推進室を新設 戦略本部の9月発足に向け司令塔機能強化へ
https://plus-web3.com/media/latestnews_1000_4557/












