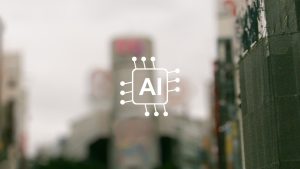AIと5分ほどの会話から認知機能を測定 塩野義製薬とFRONTEOが10月提供へ
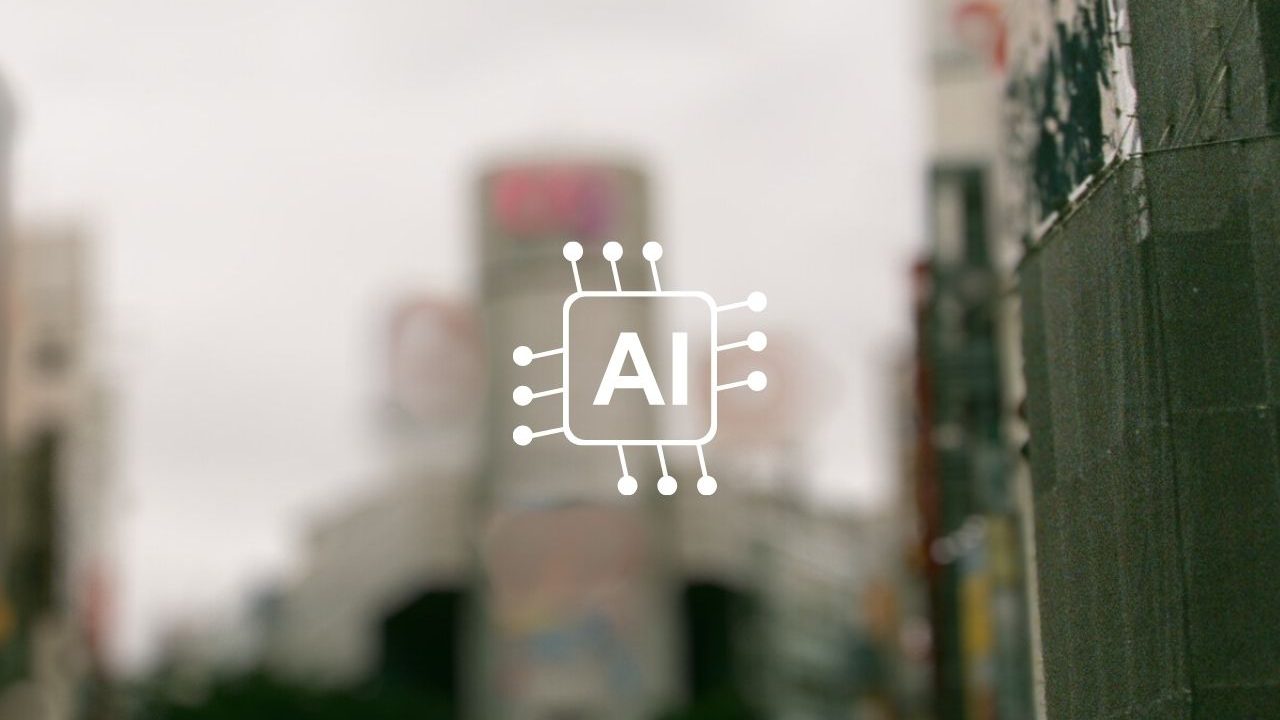
2025年9月3日、塩野義製薬とAI企業FRONTEOが、数分間の会話で認知機能を評価できる新サービス「トークラボ KIBIT」を提供開始すると発表した。
日本国内で10月から提供が始まり、保険付帯サービスや介護施設での導入が見込まれている。
塩野義とFRONTEO、会話型AIで認知機能を簡易チェック
塩野義製薬とFRONTEOが共同開発した「トークラボ KIBIT」は、AIと数分間会話するだけで認知機能の状態を測定できるアプリだ。
出題されたテーマについて回答すると、AIが語彙の豊富さや情報量などを解析し、認知機能の状態を判定する仕組みになっている。
塩野義製薬の三春洋介執行役員は、「認知機能は一緒に暮らすご家族も状況について判断がつかない部分が多いと思う。
5分程度で認知機能のチェックができるので、日常生活の改善や健康への気遣いなどを考えるきっかけにもしていただけるのでは」とコメントした。
厚生労働省の推計によれば、高齢者の約3割が認知症や軽度認知障害を抱えており、早期発見・介入の重要性は高まっている。
本サービスはまず保険の付帯サービスとして展開される予定で、運転免許センターや介護施設など幅広い現場での利用が想定されている。
「トークラボ KIBIT」ウェブサイト:https://talklab-kibit.com/
認知症予防の新たな選択肢に 普及とリスク管理が焦点
「トークラボ KIBIT」は、短時間で結果を得られる点から、幅広い利用シーンに浸透していく可能性がある。
特に免許更新や介護現場といった場面で導入が進めば、認知機能低下をいち早く察知できる体制が整うだろう。
ただし、いくつかの課題も無視できない。
音声は極めてセンシティブな個人情報であるため、プライバシー保護やセキュリティ対策の徹底は必須となるだろう。
さらに、AIの判定に過度に依存すれば、誤判定によって利用者が不安を抱いたり、現場で不適切な対応が生じるリスクも残ると考えられる。
そのため、この仕組みはあくまで医師や専門家による診断を補完する位置付けで活用する姿勢が望ましいだろう。
今後は、利用環境が拡大するなかで、ユーザーに安心感と利便性を両立させる体験を提供できるかが鍵となりそうだ。
高齢化が進む日本社会において、このサービスが認知症予防の一助として定着するかは、制度設計や社会の受け止め方に大きく左右されると見込まれる。
関連記事:富士通が最新AI技術を公開 認知症の兆候検知など幅広く応用へ
https://plus-web3.com/media/latestnews_1002_4267/