宮崎市、定例会見動画にAI導入 自治体DXで発信力と業務効率化を両立
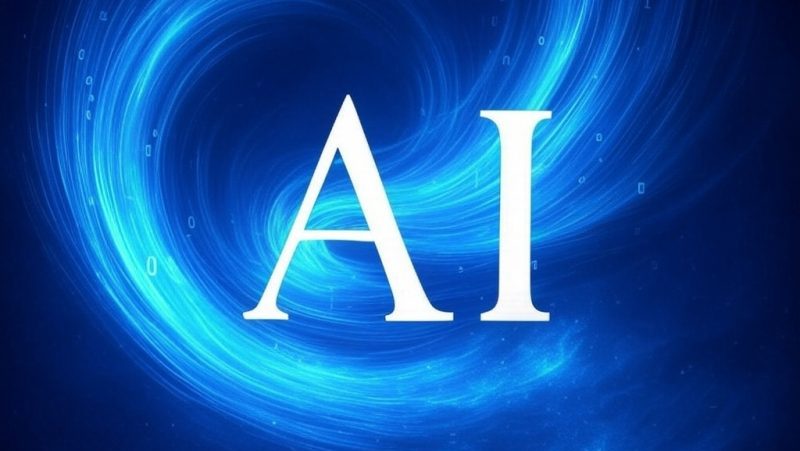
2025年8月6日、宮崎市は市長定例記者会見の要約動画に生成AIを導入したことを発表した。
従来型の15分動画に代え、約3分の短尺コンテンツを制作することで、市民への情報伝達力を高めつつ、職員の作業時間を大幅に削減した。
AIで要約・音声生成、作業時間を半減
宮崎市の広報広聴室は、毎月開催される1時間程度の市長定例記者会見から、要点のみを抜き出した動画をYouTubeで公開してきた。
これまでは、原稿作成から撮影・編集まで人力で行う15分程度の動画が中心で、制作には約4時間を要していた。
2025年8月からは、要約原稿の自動生成と音声読み上げにAIシステムを活用し始めた。
市ホームページに掲載された会見内容のURLをAIに提示し、原稿の文字数や語調、「2分程度で要旨を説明する」といった条件を指示することで、下書きが自動生成される。
担当職員が内容の確認を行った後、声質や話速を設定するだけで音声データが完成する仕組みだ。
市民からは「1分とか2分に要約してくれていると分かりやすい」「アナウンサーがしゃべられているように聞こえた」と好意的な声も寄せられた。
清山市長自身も「撮影に30分ほどかかっていたが、10分で終わり事務軽減につながった」とコメントしている。
宮崎市は今後、AIを活用した発信業務をさらに高度化する方針を示している。
具体的には、市長のCGアバターに本人の声を合成することや、多言語への対応を検討しており、市民や海外の関係者への情報提供手段を拡充する考えだ。
AI活用で情報発信の即応性と多言語対応を強化へ
宮崎市が定例記者会見動画に生成AIを導入した取り組みは、今後、自治体における広報DXのモデルケースとして広がっていく可能性が高い。
制作工程の自動化により職員の負担を軽減しつつ、短時間で要点を伝える動画を提供できる仕組みは、住民の情報接触機会を高める手段として評価されており、他自治体が追随する導入事例も増えていくと予想できる。
将来的に、市長アバターの生成や多言語対応が実現すれば、災害や緊急時など即応性が求められる場面においても迅速に高品質なコンテンツを配信できる体制が整うだろう。
特に国際交流の推進を目標に掲げる地方自治体にとって、外国人住民に対する情報提供手段として活用価値が高く、国内外への発信力強化に直結する可能性がある。
一方で、AI生成コンテンツが高度化すればするほど、情報の正確性や倫理的課題に対するガバナンス強化は不可欠となるだろう。
今後「AIが自動生成する範囲」と「人間が最終確認を行う範囲」を明確に線引きした運用体制が標準化されていくとみられる。
また、信頼性評価のプロセスを内部に組み込み、継続的に改善していくことが自治体DXの定着を左右する重要な要素となりそうだ。
関連記事:富山市、AIと防災無線を連携 クマ検知で自動放送の実証実験開始
https://plus-web3.com/media/latestnews_1000_4360/












