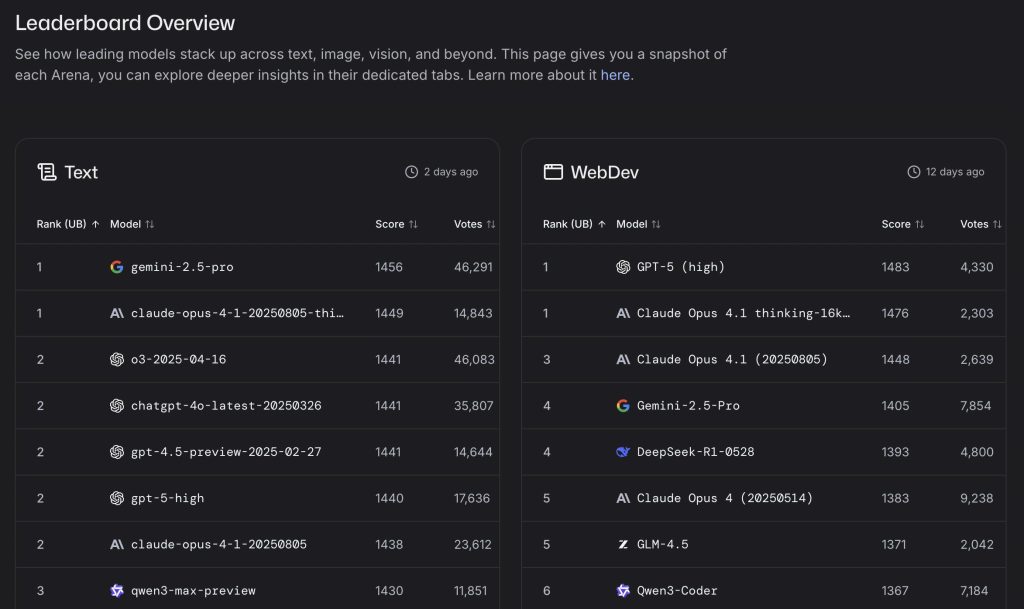経産省、スマホやモバイルバッテリの回収義務化へ リチウム電池リスク低減狙う

2025年8月12日、経済産業省はモバイルバッテリやスマートフォン、加熱式たばこデバイスを「指定再資源化製品(※)」に追加指定する案を公表した。
事業者に自主回収と再資源化を義務付けるもので、パブリックコメントを経て10月に政令を公布する方針である。
3製品を新たに指定、事業者に回収・再資源化を義務付け
経産省が取りまとめた案では、電源装置(モバイルバッテリなど)、携帯電話用装置(スマートフォンなど)、加熱式たばこデバイスの3品目を指定再資源化製品に追加する。
これにより、対象製品の製造・販売事業者は、自主的な回収と再資源化を行う義務を負うことになる。
背景には、資源有効利用促進法に基づく任意の回収制度では回収量や安全対策に限界があるという指摘がある。
指定再資源化製品ワーキンググループは、包括的かつ強制力のある制度の導入が必要だと結論づけた。
追加指定の理由は、レアメタルを含む小型リチウムバッテリの回収量拡大(資源性)、廃棄時の発煙・発火リスク低減(安全性)、一体型バッテリ製品の回収体制強化である。
義務化の対象基準は、電源装置で年間1,000台以上、携帯電話用装置で1万台以上、加熱式たばこデバイスで30万台以上の生産または販売量を有する事業者である。
電気掃除機やハンディファンなど他のリチウムバッテリ製品も、今後状況を見ながら追加指定が検討される。
※指定再資源化製品:資源有効利用促進法に基づき、事業者が自主回収と再資源化を行う製品群。
資源循環と安全性向上の分岐点 義務化の成否は体制とコスト両立に左右
今回の義務化は、希少資源の国内循環や廃棄物処理時の事故防止を加速させる契機となる可能性が高い。
特に、モバイルバッテリやスマートフォンは回収率の低さや廃棄時の発火事故増加が課題となっており、回収ルートの整備と義務化の組み合わせによって改善が進むとみられる。
経済面では、リサイクル関連産業の拡大や新たな資源供給網の構築が促進される一方、対象事業者には回収・処理コストの増加が避けられず、中小規模のメーカーや輸入業者への負担が課題として浮上する可能性がある。
消費者に対しても、回収拠点の積極的な利用や分別の徹底が求められ、運用の不備が制度の実効性を損なうリスクも残るだろう。
政令公布施行後は、大手メーカーや流通事業者が主導して回収ルートを確立する動きが加速すると予測できる。
さらに、リサイクル技術が高度化し、回収バッテリからの資源抽出効率が向上すれば、経済的インセンティブが制度の持続性を押し上げる要因となるとみられる。
一方、技術革新が遅れ、処理コストが高止まりすれば、事業者の負担感が増し、制度見直しを求める声が強まる恐れもある。
最終的には、回収体制の利便性と経済合理性をいかに両立できるかが、この制度の長期的な成否を左右することになりそうだ。
関連記事:ソニー、廃棄テレビ部材を新品のテレビにリサイクル開始 困難だったテレビ部材の再利用を可能に
https://plus-web3.com/media/haikiterevibuzairisiclekaisi20250423/