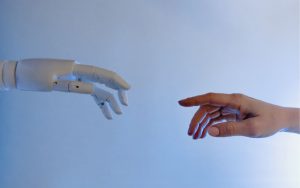スバルが“支援型無人機”を防衛装備庁に納入 有人戦闘機と編隊飛行へ向け実証段階に
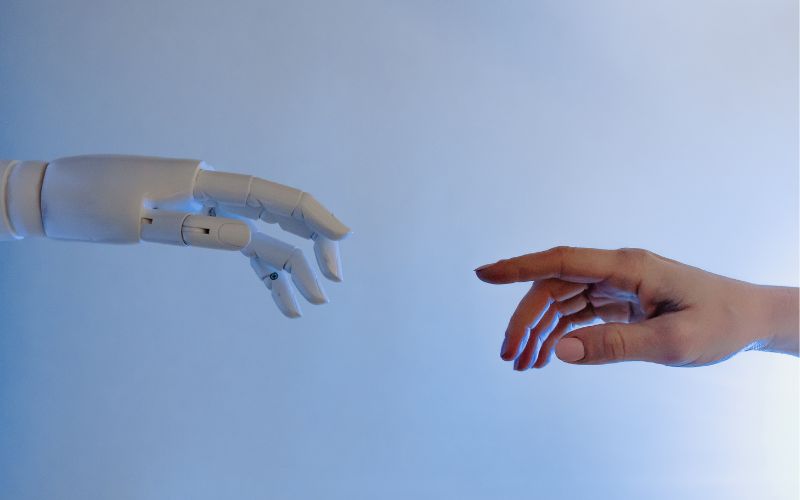
2025年7月9日、スバルは防衛装備庁に対し、有人戦闘機と連携する無人航空機「遠隔操作型支援機」の実験機を納入したと発表した。
実機画像や編隊飛行の様子を収めた動画も同時に公開され、実証研究が本格化している。
有人機と連携する無人支援機、実証段階へ
スバルが納入したのは、防衛装備庁が進める「有人機と連携して任務を遂行する無人航空機技術」の一環として開発された「遠隔操作型支援機」の実験機である。
機体の画像とあわせて、編隊飛行や離着陸を行う様子を撮影した動画が公式に公開された。
映像からは、機体の全長がおおむね成人男性と同程度であることが確認でき、塗装は薄いグレーを基調に橙色のアクセントが施されている。
防衛装備庁では、パイロットが自機を操縦しながら複数の無人機を同時に管制する技術や、有人機や他の無人機から得た情報をもとに、無人機が自律的に飛行経路を算出・変更するアルゴリズムの研究にも取り組んでいる。
防衛装備庁は今後、スバルの支援を受けながら、複数の実験機を用いた模擬任務の飛行試験などを行い、無人機の実用化に向けた研究を進めていく方針だ。
“分散型戦術”の鍵となる技術、民間主導で加速か
遠隔操作型支援機の導入が進めば、有人機に過度なリスクを負わせることなく、敵地偵察や電子戦などの任務を無人機が代行できるようになると思われる。
従来の一機集中型運用とは異なり、「分散型戦術」への転換が可能となる点は、安全性や柔軟性の面で大きなメリットといえる。
特に、日本における人材不足やパイロット養成コストの高さを背景に、自律・遠隔操作型の航空戦力は現実的な選択肢となりつつある。
一方で、運用段階での懸念もある。
無人機に与える指示の安全性確保や、万が一の暴走リスクへの対策、敵による妨害やハッキングといったサイバーセキュリティ面の脆弱性も克服すべき課題だろう。
また、国際的な無人兵器の規制議論が加速する中、日本の技術開発がどのような透明性と説明責任を伴うかも問われる可能性がある。
今回の納入は、国内防衛産業が無人戦闘技術の実用化フェーズに移行しつつあることを示す象徴的な動きといえる。
今後は、模擬任務下での飛行試験を重ねつつも、実運用に向けた機能統合と信頼性をどのように確保するかが課題になるだろう。