京都の神社に30通超の脅迫メールを送信 AI擁護への不満が動機と語る男を逮捕
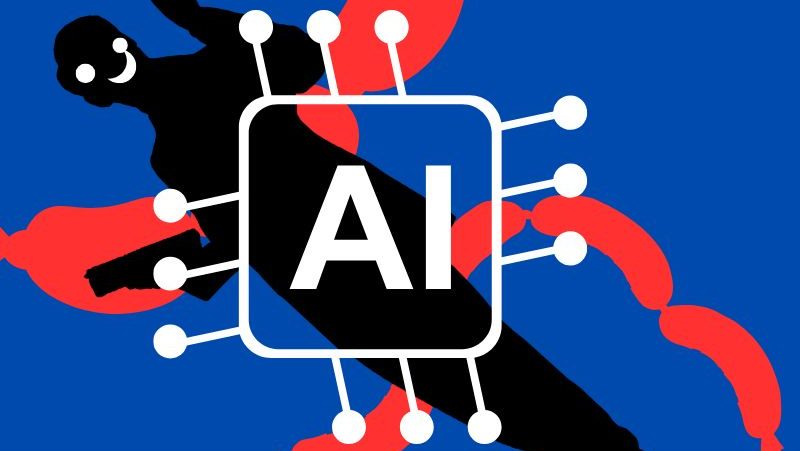
京都市の神社に対し「全焼するぞ」などと30通以上の脅迫メールを送った疑いで、滋賀県在住の無職の男が逮捕されたことが、2025年7月4日に報じられた。
男は、神社が生成AIで制作した画像をSNSに投稿した姿勢に憤りを覚えたと供述している。
AI擁護に憤り、京都の神社に脅迫 無職の男が逮捕
逮捕されたのは滋賀県野洲市の無職、広沢和人容疑者(38)。
警察によると、同容疑者は2025年3月、京都市右京区にある車折(くるまざき)神社に対し、「叩き殺してやる」「いつか原因不明の火事で全焼するぞ」などといった内容のメールや画像を、30通以上にわたり送信した疑いが持たれている。
捜査関係者によれば、神社側が通報し、メールの送信元などの解析から広沢容疑者を特定した。
容疑者は「間違いありません」と容疑を認めているという。
車折神社は、芸能人やクリエイターが参拝することで知られ、SNSでの情報発信も盛んに行っていたが、今年3月に生成AIで制作した巫女のイラストを投稿したところ、ネット上では賛否が分かれていた。
広沢容疑者は、こうした神社側の「AI絵師を擁護する態度」に激高したと動機を語っている。
表現の自由と暴力の境界線 生成AI時代に問われる責任とリテラシー
今回の事件は、生成AIをめぐる価値観の対立が実際の脅迫へと発展した、極めて異例のケースといえる。
生成AIは、誰もが創作活動に参加できる可能性を広げるツールであり、特にイラストや音楽などの分野で新たな表現の扉を開いている。
一方で、生成AIの活用のあり方によっては、既存の職業倫理や創作文化との摩擦が生じる場合もある。中でも「AI絵師」と呼ばれる存在への反発は根強く、ネット上での中傷が現実の犯罪にまで波及した事実は深刻だ。
表現の自由や技術革新といった利点の陰には、社会的分断や暴力的反応といったリスクも潜んでいることが、今回の事件から浮き彫りになった。
生成AIの普及により、芸術や宗教といった価値観の深い領域では、表現をめぐる衝突が今後も続く可能性がある。表現者には説明責任と配慮が求められる一方で、生成AIによるコンテンツには注釈や制作意図の開示が、対話を促す重要な契機となるだろう。
また、SNSのリテラシー教育に加え、脅迫・中傷への法的な対応強化も必要になると考えられる。
表現への強い執着や偏った正義感が、暴力的手段に向かう構図は、生成AIに限らず、ネット社会全体に共通する課題といえる。












