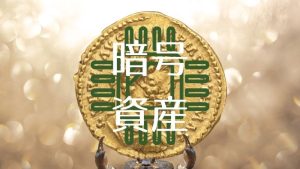財務省、自己管理型暗号資産の差押え困難を公表 国税徴収の実務で課題顕在化
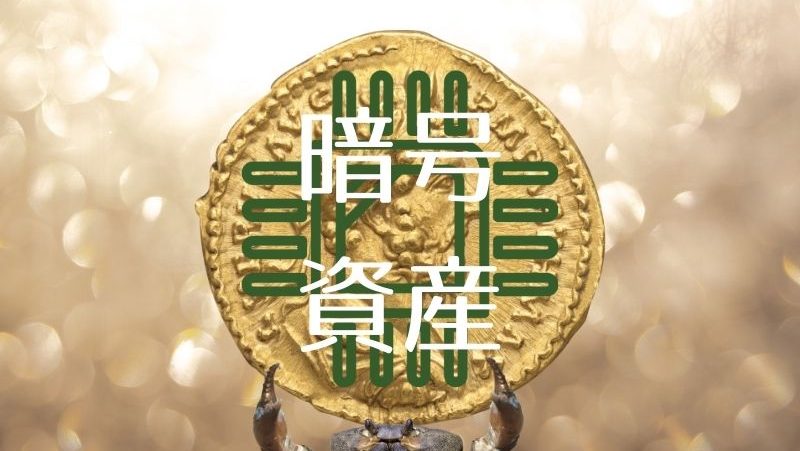
2025年11月13日、日本の財務省は専門家会合で公表した資料で、滞納者が自己管理型ウォレットで保有する暗号資産について差押えが行えない現状を示した。
国税徴収の現場で対応が難航する事例が明記された。
自己管理型ウォレットは差押え不能と明記 財務省が課題を整理
財務省は11月13日に開催した「経済社会のデジタル化への対応と納税環境整備に関する専門家会合」で、税務執行に関する課題を記した資料を公開した。
資料では、滞納者が自己管理型ウォレット(※)で保有する暗号資産は、差押え手続きを行う仕組みが存在しないと整理している。
示された事例では、滞納者が暗号資産取引で約5億円の所得を得ながら申告せず、税務調査の結果、約2億5千万円の追徴課税が確定した。
その後、暗号資産価格が下落したため納付が進まず、国税当局が資産売却を勧めても、本人は「値上がりしてから売却する」と述べ、納付に応じなかったと説明されている。
資料は、暗号資産交換業者を介して保有している場合には、業者に対する債権を差し押さえることが可能であると記載した。
一方で、自己管理型ウォレットに保管されている資産は第三者の関与がないため、差押え対象にならないと明確化している。
また、地方税についても同様の課題が存在することが付記された。
暗号資産の普及が進む中、既存の徴収手続きが適用しにくい領域が具体的に示されたことで、税務行政における対応の難しさが浮き彫りになった。
※自己管理型ウォレット:秘密鍵を利用者本人が保持し、第三者サービスを介さずに暗号資産を管理する方式。
徴収公平性の確保と利用者自由の両立が課題に
財務省が示した事例は、暗号資産の利用形態が多様化する中で、徴収手続の実効性と資産管理の自由度の両立をどのように図るかという制度的課題を突きつけている。
自己管理型ウォレットは秘密鍵を利用者が保持するため、第三者リスクを抑えられるという利点があるが、徴収当局がアクセスできない構造は、滞納時の対応を阻む要因となり得る。
この特性は、個人の資産管理の自由度を高める反面、強制徴収の必要が生じた際に手段が限定されるという構造的な制約をもたらすだろう。
利用者保護と徴収の公平性の観点からも、自己管理型資産をどの範囲で制度的に扱うかは慎重な検討が求められそうだ。
制度を見直す場合、過度な規制が暗号資産の利便性を損なう可能性がある一方、現行制度では徴収の実効性が十分に確保されない場面が生じる。
こうした緊張関係をどう調整するかが、今後の議論の焦点となるだろう。
暗号資産の利用拡大に伴い、税務行政には新たな判断が迫られる局面が続くと考えられる。
従来の枠組みでは対応しきれない領域が拡大する中で、徴収制度の再設計や技術的対応の検討が進む可能性がありそうだ。
関連記事:
米財務省、ジーニアス法に基づく意見募集開始 AIやブロックチェーン活用に注目