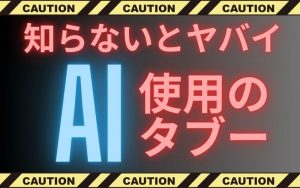アニメ・出版17社と2団体、生成AI時代の著作権保護に関する共同声明を発表
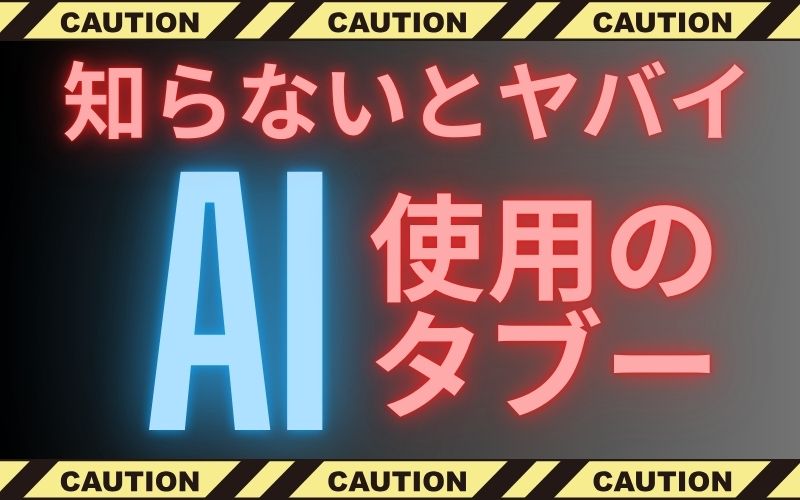
2025年10月31日、日本動画協会や講談社、小学館などアニメ・出版関連17社と2団体が、生成AIによる創作物の権利保護に関する共同声明を発表した。AI時代における創作物の利用と保護の両立を目指す国内の動きである。
生成AIの創作物利用に関する国内17社の原則表明
共同声明では、OpenAI社の映像生成AI「Sora2」による著作物の利用状況を背景として、権利者の明示的な許諾なしに生成AIが学習や公開を行う仕組みへの懸念が示されている。
著作権法やWIPO条約の原則に沿わない運用は文化的創造の持続可能性を損なうという。
声明では、生成AIの進展を歓迎しつつも、学習段階・生成段階における権利者許諾の取得や透明性確保、適正な対価還元を原則とする必要性が強調されている。
加えて、利用者が知らずに他者の著作物を生成・公開することによる権利侵害防止のため、AI事業者や権利者、行政などステークホルダー間での協力が不可欠との見解も示された。
具体的な懸念点として、オプトアウト原則のまま権利者が許諾を求める仕組みでは、権利侵害のリスクが高まると指摘されている。また、学習データの透明性が担保されなければ、生成物の権利確認や創作者評価の保護は困難だという。
今後の対応方針として、生成AIの活用自体を否定するのではなく、法的・倫理的観点での権利保護を重視しつつ、クリエイターと利用者双方が安心して創作・利用できる環境整備を進める姿勢であることが示された。
権利保護強化で創作環境はどう変わるか
今回の共同声明は、生成AI活用の拡大と著作権保護の両立を模索する国内業界の姿勢を明確に示すものであると言える。権利者のオプトイン制度徹底や透明性確保により、創作者が自らの作品利用状況を把握しやすくなると考えられる。
一方で、生成AI事業者にとっては、利用許諾取得や対価還元の実務負担が増加するリスクも存在する。特に、膨大な既存作品を学習データに含める場合、許諾手続きの効率化が課題となりそうだ。
業界全体では、権利保護の明確化がクリエイターの信頼醸成につながり、安心して創作活動を継続できる環境構築の追い風になると見込まれる。
また、利用者側も法的リスクを意識した創作が促され、コミュニティ全体で健全な文化形成が期待される。
将来的には、国内での取り組みが国際的な生成AI規制の議論に影響を与える可能性もある。
透明性と対価還元を両立させるモデルケースを国内で確立できれば、海外企業や団体に対する指針となり、創作と技術革新のバランスを探る先駆的な取り組みとなるかもしれない。
関連記事:
「Sora 2」の日本アニメ酷似動画に政府が懸念 OpenAI、著作権対策を強化へ