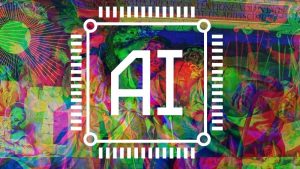広島市、AI活用で被爆者と対話 次世代への証言継承を目指す
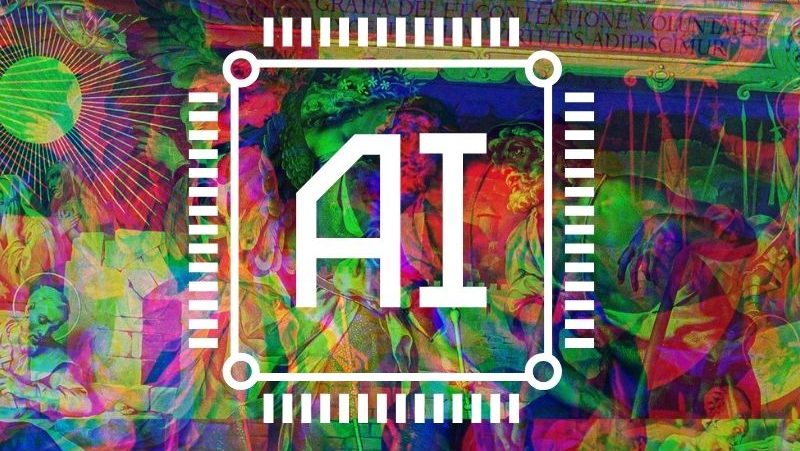
2025年10月16日、広島市はAIを活用し被爆者と対話できる「被爆証言応答装置」を製作したと発表した。高齢化が進む被爆者の体験や平和への思いを、学校教育や体験会を通じて次世代に伝える取り組みとして注目される。
AIが質問に応答 被爆体験を双方向で伝える装置完成
広島市が開発した「被爆証言応答装置」は、利用者の質問に応じてAIが解析し、事前に収録された被爆者インタビュー映像から適切な回答を再生する仕組みである。生成AIのように回答を作り出すのではなく、証言者自身の声を忠実に伝える点が特徴だ。
装置は常設2台、可搬3台の計5台が用意され、端末ごとに証言者を切り替えられる仕様である。日本語と英語に対応しており、誰でも直感的に操作できるユニバーサルデザインが採用されている。
撮影は5人の証言者が協力し、半日×3回のインタビューで200問以上の一問一答形式映像と30分程度の証言ビデオを収録した。
質問リストは、将来的に利用者が尋ねる可能性のある内容を想定し、小中高校生の公募や平和学習プログラムで集めた600以上の質問を整理・分類して作成された。
試用開始後は、回答精度や操作性の評価を継続し、改善を図る計画だ。
市内学校での体験会や可搬型装置による出張学習を通じ、児童・生徒や教員のフィードバックをもとに運用方法を最適化し、従来の講話形式に近い双方向の学習体験として活用することを目指している。
デジタル化による継承の利点と課題、今後の平和教育への影響
AIを活用した被爆証言装置は、物理的制約に縛られずに証言を長期保存できる点で大きなメリットを持つ。
遠方の学校や国際的な学習機会でも活用可能なため、従来の講話聴講に比べ、より多くの学習者が平和教育に触れやすくなるだろう。
特に、英語対応の映像により、世界中の学習者が日本の被爆体験を理解できる機会が増えることから、広島市の取組は国内外における平和教育のモデルケースとなる可能性が高い。
一方で、装置は録画済み映像に基づくため、想定外の質問には回答できない可能性がある。
また、AIが回答生成を行わないため、証言者が経験していない新たな質問には対応できないと思われる。
教育者による補足が依然として必要となるだろう。
今後は、装置の利用データをもとに質問リストや映像の拡充を図ることが予測される。
VRやメタバース技術などと組み合わせれば、より没入感のある平和学習が可能になるかもしれない。
デジタル技術の活用により、被爆者不在の時代においても次世代への平和継承が持続可能になりそうだ。