東北・新潟に次世代データセンターを誘致推進 東北電力・NTT東日本・DBJが協定を締結
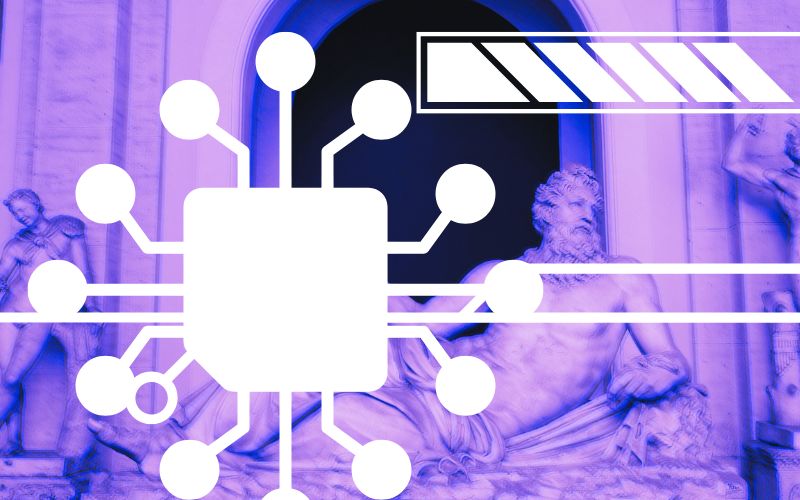
2025年10月16日、東北電力、NTT東日本、日本政策投資銀行(DBJ)の3社が、東北・新潟地域へのデータセンター誘致に関する業務協力協定を締結した。生成AIの普及で急増するデータ処理需要に対応し、地域の再生可能エネルギーを活用した分散型インフラの構築を目指す。
再エネと冷涼な気候を武器に 東北・新潟がデータセンター誘致へ
今回の協定は、データセンター(※)の国内分散を推進する国の「GX2040ビジョン」を背景にしたものだ。
電力・通信リスクを軽減するため、地方への産業集積を促す狙いがある。
東北電力、NTT東日本、日本政策投資銀行(DBJ)の3社は、立地選定から企業誘致、情報発信までを一体的に進める。
特に東北・新潟地域は、風力や水力など再生可能エネルギーの供給ポテンシャルが高く、年間を通じて冷涼な気候がサーバー冷却に適している。
DBJが2025年4月に発表した調査によれば、東北地域は「生成AI等により近年拡大するDC利用の需要を取り込むことができる可能性がある」とされている。
本協定は、国策と民間主導の連携が結実したものと言える。
3社は今後、企業や自治体との連携強化を図りながら、東北・新潟を生成AI時代の新たなデータ拠点へと押し上げる方針だ。
※データセンター:サーバーや通信設備を集約し、企業や個人のデータを保管・処理する施設。近年はAIの学習処理やクラウドサービスの基盤として需要が急拡大している。
AI時代の「北の拠点」構想 雇用創出と地域活性の起爆剤となるか
データセンターの地方誘致は、エネルギーの地産地消を進めると同時に、地域経済の再活性化にもつながり得る。建設・運営に伴う雇用創出効果は大きく、通信インフラや再エネ関連産業の波及も期待される。
生成AIの普及で膨大な計算リソースが求められる中、冷却効率の高い地方立地は競争力を左右する要素になりつつある。データセンター需要を各地に分散できれば、災害リスクの低減や電力負荷の平準化にも寄与するだろう。
一方で、課題も少なくない。
送電インフラの増強や光ファイバー網の拡充には長期的な投資が必要であるため、電力需給の安定確保が不可欠になる可能性が高い。
また、自治体間の誘致競争が激化すれば、過剰な補助金や土地優遇策に頼るリスクも生じかねない。地元に残る利益をどう確保するかという「地域還元モデル」の設計が不十分であれば、外資や大企業による一極支配に陥る懸念も残る。
それでも、政府のGX政策と企業の脱炭素経営が重なり合う今こそ、地方のポテンシャルを活かす好機であると考えられる。
東北・新潟の挑戦が、日本全体のデジタル・グリーン融合モデルとなるか、引き続き注目したい。
関連記事:
ゲットワークス、苫小牧にAI拠点 GPU搭載コンテナ型データセンター建設へ













