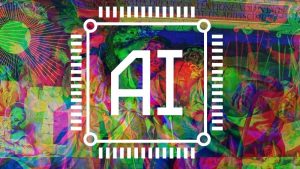Google、AI動画生成「Veo 3.1」発表 映像制作の自動化でSoraに対抗か
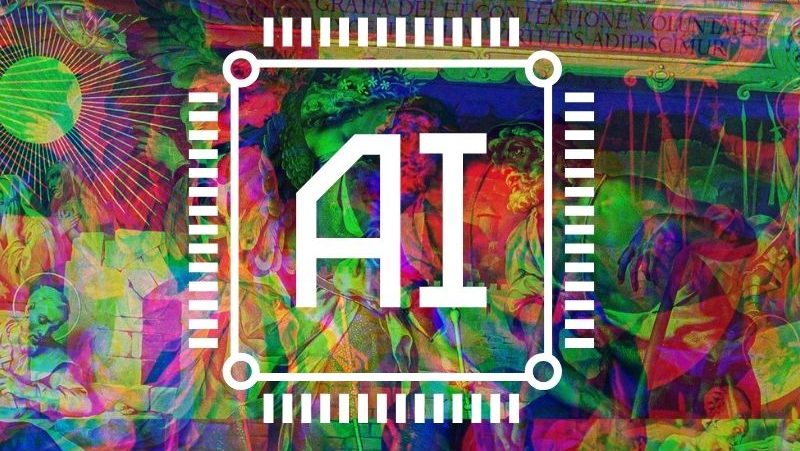
2025年10月15日、米GoogleはAI動画生成モデル「Veo」の最新版「Veo 3.1」を正式発表した。
有料版Geminiユーザー向けに提供が始まり、Flow、Gemini API、Vertex AIを通じて利用可能だ。
Flowと統合、映像生成をワンストップ化した「Veo 3.1」
新たに発表された「Veo 3.1」では、Googleが開発するAI映像制作ツール「Flow」で先行導入されていた複数の機能が統合された。
動画素材、画像、音声を個別にアップロードするだけで、AIが自動的に構成・編集・合成を行う「Ingredients to video」機能を備えており、実用性に優れている。
さらに、不要なオブジェクトの削除や、新たな要素の追加など、従来は手動で行っていた作業を自動化することもできる。
また、静止画2枚から滑らかなトランジション映像を生成できる機能も搭載した。
生成できる映像の長さは最大1分超に拡張され、短尺広告やプロモーション映像の制作効率が大幅に向上した。
Veoシリーズは、今年5月の年次開発者向け会議「Google I/O」で初登場したもので、AIが映像に合わせて音声を自動生成する初のネイティブ音声対応モデルとして注目を集めた。
Googleは「nano banana」など、画像生成AIの開発も並行しており、マルチモーダル分野での技術優位性を強化している。
AI映像競争の激化 Soraとの対抗軸とクリエイティブの懸念
一方で、Googleの動きはOpenAIの「Sora 2」発表と対抗するものとみられる。
OpenAIは動画生成AI「Sora」を基盤としたSNSアプリを展開し、ユーザーが自作映像を共有する新たな潮流を生み出している。
招待コードを求めるユーザーが殺到するなど、一般層への浸透が進む中で、Googleはプロフェッショナル用途での差別化を狙っていると考えられる。
ただ、AI映像モデルの急速な普及は、クリエイティブ業界に懸念をもたらしている。
AIによる生成と人間の創作の境界が曖昧になるなか、ディープフェイクや著作権侵害などの問題も深刻化しており、倫理的問題と技術的競争の両方を問われる難しい局面となっている。
今後、SoraとVeoの競争は、単なる技術比較を超え、生成AIが「誰の創作か」という倫理的・法的課題を問う局面に入ると考えられる。