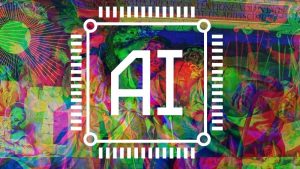武蔵野大学、GPTs活用の学修支援AI「AI先輩」導入 通信教育の孤独感を軽減へ
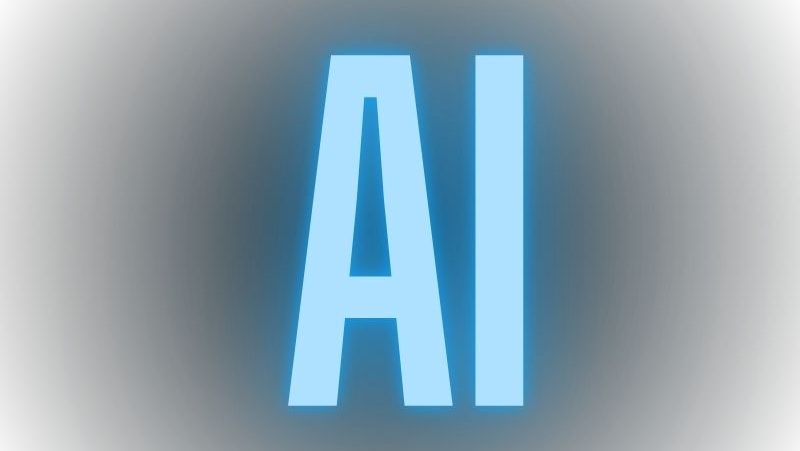
2025年10月14日、武蔵野大学(東京都江東区)は、通信教育部の心理学専攻を対象に、OpenAIのGPTsを基盤とした独自の学修支援サービス「AI先輩」をトライアル導入することを発表した。
通信教育の課題である孤独感や質問のしづらさを補うことで、学修意欲と理解の深化を支援することが狙いだ。
AIが「先輩」として学びに寄り添う 国内初のGPTs活用教育支援
武蔵野大学が10月からトライアル導入を開始した「AI先輩」は、授業で使用されている教科書や講義資料を学習し、学生からの質問に対して教科書に即した回答を行うAIシステムである。
OpenAIのGPTs(※)を基盤に同大学が独自にチューニングしたもので、国内の大学としては初の試みとなる。
通信教育は働きながらでも学べる柔軟さがある一方で、対話機会の少なさから孤独を感じやすく、学修モチベーションが続きにくいという課題が指摘されてきた。「AI先輩」は、そうした学びの「空白」を埋める役割を担う。
学生が理解に詰まった際や、授業内容の補足を求める際にAIが即座に応答し、さらに興味分野を深掘りする提案も行う。
先行トライアルでは通信教育部修了生3名が試用し、「難しい定義もわかりやすく整理され、モチベーションが上がった」「一人での学習でもつまずきを軽減できる」といった好意的な評価が得られた。
初期導入は心理学専攻の基幹科目「心理学概論」(1年次、受講者1,190人)を中心に、2〜4年次の共通科目「心と体の健康」や専門科目「行動療法」など計3科目で実施される予定だ。
※GPTs:OpenAIが提供する生成AIプラットフォーム。利用者が独自の知識データやプロンプトを組み込むことで、個別目的に最適化されたAIを構築できる仕組み。
学びのパーソナライズが進む教育現場 AI先輩が拓く新しい学修体験
「AI先輩」の導入は、通信教育における「孤独な学び」を変える契機となりうる。
AIとの対話を通じて学習内容を整理できるだけでなく、心理的な支えとしても機能する点が注目される。人との関わりが希薄になりやすいオンライン学習において、AIが「伴走者」として存在することで、継続率や学習効率の向上が期待できる。
一方で、AIによる回答が常に正確とは限らず、誤情報が含まれるリスクを伴う。
特に、心理学のように倫理的判断を伴う学問分野では、AIが提示する情報の限界を学生自身が認識することが重要になるだろう。
さらに、AIへの依存度が高まるほど、教員や学生間の直接的な交流が減少し、教育の本質である「人間的学び」の希薄化を招く懸念も残る。
AIはあくまで補助的存在に留めるという大学側の運用方針が、この先の鍵を握るといえよう。
今後、AI先輩の運用データをもとに、回答精度の向上や他学部への拡大が期待される。AIを活用した教育支援が定着すれば、学生一人ひとりに最適化されたパーソナライズド学習の実現に近づく可能性がある。
教育現場におけるAIの存在は、単なる利便性を超え、「学びのパートナー」としての価値を持ち始めていると言える。
関連記事:
追手門学院大学、大学公式アプリにマルチエージェントAIを導入 学生一人ひとりに最適化した学修支援を実現へ