「Sora 2」の日本アニメ酷似動画に政府が懸念 OpenAI、著作権対策を強化へ
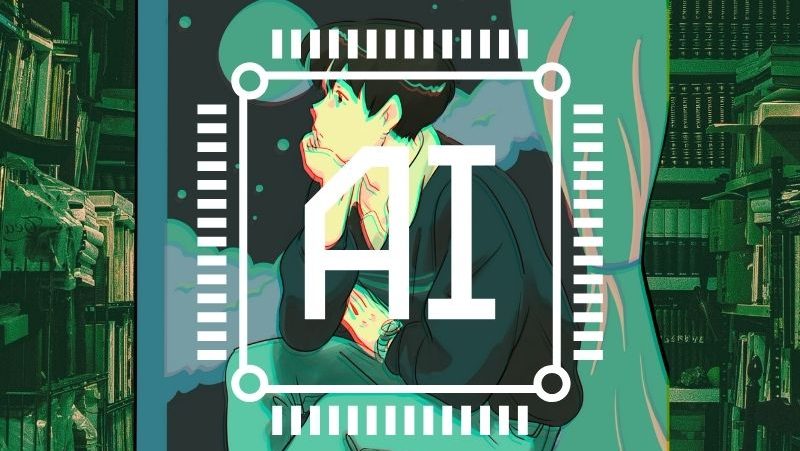
2025年10月7日、米オープンAIの動画生成モデル「Sora 2」で日本アニメに酷似した映像が生成されている問題を受け、デジタル相はオープンAI幹部と面会したことが報じられた。知的財産の保護を理由に改善を要請し、オープンAIは再発防止策を講じる方針を示した。
アニメ酷似動画が拡散 政府が懸念伝達、OpenAIが対策表明
米オープンAIが9月末に提供を開始した動画生成AI「Sora 2」が、日本の人気アニメやゲーム作品に酷似した映像を生成しているとして物議を醸している。
SNS上では「ポケットモンスター」や「ドラゴンボール」「ドラえもん」などに似た動画が投稿され、「著作権を侵害している」との批判が相次いだ。
これを受けて平デジタル相は7日、オープンAI幹部と面会し、政府として懸念を正式に伝達。日本の知的財産を損なわないよう、生成制限や監視体制の強化を要請した。
オープンAI側は重大な問題として認識しているとし、原因の説明とともに仕様変更を進める意向を示したという。
サム・アルトマンCEOは10月3日に「誤りは迅速に修正する」と表明し、著作権者が生成可否を設定できる仕組みを導入する方針を明らかにした。すでに、特定キャラクターの無断生成を防ぐブロック機能を強化している。
一方で、対象範囲の明確化や技術的制限の実効性には課題が残る。
自民党の塩崎彰久議員はAI法(※)に基づく調査権限の行使を示唆し、「海外プラットフォーマーに日本のルールをしっかり伝えるべきだ」と述べている。
※AI法:2025年6月に日本で施行された法律。生成AI事業者に対し、著作権侵害防止や学習データの透明性確保を求め、政府に調査権限を付与している。
AI創作の光と影 著作権保護と表現の自由がせめぎ合う
Soraの問題は、生成AI時代の創作の自由と著作権保護のバランスを問う典型例である。
AIによる映像生成はクリエイティブ業界の生産性を飛躍的に高め、個人でも映画並みの作品を作れる時代を開いた。
一方で、既存キャラクターや世界観の模倣が容易になり、創作者の権利を脅かすリスクが顕在化している。
既存作品に酷似した映像が容易に生成されることで、著作権侵害の境界が曖昧になり、権利者の利益が損なわれる懸念が強い。特に日本のアニメは世界的なブランド価値を持つため、無断模倣が横行すれば文化資産そのものの信頼性を損ねかねない。
さらに、AIが学習過程で使用するデータの透明性が担保されていない現状では、「どこまでがオリジナルで、どこからが引用か」という判断が極めて困難である。
オープンAIのような大手企業が権利者への管理権限付与を検討する動きは、法的整備が追いつかない現状を補完する暫定的な措置といえる。しかし、AIが自動的に学習する過程で著作物をどこまで参照しているかを把握するのは難しく、完全な防止策とはならない。
今後、生成AIと著作権保護の関係は国際的な政策課題としてさらに注目されるだろう。日本政府がAI法に基づく調査権限を積極的に行使する可能性もあり、AI事業者への透明性要求は一段と高まると考えられる。
生成AIが文化産業とどう共存していくか。今回のSora問題は、その試金石となるといえる。
関連記事:OpenAIのアルトマンCEO、「Sora 2」で権利者保護と収益分配の新方針を発表 日本の創作分野にも言及













