OpenAIの動画SNS「Sora」、米App Storeで首位に 「ChatGPT」や「Gemini」を上回る
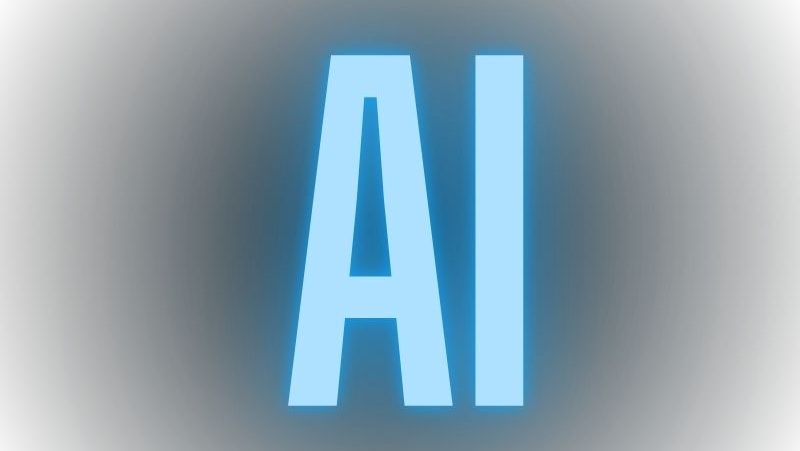
2025年10月3日、米OpenAIが提供するAI動画SNSアプリ「Sora」が、米国のApp Store無料アプリランキングで1位を獲得したと報じられた。
2位の「ChatGPT」や3位の「Gemini」を上回り、生成AIを核とした新しいソーシャルメディアの潮流を象徴する動きとなっている。
「Sora」、AI生成動画だけで構成されたSNSがApp Store首位に
OpenAIの新アプリ「Sora」は、TikTokに似た縦型の動画フィードを採用しながらも、配信されるコンテンツのすべてがAIによって生成されている点で従来のSNSと一線を画している。
特に、ユーザーが登録時に自身の顔と声を記録すれば、AIがその人物を動画内の登場キャラクターとして再現できる「cameo」機能が人気を集めている。
他者にSora上の自分の姿や声を利用させることも可能であり、擬似的な“共演”体験を容易に楽しめる。
現在、Soraは招待コードを持つiOSユーザーに限定公開されており、Android利用者はウェブ経由でのみアクセスできる。
Soraは、短時間で高精度の動画生成を実現するOpenAIの新Aiモデル「Sora 2」を生成エンジンとして搭載している。
Sora 2はユーザーが入力した数行のテキストから映像を生成でき、SNSとしてのSoraの流行において役割を果たしている。
ただし、こうした“完全生成型”SNSの拡大は、ディープフェイク(※)などの悪用リスクの懸念もある。
実際、Sora上ではCEOのサム・アルトマン氏が他社製品を称賛する架空映像なども作成でき、現実と虚構の境界がますます曖昧になりつつある。
※ディープフェイク:AIによって実在人物の容姿や声を模倣し、架空の映像・音声を生成する技術。
AI生成メディアが拓く新市場 創造の自由か、倫理の脆さか
Soraの台頭は、AI生成コンテンツが単なる補助技術から主役へと移行しつつあることを象徴している。
動画制作の手間を劇的に削減させ、創作未経験者でも短時間で映像を公開できる点は、SNS文化の民主化をさらに進めるだろう。
一方で、現実と虚構が交錯する空間では、著作権や肖像権の侵害リスクが急増すると思われる。
他人の顔をAI動画で使える仕組みは、倫理的に危うい面をはらんでおり、米国では法的議論が始まりつつある。
OpenAIが従来の「ChatGPT」に続いてSNS領域を押さえたことで、今後はGoogleやMeta、Anthropicなどとの競争構造がさらに激化する見通しだ。
しかしSoraがこの勢いを維持できるかは、ユーザー生成コンテンツとAI生成物の境界をどこまで透明化できるかにかかっていると考えられる。
創造と偽装が隣り合わせに存在するこのプラットフォームは、AI時代の“表現の自由”と“信頼性”の両立を問う試金石となるだろう。
関連記事:
OpenAI、新動画生成AI「Sora 2」とSNSアプリを同時発表 現実世界を高精度に再現













