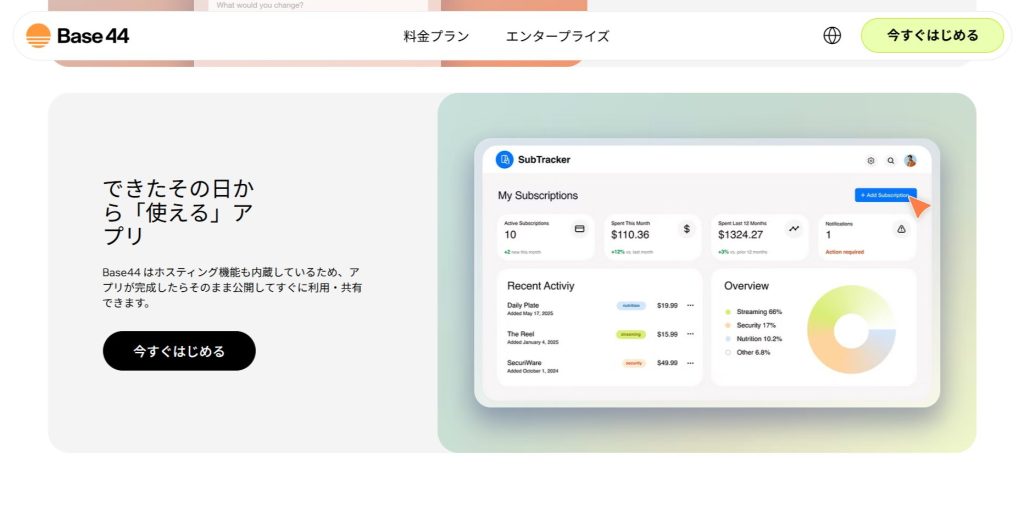尾花沢市、AI活用の乗り合い交通を導入 持続可能な移動手段へ実証運行開始

2025年9月29日、山形県尾花沢市役所前で、AIを用いた予約制の公共交通システム「まちなか交通のらっしゃい」の出発式が行われた。市は今年10月1日から来年9月末まで実証運行を行い、持続可能な地域交通の実現を目指す。
AIが最適ルートを算出 市中心部と徳良湖周辺を結ぶ
尾花沢市がAIを活用した新たな公共交通の仕組みを導入した。7人乗りのミニバンを用い、利用者はスマートフォンアプリやLINE、電話から希望の乗降場所や時間を予約する。AIが複数の利用者の行き先をもとに効率的なルートを自動算出し、利便性と効率性を両立させる設計である。
運行エリアは市中心部と観光地・徳良湖周辺で、停留所はスーパーや医療機関、薬局、ごみステーションなど計90カ所に設置されている。地域住民の生活動線を広くカバーする形となった。
出発式では、結城裕市長や市地域公共交通活性化共創協議会の笹原光政会長、運行事業者の尾花沢タクシーの関係者が出席した。
市長は「A Iを使うことで必要な人が適時、適切に利用できる。利用者の声を踏まえ改善し、本格実施を目指す」と述べた。
実証運行は月曜から土曜まで実施し、料金は1回300円(未就学児は無料)と手頃に設定されている。
利便性と持続性の両立 利用定着が課題か
今回の取り組みは、公共交通の維持に苦慮する地方都市にとって先行的な事例といえる。
AIが効率的に運行ルートを組み立てることで、従来型のバス路線より柔軟に需要へ対応できることはメリットだろう。特に高齢者や免許返納者にとっては、自宅近くの停留所から医療機関や商業施設へ容易に移動できる点が大きな利点となりそうだ。
一方で、利用者数が十分に確保されなければ、実証終了後の本格運行に向けた採算性が課題になると予測できる。
スマホやアプリ利用に不慣れな高齢層も多いため、予約手段の周知徹底や操作サポートも必要だろう。
また、AI運行の安定性や混雑時の待ち時間、運行コストとのバランスも検証が求められそうだ。
今後は実証運行での利用データを基に、利便性の改善や停留所配置の最適化が進められることになるだろう。成功すれば他自治体への横展開の可能性もあり、地方の持続可能な公共交通モデルとして全国的に注目されると考えられる。
関連記事:AIデマンド交通「ごしょくる」始動へ 高齢化地域の移動課題に挑む五所川原市
https://plus-web3.com/media/latestnews_1000_5479/