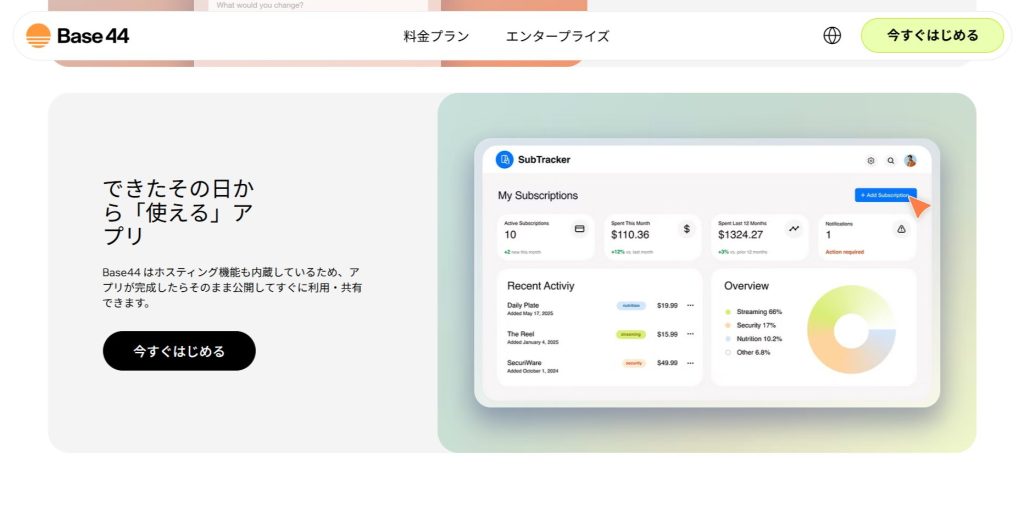スマホのリチウム電池をAIで自動回収 産総研が実証実験を堺で開始

2025年9月25日、国立研究開発法人・産業技術総合研究所(産総研)は、スマートフォンに内蔵されたリチウムイオン電池をAIで自動回収する新システムを開発し、堺市で実証実験を開始すると発表した。2028年以降の実用化を目指す。
AIとX線でスマホ内部の電池を自動分離・回収
近年ごみ処理施設での火災原因として問題視されているのが、スマートフォンやタブレットに内蔵されたリチウムイオン電池である。
処理時に強い衝撃が加わると、発火・発煙する危険性があり、実際に施設での火災が相次いでいる。国立環境研究所の試算によれば、火災による年間被害額は約100億円にのぼるという。
こうした課題を受け、産総研と廃棄物処理大手の大栄環境などのチームは、AIとX線装置を組み合わせた無人回収システムを開発した。
AIが廃棄物の外観からスマホやタブレットを判別し、X線で電池の位置を特定する。そして、その周囲を切断して電池を安全に取り出す仕組みである。
実証実験は大栄環境の堺市内の関連施設で行われる。同施設は1時間あたり最大600台のスマホ・タブレットを処理可能とされ、回収の負担軽減が期待されている。
同システムは廃棄物処理現場の慢性的な人手不足という構造的課題への対応策としても注目される。
産総研の大木達也・首席研究員は「ごみ処理工場の人手不足の解決にも貢献できる。実証実験で得られたデータを基に、『未来のリサイクル工場』を実現したい」と述べ、AIによるごみ処理の未来像を描いた。
「未来のリサイクル工場」構想 人手不足と資源回収に挑む
今回の技術は、リチウムイオン電池の安全な処理だけでなく、リサイクル業界全体の効率化にも資する取り組みといえる。スマホや小型家電に含まれる基板やレアメタルの回収も視野に入っており、資源循環の高度化が今後の焦点となりそうだ。
一方で、デメリットや懸念材料も存在する。
まず、技術的な精度の確保が導入障壁となるだろう。スマホの形状や素材の多様性に対応するには、高度な画像認識や精密な切断制御が不可欠であり、誤作動や誤判別によるリスクも無視できない。
加えて、初期導入コストや運用維持費の高さが、中小規模の処理施設にとって大きな負担となるかもしれない。また、AIが誤って電池を見逃した場合の安全対策も未確立であると考えられるため、制度的・技術的に改善の余地がありそうだ。
今後は自治体や業界団体との連携が進むかどうかが、技術の社会実装を左右するだろう。