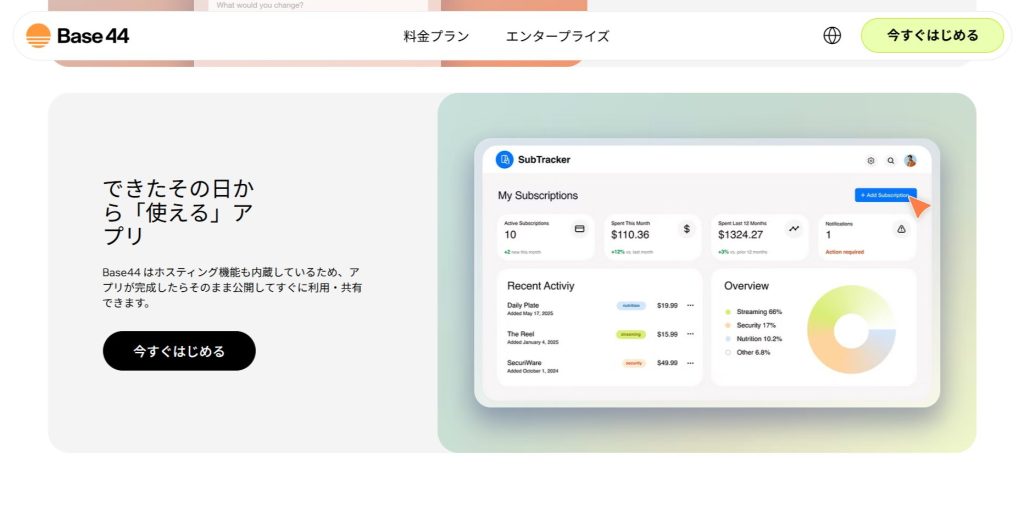YouTube、「Shorts」に生成AI編集ツールを追加 動画制作を一段と簡易化へ

2025年9月16日、米YouTubeは年次イベント「Made on YouTube 2025」で、ショート動画「YouTube Shorts」向けに生成AIを活用した新編集ツール群を発表した。
動画生成や音声加工を容易にする仕組みを導入し、世界中のクリエイターの創作活動を後押しする狙いだ。
AIで動画作成から編集までを一括支援
YouTubeは、Google DeepMindと共同開発した動画生成モデル「Veo 3 Fast」を「Shorts」に統合した。
スマートフォンから任意のプロンプトを入力すれば、480pの動画を低遅延で生成でき、さらに音声付き出力にも対応する。
これにより、短時間でアイデアを映像化することが可能になる。
併せて、静止画に動きを付与する「Add motion」や、ポップアート風などの「Stylize」機能、テキストから物体を挿入できる「Add objects」など、生成AIを活用した複数の新機能が試験導入される予定だ。
これらは数か月以内に「Shorts」で段階的に展開される。
さらに、編集支援機能「Edit with AI」も公開された。
これは端末のカメラロールにある映像素材を自動解析し、最適な場面の抽出、音楽やトランジションの追加、さらには英語やヒンディー語による音声ナレーションを付与する。
ユーザーはゼロから編集する負担を軽減し、仕上げや演出に集中できる。
また「Speech to Song」では、動画内のセリフや音声を抽出し、Googleの音楽生成モデル「Lyria 2」を用いて楽曲化することが可能になる。
これにより、日常的な会話や流行フレーズを即座にサウンドトラックへ変換でき、短尺動画の音楽的な表現力が拡張される。
なお、生成物には透かし技術「SynthID」やAI生成コンテンツ表示ラベルが付与され、透明性が確保される仕組みだ。
創作環境の変化とリスク 新時代の動画制作をどう導くか
今回の一連の発表は、動画制作の民主化をさらに推し進める契機になり得る。
従来、動画制作には編集スキルや時間が必要だったが、AIによる自動生成機能の普及により、初心者や非専門家でも高品質なコンテンツを制作できる環境が整えられる可能性が高い。
結果として、ショート動画市場における競争が一段と活性化し、SNS上での拡散やブランド発信の手段としても価値を高めるだろう。
一方で、生成AIの普及に伴うリスクも指摘されている。著作権やオリジナリティの問題、AIによる誤生成や偏りの懸念は依然として残る。
特に「Speech to Song」のように既存動画の音声を再利用する仕組みでは、オリジナル制作者への適切なクレジットや収益配分が課題となりうる。
今後は、YouTubeが導入する透明性確保の仕組みがどこまで信頼を得られるかが試金石になるだろう。
利用者の創作体験を豊かにする一方で、AI生成コンテンツの倫理的・法的な課題をいかに解決するかが、プラットフォームの持続的な成長に直結すると言える。