NTT-AT、RPA「WinActor」に生成AI標準搭載 10月から新ライセンス提供開始
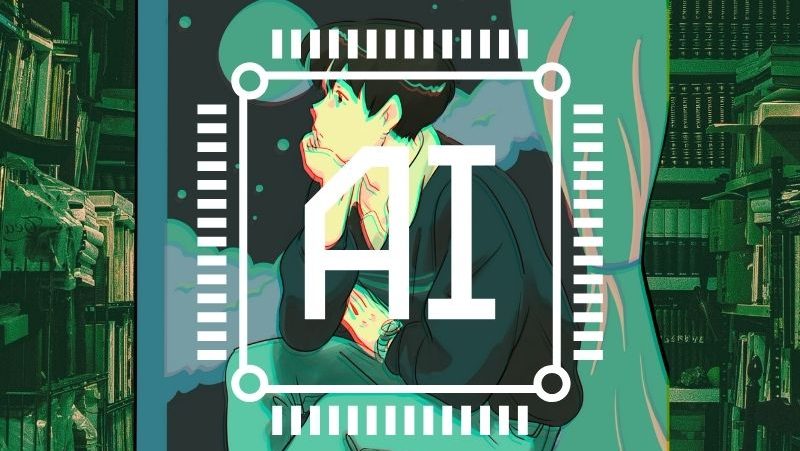
2025年9月4日、NTTアドバンステクノロジ(NTT-AT)は、RPAツール「WinActor」に生成AI機能を標準搭載した新ライセンス「AI連携ライセンス」を発表した。10月中旬より国内販売を開始し、問い合わせ対応や帳票処理などの自動化を強化する。
WinActorが生成AI対応 問い合わせや帳票処理を自動化
NTT-ATは、マイクロソフトの「Azure OpenAI」を利用することで、ユーザーが追加契約を結ばずとも生成AI機能を活用できる新ライセンスを提供する。
ライセンスはフローティング方式を採用し、購入数に応じて複数端末から利用できる。
初期機能は、問い合わせ対応や画像認識との連携、対話によるシナリオひな形生成、簡易な帳票操作の3種類で、今後も追加機能を拡張する予定だ。
価格は年間ライセンス制で、開発・編集・実行が可能なフル機能版が税込219万8000円、実行専用版が60万1000円。
2026年9月末までは生成AIの利用量に制限はないが、翌10月以降は上限が設定され、追加パックの購入が必要となる。
生成AI活用が進む一方、コスト負担と利用制限に課題感
今回の標準搭載は、業務効率化を目指す企業にとって追い風となるだろう。
特に、シナリオ作成や帳票操作をAIが実行できるようになれば、人手不足に悩む中小企業でも活用の余地は広がると見られる。
また、生成AIがRPA(※)に常設されることにより、導入のハードルが下がり、業務プロセス改革の一環として定着する可能性も高い。
一方で、年間数百万円規模のライセンス費用はコスト負担として重く、導入効果が限定的な業務では採算が合わない場合も想定される。
また、2026年以降にAI利用量に上限が課される点は、長期的な運用コストの不透明要因になりかねない。
今後、他のRPAベンダーとの競争が激化する中では、コスト構造の見直しや追加機能の拡充が鍵を握りそうだ。
また、市場が成熟する過程においては、従量課金型や低価格プランなど、柔軟な提供モデルが求められる局面も訪れると考えられる。
※RPA:Robotic Process Automationの略。ソフトウェアが定型的な業務手順を自動実行する技術。












