デンソーと東大、AIで熟練知識を継承 次世代生産システム基盤の共同講座を開設
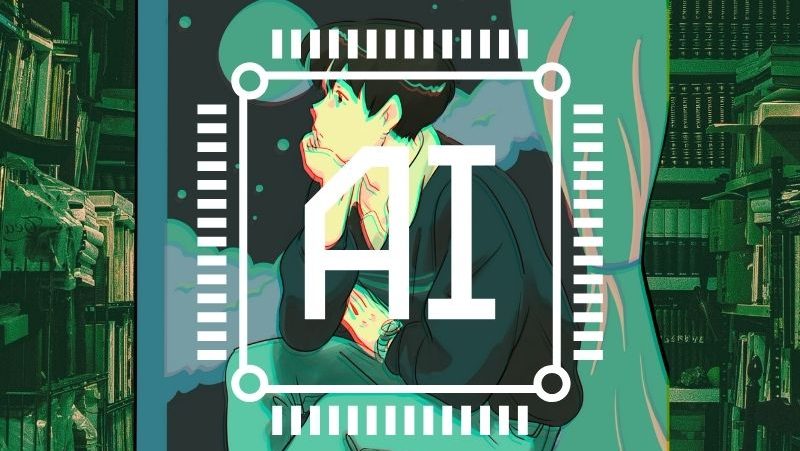
2025年8月28日、デンソーと東京大学大学院工学系研究科は、AI技術を活用した次世代生産システム基盤の構築を目指す社会連携講座を4月1日に開設したと発表した。日本の製造業が直面する人材継承や生産効率化の課題に対する取り組みとして注目だ。
デンソーと東大、AI活用の社会連携講座を始動
新たに設置された社会連携講座は、「AI技術を活用して持続発展する次世代生産システム運用基盤の構築」と名付けられ、2029年3月までの約4年間にわたり研究が進められる。
東京大学大学院工学系研究科に設置され、AI研究で実績のある太田順教授らが主導する。
講座の狙いは、日本の製造業が強みとするリーンマニファクチャリング技術(※)をデジタル化し、AIで高度化することにある。従来は熟練者の経験に依存してきた知識や判断を体系化し、効率性を高めることで、変化に対応できる柔軟な生産体制の構築を目指す。
具体的には、生産現場から得られる稼働データを分析・整理し、改善プロセスを知識化する仕組みを開発する。
また、AIがセンサーデータや工程モデルを組み合わせて異常原因や対策を推論する技術を開発し、これらを蓄積・管理して生産システムの持続的進化を支える基盤を築く。
さらに、得られた研究成果は教育プログラムへと展開され、次世代のモノづくり人材の育成に活用される。デンソーの現場知見と東大のAI研究力を融合し、日本の製造業の課題克服と競争力強化に貢献する構想である。
※リーンマニファクチャリング技術:日本の製造業で発展した、生産工程の無駄を徹底的に排除する手法。トヨタ生産方式が代表例とされる。
AIによる製造業の進化 効率化とリスクの両面を抱える展望
今回の取り組みが実現すれば、製造現場でのデータ活用が一気に進み、従来は熟練者の暗黙知に頼っていた領域を形式知化できる可能性が高い。
知識の体系化によって生産性は大幅に向上し、熟練人材の不足が進む中でも効率的な運用が可能になると考えられる。
また、AIによる異常検知や原因分析は品質保証やリスク管理にも有効で、人間の判断にデータ分析を加えることで安定した生産活動を実現できる。これは国内のみならず、グローバルな製造拠点に展開可能な強みとも言える。
一方で、AIに依存するシステムはサイバーリスクやデータの偏りといった課題も抱える。
熟練者の知識を完全に再現することは難しく、過度に自動化すれば現場の柔軟な対応力を損なう懸念も残る。こうした点は導入企業にとって慎重な検討が必要となる。
将来的には、本講座の成果が標準化されれば、日本の製造業全体に波及し、新たな競争優位の基盤を形成する可能性がある。効率化とリスク管理を両立させることが、長期的な発展を左右する重要な要素となるだろう。
プレスリリース:https://www.t.u-tokyo.ac.jp/hubfs/press-release/2025/0828/001/text.pdf
「AI技術を活用して持続発展する次世代モノづくりインフラの構築」特設サイト:https://denso.fa.race.t.u-tokyo.ac.jp/












