「対話型AIロボット」が展示を案内 GMO系が日本科学未来館で実証開始
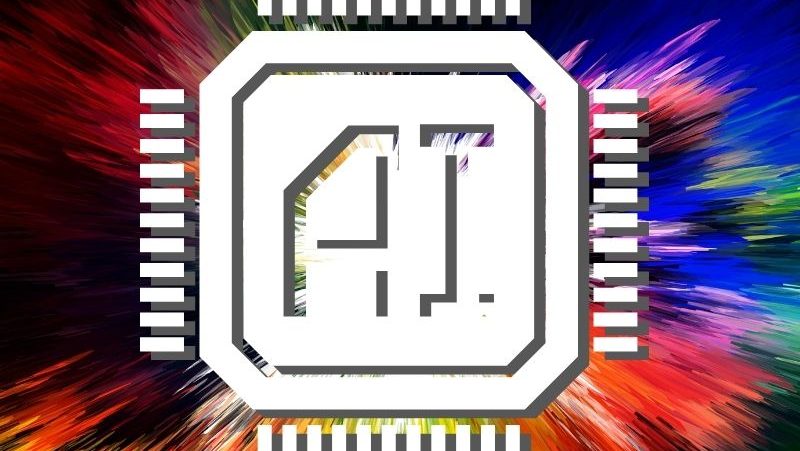
2025年8月25日、GMOインターネットグループ子会社のGMO AI&ロボティクス商事(GMO AIR)は、日本科学未来館(東京都江東区)で対話型AIを搭載したロボットの実証実験を開始した。
来館者への展示解説や案内を担い、サービス向上と業務効率化の可能性を探る。
未来館で多言語対応のAIロボ実証開始
GMO AIRと日本科学未来館が導入したのは、館内を自律的に移動し、英語や中国語など多言語で会話できる対話型AIロボットだ。
来館者が展示内容について質問すると、ロボットは位置情報と外部データを参照し、RAG(検索拡張生成)(※)を活用して回答を生成する。
これにより、来館者が「この展示は何ですか」と尋ねれば、展示に即した解説を行い、場合によっては展示にないテーマにも対応できる。
初日のデモンストレーションでは、地球温暖化に関する質問に応じて現象を解説したほか、気候変動の展示エリアへ案内する動作も披露した。
さらに「2100年の気温」といった展示外の問いにも答える柔軟性を見せた。
実験は31日まで行われ、機能面だけでなく、文化施設での業務効率化やサービス品質向上への有効性を検証する。
GMO AIRの内田朋宏社長は「全国の博物館や美術館などで課題となっている労働力の減少という課題を解決する一助になりたい」と強調し、全国展開を視野にカスタマイズ性の高い仕組みづくりを進める意向を示した。
※RAG(検索拡張生成):外部データを検索し、その情報をもとに大規模言語モデル(LLM)が回答を生成する手法。AIの知識精度を補完し、最新情報を反映できる特徴がある。
AIロボ普及が文化施設運営を変える可能性
今回の実証は、文化施設が抱える人材不足や多言語対応の負担を軽減する技術として期待される。
来館者が増加する国際イベントや観光需要において、ロボットが案内役を務めれば、サービス品質を維持しつつ運営コストを削減できる利点がある。
一方で、展示ごとに異なる説明内容や案内方法を正確に組み込むには、データ整備やローカライズに相応の労力が必要になる点は課題となりそうだ。
さらに、対話型AIには誤情報を生成するリスクも伴う。展示内容と乖離した説明を行えば、教育機関としての信頼性に影響する可能性がある。
そのため、AIの回答を監修・調整する運用体制の確立が不可欠であろう。技術面では、GMO AIRが導入したAIエージェントの仕組みが開発効率を押し上げ、アプリ実装の約8割を自動生成する成果を挙げている。
こうした効率化が進めば、今後は中小規模の施設にも普及しやすくなるだろう。
文化体験とテクノロジーの融合が進む中で、今回の実証は「AIによる展示解説」の社会実装に向けた重要な一歩になると考えられる。












