ChatGPTが方針転換 前モデル「GPT-4o」再び利用容易に
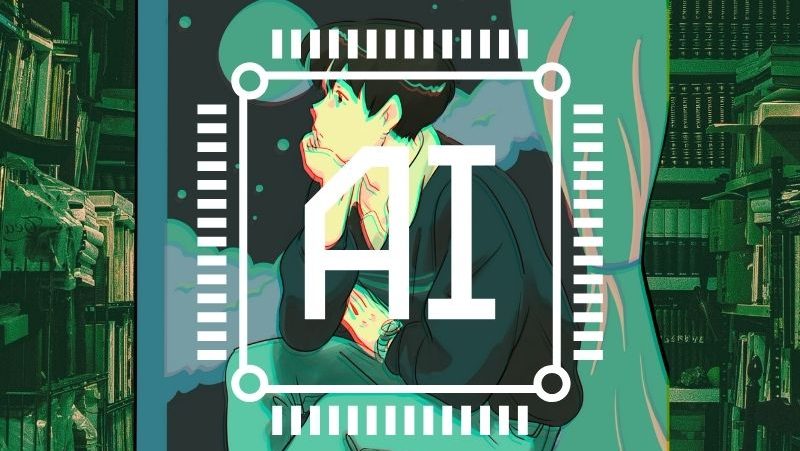
2025年8月13日、米OpenAIのサム・アルトマンCEOは、対話型AI「ChatGPT」に関する複数のアップデートを発表した。
最新モデル「GPT-5」の改善に加え、前モデル「GPT-4o」を有料ユーザーが再び利用しやすくする方針転換を明らかにした。
GPT-5に3モード追加、GPT-4oも選択可能に
OpenAIは8月13日、最新モデル「GPT-5」に「自動(Auto)」「高速(Fast)」「思考(Thinking)」の3つの動作モードを新たに導入した。
自動モードは状況に応じ最適化され、多くの利用者に推奨される。
一方、高速モードは応答速度を優先し、思考モードは複雑な推論や長文生成に適する設計となる。思考モードのコンテキスト長は19万6000トークンで、週あたり3000メッセージのレート制限が設けられている。
今後の利用状況に応じて制限変更の可能性もあるという。
さらに、有料ユーザー向けに高性能モデル「GPT-4o」がモデル選択画面に再びデフォルト表示されるようになった。
将来的に提供終了する場合は、事前に十分な告知期間を設けるとしている。
設定変更により「o3」や「4.1」、「GPT-5 Thinking mini」など追加モデルも利用可能で、GPUリソースを多く消費する「GPT-4.5」は現状Proプラン限定だ。
OpenAIはまた、GPT-5の「パーソナリティ」も改善予定で、温かみを持ちながら煩わしさを抑える個性を目指す。
最終的にはユーザーごとにモデルの人格をカスタマイズできる環境の実現を視野に入れている。
モデル選択肢拡大で利用体験は柔軟に、だが運用課題も
今回の方針転換は、GPT-5の性能向上とユーザーの多様なニーズを同時に満たす狙いがあると考えられる。
特に、GPT-4oの再表示は、親しみや会話の柔らかさを重視するユーザー層にとって歓迎されるだろう。
また、3つのモードによる制御は、開発者やビジネス利用者がプロジェクト内容や処理要件に応じた最適設定を選択できる利点をもたらす。
一方で、複数モデルの併存は管理コストの増大や学習リソースの分散を招く可能性がある。
特に高性能モデルはGPU消費が大きく、利用制限やプラン間の格差が顕著になる恐れも否めない。
また、パーソナリティのカスタマイズ性向上は、ブランド統一感とのバランスや悪用防止策が課題となり得る。
今後、OpenAIにはユーザー体験の自由度向上と、システム運用効率の両立が求められるだろう。
市場では他社もカスタマイズ性や応答制御機能の強化を進めており、同社の動向は生成AIの利用環境全体に影響を与えると考えられる。












