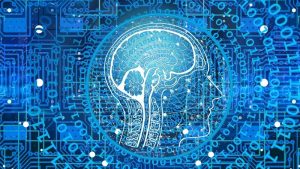YouTube、「AI使用=収益化不可」の誤解を否定 新ポリシーは“量産動画”への対応強化
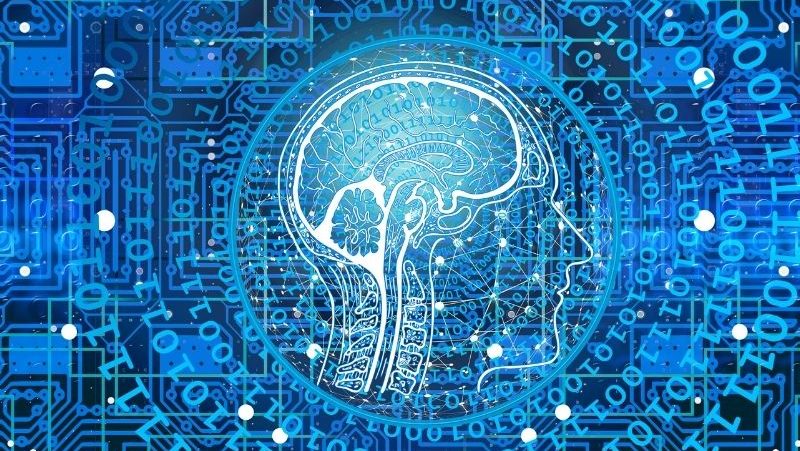
2025年7月11日、米GoogleはYouTubeの収益化制度「パートナープログラム」に関する新ポリシーの補足情報を公表した。AIの使用自体は収益化に影響しないと明言し、対象は“本物でない”量産型コンテンツであると説明している。
AI使用は収益化可能、対象は「本物でない」動画
Googleは、YouTubeパートナープログラム(YPP)のポリシーを2025年7月15日から改定すると発表していたが、内容が不明瞭だった点について補足説明を行った。
特に注目が集まったのは、AI技術の使用が収益化にどのような影響を及ぼすかという点である。
改定されたポリシーでは、「本物でないコンテンツ」や「反復的な内容の動画」の収益化を制限することが明示された。Googleは今回の説明で、これは新たな制限ではなく、既存のガイドラインをより正確に適用するための更新だと強調した。
対象となるのは、大量に生成されたコンテンツや、再利用された無個性な動画などであり、AIの利用そのものを制限するものではないという。AIを用いた動画であっても、オリジナリティや視聴者価値が認められれば、これまで通り収益化は可能である。
また、AIによって改変・合成されたコンテンツを公開する際には、視聴者に対してその旨を明確に表示することが求められる。これにより、透明性と信頼性の確保を図るという。
Googleは、ポリシー変更は視聴者がスパム的と感じやすい動画をより的確に排除するための措置であり、健全なエコシステムの維持を目的としたものと説明している。
質の担保がカギ 生成AI時代のクリエイター戦略とは
今回のポリシー補足により、生成AIを用いたコンテンツでも「質」が伴えば収益化の道が開かれていることが明確となった。これは多くのクリエイターにとって、AIとの共存に向けた重要な指針となる。
一方で、低品質なAI動画の大量投稿が増加している現状を鑑みれば、YouTube側が規制を強化するのは当然の流れとも言える。視聴者体験を損なう反復的・スパム的な動画が収益対象となることは、広告主やプラットフォーム全体の信頼性低下につながるリスクがあるためだ。
今後の展望としては、YouTubeが導入する新たなアルゴリズムやAI判定システムが、どこまで「オリジナル」と「量産」を精緻に見分けられるかが焦点になる。
収益化の可否がシステム判断に委ねられる以上、クリエイター側にも一定の透明性や説明責任が求められる時代が到来している。
また、マーケティングやビジネス戦略の観点からは、AI活用を前提とした「ハイブリッド制作体制」の構築が鍵となる。AIを補助的ツールとして活用しつつ、企画や編集、演出といった人間の感性が求められる工程に注力することが、今後の差別化要因となるだろう。