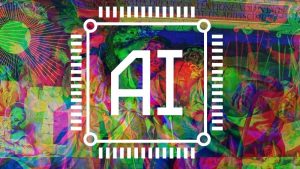NEC、生成AIで法規制対応を自動化 品質管理部門で実証、属人化リスクを解消へ
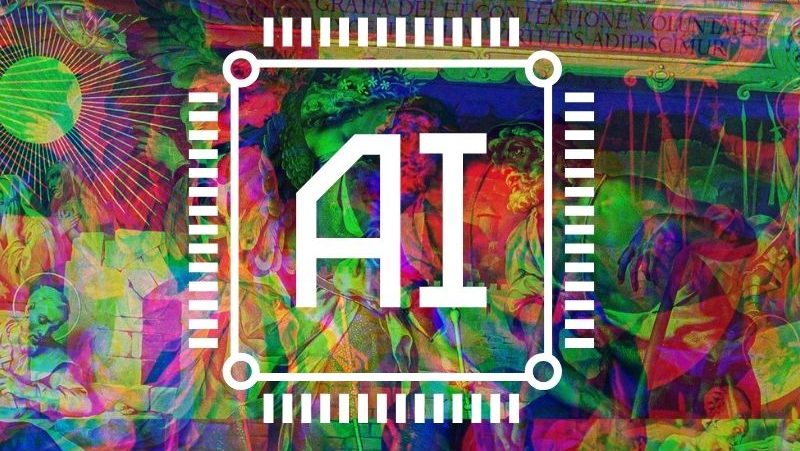
2025年7月1日、NECは国内で複雑化する法規制対応業務の効率化に向け、生成AIを活用したソリューションの社内実証を進めていることを発表した。
品質管理部門での現場検証を通じ、属人化や対応漏れといったリスクの解消を目指す。
NEC、生成AIで法規制業務を変革 社内現場でプロトタイプ検証
NECは、国内外で急速に複雑化する法規制対応業務において、生成AIによる支援ソリューションの開発に着手している。2025年7月1日、その一環として品質管理部門で実証実験を進めていることを明らかにした。
現行業務は担当者ごとの知識や経験に依存する場面が多く、工数増大や情報共有の非効率、対応漏れリスクが課題となっていた。
そこでNECは、法規情報の解釈支援AIを組み込んだ業務システムのプロトタイプを開発した。これにより、これまで人手で行っていた法改正情報の収集、内容解釈、対応要否の判断、具体策の策定といったプロセスをAIが支援する。
実証の対象は、業務プロセスに沿ったUI/UX設計の最適化、生成AIのアウトプット精度、作業負荷軽減効果など複数観点に及ぶ。
同社はこの実証で得られるデータをもとに、機能の精度向上とUI改善を加速させる方針だ。
生成AIによる法規制対応のメリット・デメリット
NECによる生成AIの法規制対応業務への導入には、いくつかの明確なメリットがある。
第一に、属人化によるリスクを低減できる点が挙げられる。
これまで経験や個人スキルに依存していた法規制対応が、AIによる知識支援で標準化されることで、判断ミスや対応漏れのリスクが減少する効果が期待できる。
また、法改正の情報収集や内容解釈、対応策立案といった工程が自動化されれば、作業工数が大幅に削減され、リソースを他の重要業務に振り向ける余地が生まれるだろう。
加えて、UI/UX設計において現場業務に最適化されたプロトタイプを用いることで、現場担当者の負荷軽減や導入時の定着率向上も見込める。
DMS2025(7月9〜11日、幕張メッセで開催)で公開予定というタイミングからも、短期間での市場投入を見据えた開発体制が整いつつあることがうかがえる。
一方で、デメリットもある。
特に生成AIの特性として、誤った解釈や不完全なアウトプットによるコンプライアンスリスクが新たに生じる懸念は拭えない。法規制対応は企業の事業継続に直結するクリティカルな業務であるだけに、AIによる判断ミスは重大な法令違反や取引停止リスクを招く可能性がある。そのため、AIのアウトプットに対するダブルチェック体制や人による最終確認プロセスは不可欠であろう。
また、現段階ではAIの精度が十分とは言えず、現場での実運用にはまだ課題が残ると考えられる。