廃棄物処分場の水質をAIで予測 住吉工業とNTT Comが地方発DXモデル構築
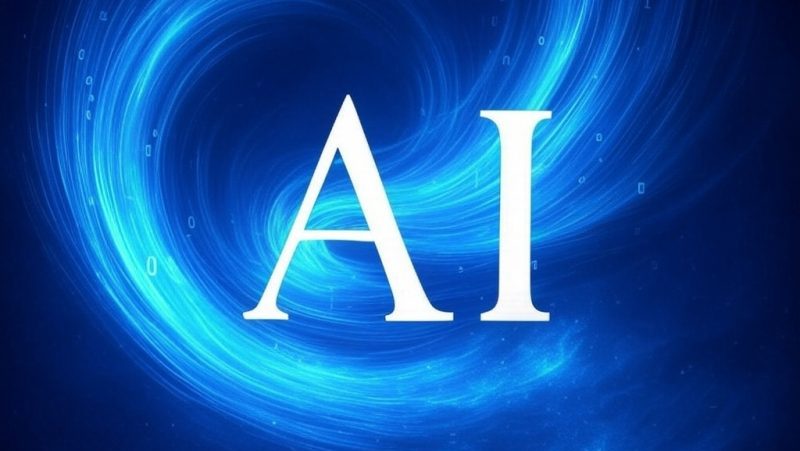
2025年5月15日、日本国内で産業廃棄物処理業を手がける住吉工業が、山口県下関市の最終処分場においてAIを活用した水質予測モデルを開発したと発表した。NTTコミュニケーションズの技術支援を受けたこの取り組みは、労務負担の軽減と水質管理の高度化を同時に実現する新たなDX事例として注目されている。
水質点検の課題をAIで解決 Node-AI活用による実用モデル
住吉工業が管理する最終処分場では、排水のpHや水温が環境基準を超えないよう、日々の測定が不可欠となっている。従来は365日体制で作業員が点検を実施していたが、これが休日勤務や危険作業による負担、人件費の増加といった課題を生んでいた。
こうした背景のもと、同社はNTTコミュニケーションズと連携し、ノーコードAI開発ツール「Node-AI(※)」を活用して自社内で予測モデルを構築。過去の水質データや外部環境情報を学習させることで、2日後の放流水質を高精度で予測する仕組みが完成した。
導入後の検証では、87.5%の予測結果が許容誤差内に収まり、現場での判断に活用できるレベルに達したという。
この技術によって、住吉工業は年間約504時間の作業時間削減を見込んでおり、人件費にして100万円以上のコスト削減につながるとされる。水質データの即時活用が可能となることで、突発的な対応の回避にもつながり、より安全な運営体制の構築が進んでいる。
精度向上と多地点対応へ 今後の課題と展望
今後、住吉工業は気象庁のデータと連携した高度な予測モデルの構築を目指しており、水質変化に影響を及ぼす外部因子との相関をより正確に反映できる可能性がある。
この動きが順調に進めば、より高精度かつ柔軟性のあるシステムへの進化が期待できる。
さらに、複数地点での水質予測を同時に実行するモデル開発も進行中であり、処分場全体の運用最適化が図られる見通しである。
一方で、現時点では87.5%という予測精度は実用水準とされているものの、残りの約12.5%が許容範囲を超えており、環境基準を外れた排水の可能性を完全には排除できないだろう。
現場の安全と法令遵守を考慮するならば、AI任せにしすぎる運用には慎重さが求められると考えられる。また、モデルの適用範囲は限られており、多地点対応や天候変動への追従には今後の改良が不可欠といえるだろう。
導入・運用コストやデータ蓄積のハードル、現場との連携体制など、AI活用に必要な基盤整備には一定の課題が残るとみられる。
これらを乗り越えるためには、技術支援だけでなく制度的・経済的支援の充実も併せて求められていくと考えられる。
AIと地域社会との共存が持続的な形で成立するには、今後のフォローアップと段階的な導入戦略がカギになるだろう。
※Node-AI:NTTコミュニケーションズが提供するノーコード型AI開発ツール。プログラミングの専門知識を持たない担当者でも、予測や分類といった機械学習モデルを構築・運用できる点が特徴。












