ドコモ×落合陽一ら、6G時代の“AIネットワーク”を活用した次世代ロボット3体を発表
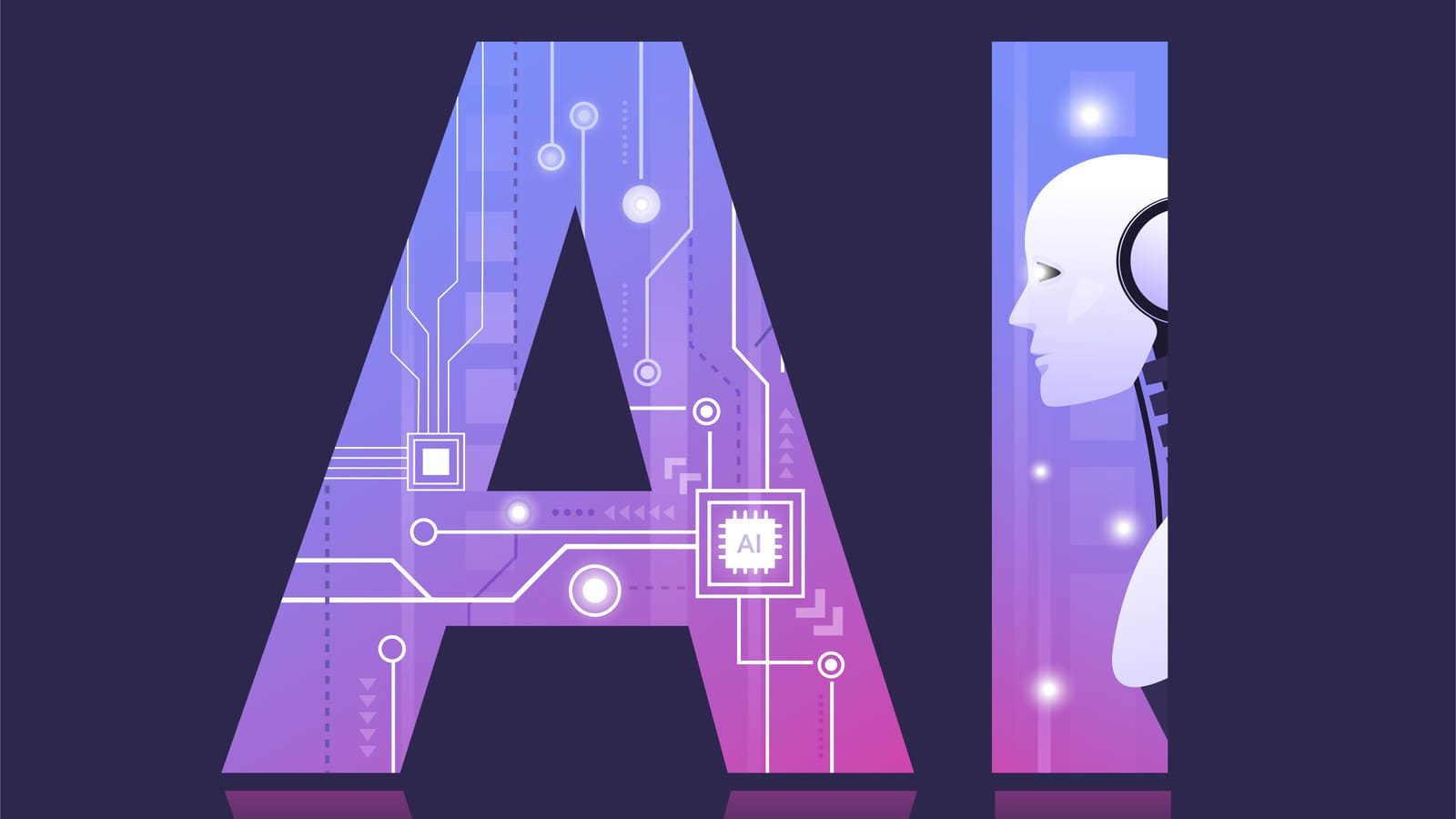
2025年5月19日、NTTドコモはアスラテック、ピクシーダストテクノロジーズ(PxDT)、ユカイ工学と共同で、6G時代の「AI用ネットワーク」を活用した3種のコンセプトロボットを開発したと発表した。
6Gを前提としたネットワークとAIの融合を実証する試みであり、2030年代の社会実装を見据えた先行的な取り組みとして注目できる。
センサレス制御から自律共存型まで、6Gが拓くロボットの未来像
ドコモが主導する「6G Harmonized Intelligence」プロジェクトの一環として、3種のロボットコンセプトが開発された。
プロジェクトの根幹にあるのは、6G通信が持つ超低遅延・大容量という特性を、AIやロボットの高度化に直接活用するという構想だ。
まず、アスラテックと共同開発された「ハーモナイズドセンサレスロボット」は、機体にセンサやカメラを搭載せず、外部のセンサ群とカメラによるフィードバックで制御される。
6Gのリアルタイム性により、物理的な部品の削減とコスト最適化が両立されている。
次に、落合陽一氏率いるPxDTと筑波大学のデジタルネイチャーグループが関与した「コンポーザーとグルーバー」は、人間との対話を重視し、AIがクラウド側でリアルタイム推論を実行する。
感性や身体性の共有を通じて、共創的なインターフェースの可能性を探る内容となっている。
さらに、ユカイ工学との協業による「DENDEN」は、都市や自然環境において人と共存しながら自律的に活動するロボットである。
「AIのためのネットワーク」構想が描く、産業応用と社会実装への可能性
3体はいずれも、2030年代に想定されるAIロボット社会の実証的ステップであり、デバイス設計やユーザーインターフェースの検証も進められている。
ドコモが掲げる「AIのためのネットワーク」という構想は、従来の人間中心の通信設計から脱却し、AIやロボットといった“非人間的存在”の活動効率を最大化する発想に立脚している。
この視点の転換は、将来的なスマートシティ構想や、超高齢化社会でのサービス提供において大きな意味を持つ。
たとえば、センサレス構造を採るロボットは、軽量でエネルギー効率にも優れるため、屋内移動支援や物流分野での活用が見込まれる。
また、人間の感性に寄り添うロボットは、教育や医療など高いコミュニケーション能力が求められる分野に展開できる可能性がある。
DENDENのような自然共存型ロボットは、地域特化型のサービスにも適応が可能だ。
一方で、6G自体の標準化やインフラ整備、AIの精度向上など、多くの技術的・制度的課題が残されていることも事実である。
企業や自治体がこれらの技術をどう活用していくかが、6G時代のロボット社会実現の鍵を握ることになるだろう。












