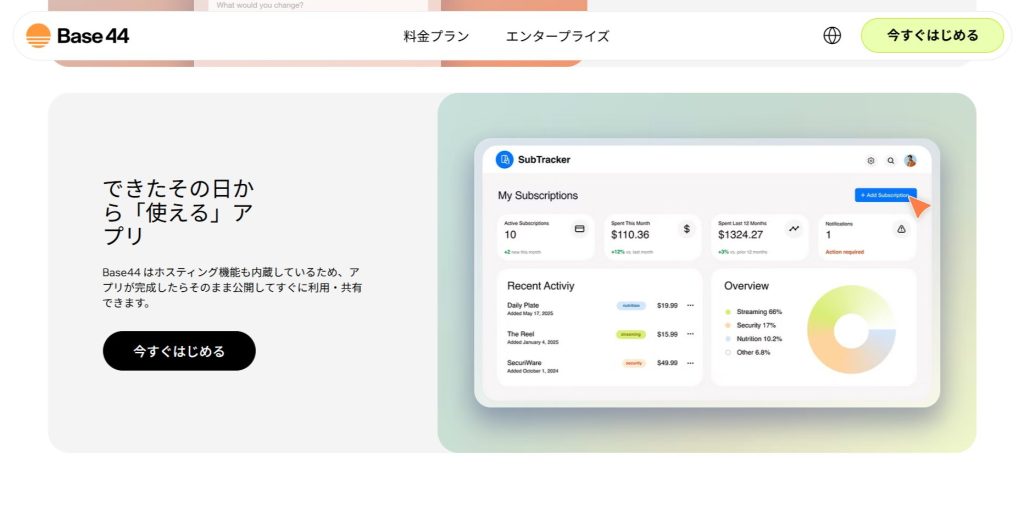「AI」が発明者として認められず、知財高裁が特許出願を棄却

2025年1月30日、日本の知的財産高等裁判所は、人工知能(AI)が発明者として特許を取得できるか否かを巡る訴訟で、「発明者は自然人に限る」との判断を下した。
本件は米国の技術者が自身の開発したAIを発明者として記載し、特許を申請したことが発端となっている。しかし、日本の特許法が想定する「発明者」にAIは含まれないとして、特許庁の却下決定が支持された。
発明者の定義と知財高裁の判断
知財高裁は、特許法が定める「発明者」が自然人に限られることを明確に示した。原告は、自身が開発したAI「DABUS(※)」が独自に食品容器を考案したとして、発明者欄にDABUSを記載して特許を出願した。しかし、特許庁はこれを拒絶し、原告はその決定を不服として訴訟を起こした。
2024年5月に東京地裁は、「特許法が想定する発明者とは自然人を指す」として原告の請求を棄却。その後の控訴審でも、同様の判断が下された。
特許法第29条において「発明」とは「自然法則を利用した技術的思想の創作」と定義されており、この規定は人間による創作活動を前提としていると解釈される。
また、特許法第36条では、発明者の氏名を出願書類に記載することが求められており、これも自然人を想定している要因となった。
※DABUS米国の技術者スティーブン・テイラー氏が開発したAIシステムで、独自にアイデアを創出する能力を持つ。
今後の法的課題と社会的議論
今回の判決は、AIが発明者として特許を取得することは現行法では不可能であることを示した。しかし、AI技術の発展に伴い、AIが関与する発明の扱いについて法改正の必要性が議論される可能性がある。
現在、欧米でも同様の議論が進んでいる。
米国では特許庁がAIを発明者とする特許を拒否しており、英国でも同様の判断が下されている。一方で、南アフリカではAI発明の特許が認められた事例がある。
各国の対応が分かれる中、日本の特許制度が今後どのような方向へ進むのかが注目される。
技術革新が進む現代において、AIが独自に発明を行うケースは今後増加すると考えられる。法律専門家の間でも「AIを発明者とする特許制度の導入を検討すべき」という意見がある一方、「AIはツールであり、発明の主体は人間であるべき」との慎重な立場も根強い。
今後の特許制度の在り方を巡る議論は、「技術と法のバランスをどのように取るか」という重要な課題を浮き彫りにしたのではないだろうか。