グーグル「NotebookLM」が進化、ウェブ上の情報を即座に登録できる新機能を追加
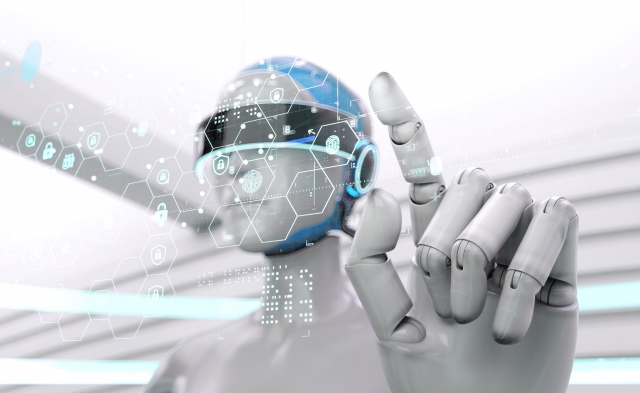
2025年4月2日、Googleは生成AIノートアプリ「NotebookLM」において、ウェブ上のソース(情報)を直接インポートできる新機能「Discover sources(提供元を見る)」を追加したと発表した。AIを活用した情報整理と要約のプロセスが一層スピーディーになることが期待される。
資料収集から活用までのプロセスを縮めるアップデートの中身
今回発表されたNotebookLMの新機能では、ソースの登録をWebから検索・選択して簡単に登録できる機能を追加。
ユーザーが任意のワードを検索すると、ウェブページや媒体資料のPDFなど関連情報が最大10個まで候補として表示され、追加したいソースを選んでNotebookLMに登録できるという。
NotebookLMでは、登録したソースをもとにチャットでやり取りしながら情報を引き出すこともできる。また、登録したPDFやドキュメントなどの内容のみに基づいて回答が生成されるため、誤情報(ハルシネーション)のリスクを抑えつつ、データを活用できる「AIリサーチアシスタント」として機能するという。
登録済みのソースから要約したり、複数のソースから必要な内容を抽出したり、FAQを作成したりといった使い方が可能である。さらに、内容を音声で紹介するPodcast風の「Audio Overview」も生成できるが、現時点では英語対応のみとしている。
この新機能では、Geminiの技術が活用されており、本日からNotebookLMの全ユーザーに順次反映され、すべてのユーザーが使えるようになるまでに1週間ほどかかる見通しだ。
ナレッジワーカーにとっての価値と今後の展望
本機能は特に、日々膨大な情報に触れるナレッジワーカーにとって、即戦力になりうる。
信頼性の高い情報をウェブ上で発見した瞬間、そのままNotebookLMに取り込み、文脈に即した質問や要点抽出をAIに任せることが可能になるため、調査・分析・提案といった一連の業務プロセスが効率化されるだろう。
また、生成AIの信頼性が課題とされる中、「登録された情報の範囲内」で回答するという設計は、慎重なユーザー層にも支持されやすいと見られる。
一方で、情報の正確性や著作権とのバランス、またユーザーごとのリテラシー差に対する配慮といった課題はまだ残されていると考えられる。
特に、自動で要約・抽出された情報の誤解釈や過信を避けるためには、今後も人間による確認と判断を組み合わせるプロセスが求められると考えられる。
生成AIが情報の「使いやすさ」を高める一方で、「正確性」を担保するための補助機能の充実については、引き続き開発が期待されるだろう。












