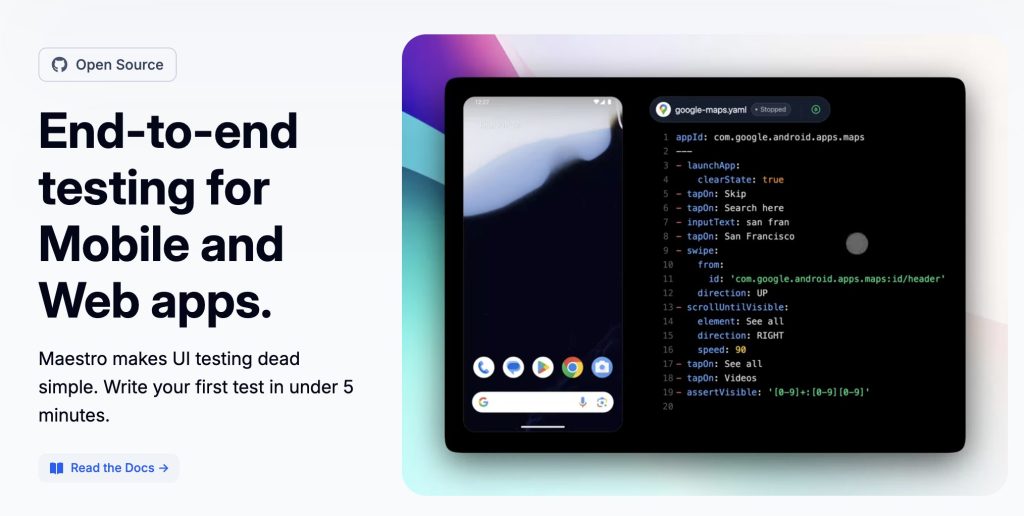日本のテック企業Ridge-iとJAXA、衛星データ活用した地球デジタルツインでAI実証に成功

2025年3月24日、日本のテック企業Ridge-iが、宇宙航空研究開発機構(JAXA)との共同研究において、地球デジタルツイン(※)構想におけるAI活用の実証を行ったことが明らかになった。
このプロジェクトは2023年11月に一般競争入札で採択されたもので、GPT-3.5やGPT-4などの生成AIを用いて、衛星観測データから地球環境に関する情報を提供するシステムを構築している。
対話型AIプロトタイプで衛星データをリアルタイム解析
Ridge-iが開発したプロトタイプは、ユーザーの質問に応じて適切な外部データを呼び出し、解釈して回答する対話型AI形式となっている。
このシステムは、JAXA Earth APIやGoogle Earth Engine APIなど複数のデータソースを活用し、専門知識を持たないユーザーでも衛星データにアクセスできる環境を実現した。
具体的な使用例としては、「2020年1月1日の関東の地表面温度の最大値は?」という質問に対して「約12.8度です。GCOM-C衛星のデータを解析した結果です」と回答するケースなどが挙げられる。
また、「2020年1月のシンガポール海域付近の様子は?」という質問に対して、衛星画像を提供することも可能だという。
JAXAの「Earth-graphy」や「サテナビ」といった衛星データプラットフォームとの連携により、多角的なデータ分析が実現されている。
JAXAのデータを応用することで、地球環境の現状把握や変化の予測など、幅広い用途での活用が期待されるところだ。
「AI on TOP」の概念で衛星データ活用を促進
Ridge-iはこのプロジェクトにおいて、「AI on TOP」という概念に基づいた技術基盤を開発している。
「AI on TOP」は、プランニング機能、データインターフェース、処理エンジンインターフェース、解釈機能、提案機能、そしてユーザーとのシームレスな接続という6つのコンポーネントから構成されている設計思想だ。
対話型のツールを開発することで、専門知識がない人でも惑星データの取得と分析ができることを目標にした考え方となっている。
この技術基盤により、衛星データの取得と解析が容易になり、専門知識がなくても利用できる環境が整いつつある。Ridge-iによれば、今後は特定領域での衛星データ活用を促進し、徐々に活動範囲を広げていく計画とのことだ。
将来的には、異なる領域間の連携や、一般消費者による衛星データの活用を促進することを目指しているようだ。このようなデジタルとグリーン分野の融合により、環境監視や災害対策など、社会課題の解決に向けた新たなアプローチが生まれる可能性が高いと考えられる。
※地球デジタルツイン:現実世界の地球環境をデジタル空間上に再現し、シミュレーションや分析を行うための技術。衛星データなどを活用して地球の状態をリアルタイムで把握・予測することを目指している。